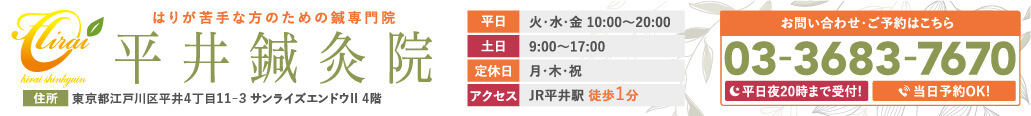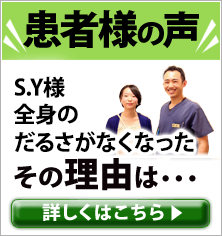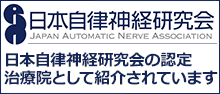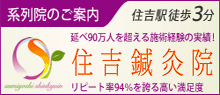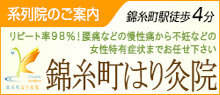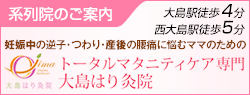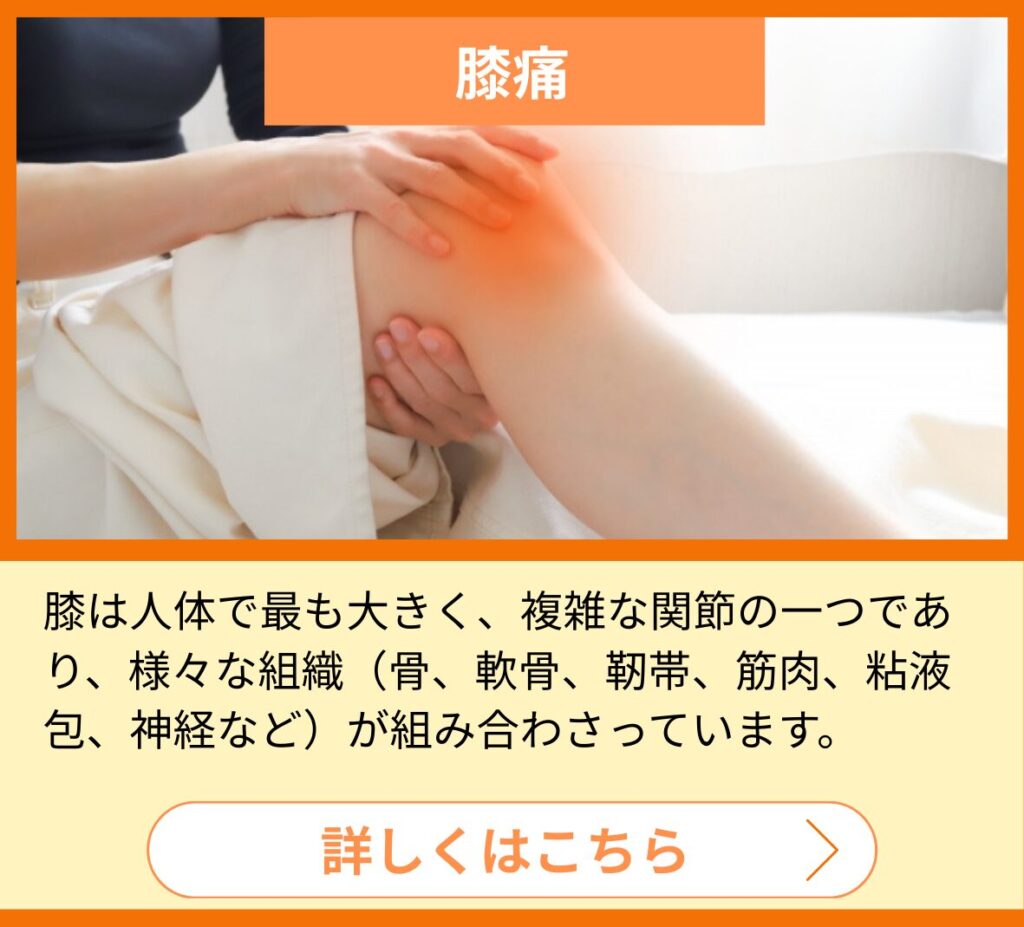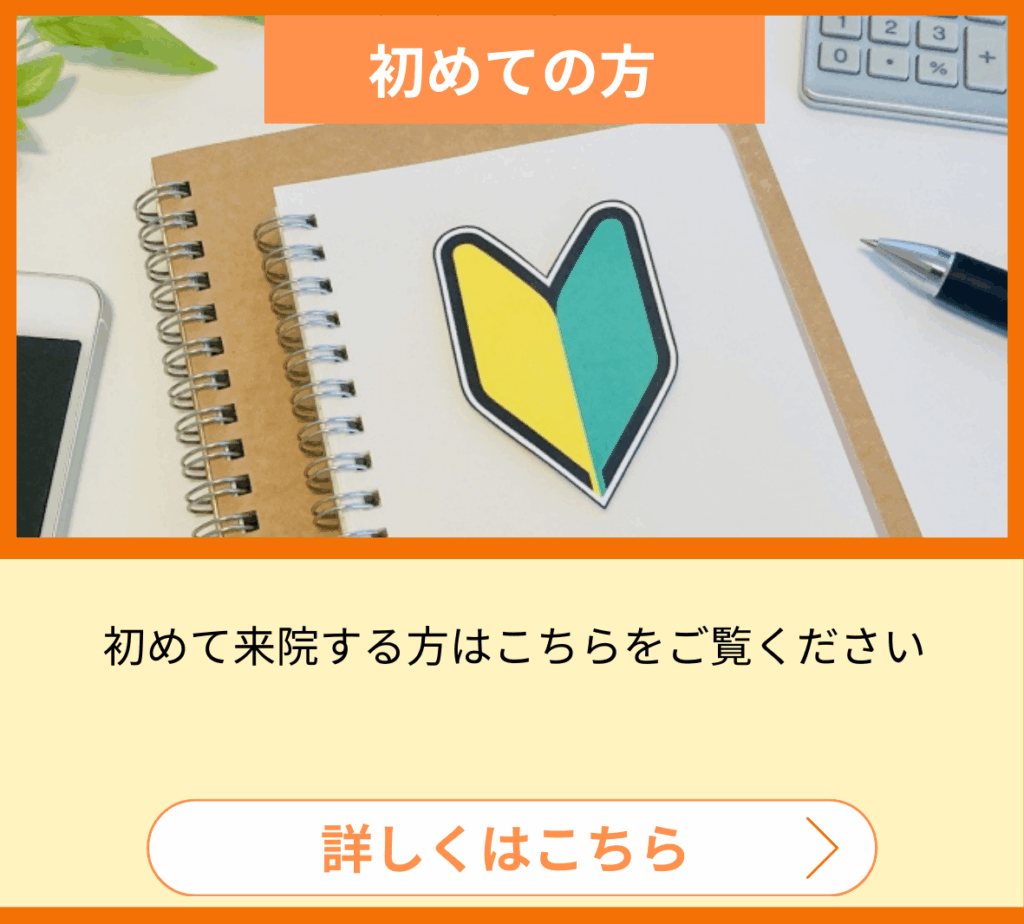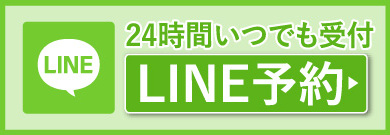変形性膝関節症と自律神経の関係 ― 鍼灸で目指す痛みと体質の改善
「階段の上り下りで膝が痛い」「立ち上がるときに膝がギクッとする」
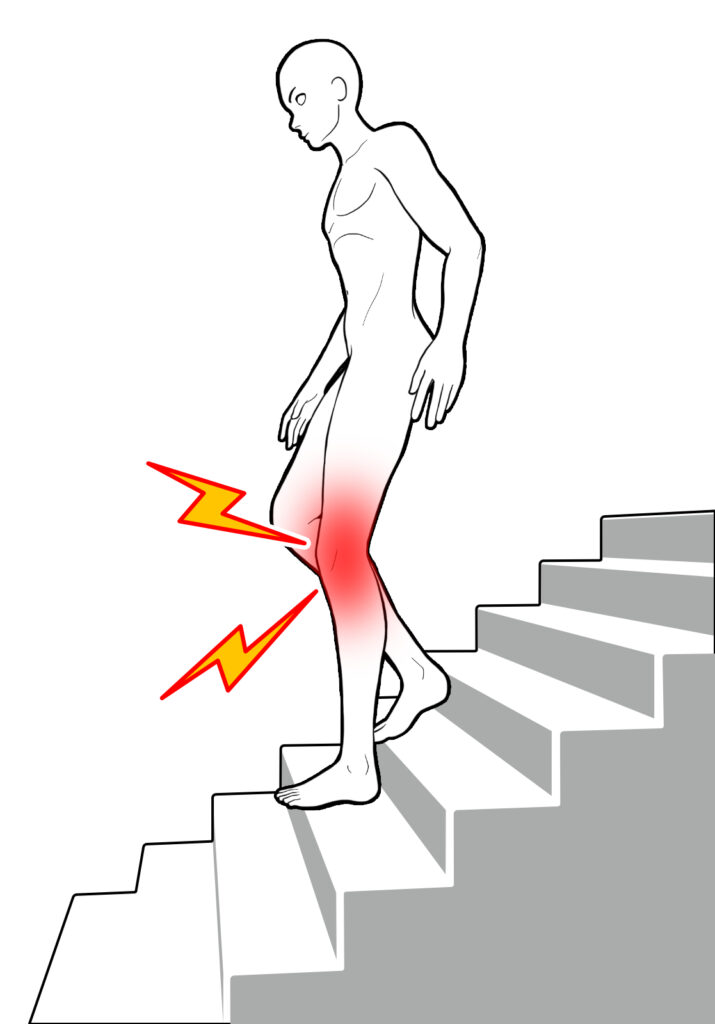
こうした訴えで来院される方は非常に多く、年齢・運動習慣・体重など生活の要因が強く関わります。変形性膝関節症は単なる“軟骨のすり減り”ではなく、関節周囲の骨・滑膜・靭帯・筋肉・神経・循環・代謝が複雑に関係する全身的な慢性疾患です。ここでは症状・病態(なぜ痛むのか)を西洋医学的に深掘りし、自律神経とのつながり、さらに東洋医学(鍼灸)的な見立てまで詳しく解説します。
変形性膝関節症とは?
変形性膝関節症は、膝関節の軟骨(関節軟骨)が変性・摩耗することで関節の構造と機能が徐々に変化し、痛み・可動域制限・機能障害を来す慢性疾患です。病変は関節軟骨だけでなく、以下のような周辺組織にも広がります。
軟骨の摩耗・亀裂:弾力とクッション性の低下
亜骨(亜骨)・骨棘形成:関節形態の変化
滑膜炎:滑膜の炎症による痛みと水腫(関節液貯留)
靭帯・半月板の退行変性:安定性低下や局所負荷の偏り
筋力低下・筋バランスの崩れ:大腿四頭筋など支持筋の機能低下
これらが組み合わさって「痛み→運動回避→筋力低下→さらなる負荷増大」という悪循環に入ることが多く、早期介入と総合的な対策が重要です。
症状(どのように現れるか)
変形性膝関節症の典型的な臨床像は以下の通りです。
荷重時の疼痛:歩行・階段昇降・立ち上がりで増強する膝の痛み
動作開始時のこわばり:朝のこわばりや動き始めの痛み(数分〜十数分)
関節可動域制限:曲げ伸ばしが制限される、正座や深く曲げる動作が困難
腫脹・熱感:滑膜炎による一時的な腫れや温感
異音(軋轢音):関節内部の摩耗によるクリック音やギシギシ音
歩行パターンの変化:痛み回避による代償動作や跛行、筋力低下に伴う転倒リスク増加
症状の程度は軟骨損傷の程度だけでなく、筋力、心理的要素、日常活動レベル、体重など多くの因子で決まります。
西洋医学的視点:原因と病態生理(なぜ進行するのか)
変形性膝関節症は多因子疾患で、以下の要素が相互に作用します。
1. 生体力学的負荷の偏り
軟骨は荷重分散の役割を担いますが、関節形態の不整合(アライメント不良)、靭帯や半月板損傷、筋力低下(特に大腿四頭筋)により特定部位に過大な負荷がかかると、軟骨の摩耗が進行します。肥満は膝への荷重を増やし、進行を早めます。
2. 軟骨の代謝的変化と炎症
加齢や機械的刺激で軟骨細胞(コンドロサイト)が変性し、マトリックス分解酵素(MMPs)や炎症性サイトカイン(IL-1β、TNF-αなど)が増加。これが軟骨基質(コラーゲン・プロテオグリカン)を分解し、軟骨の弾性・耐圧性を低下させます。また滑膜は炎症反応を引き起こし、痛みや関節液の増加を助長します。
3. 骨の反応(亜骨硬化・骨棘)
軟骨減少に伴い亜骨は過剰な応力を受けて反応性に骨増殖(骨棘)や亜骨硬化を起こし、これがさらなる関節機能障害と痛みの原因になります。
4. 神経学的要素(疼痛発生機序)
関節周囲の骨膜・滑膜・靭帯・筋膜は痛覚受容器(ノシセプター)に富み、そこからの侵害受容性疼痛が主。長期化すると中枢性感作(脊髄・脳での痛み増感)も生じ、痛みと不快感が過剰になります。また部分的に神経成長因子(NGF)等の上昇が痛み感受性を高めます。
5. 代謝・全身因子
糖代謝異常や慢性炎症、性差(女性に多い)、遺伝的素因も進行に関与します。閉経後の女性ではホルモン変化が軟骨代謝に影響することが報告されています。
全体として、機械的負荷+炎症性反応+神経感受性の変化が複合して症状を生むのが病態の本質です。
自律神経との関係 — 痛み・循環・回復の観点から
自律神経(交感・副交感)は膝関節の痛み・循環・修復過程に重要な影響を与えます。主な関連点は次の通りです。
局所血流の調節:交感神経が過剰に働くと局所血管が収縮して血流が低下し、栄養供給・老廃物除去が滞ることで修復が遅れ、痛みが持続しやすくなる。逆に適切な副交感優位や血流改善は回復を助ける。
炎症反応の修飾:自律神経は免疫系と連携して炎症の強さを調整する。交感神経と副交感神経はサイトカイン産生に影響し、慢性炎症の持続に関与する。
筋緊張と運動パターン:交感優位は筋緊張を高め、関節周囲筋のバランスを乱して関節への負荷を増やす。これが悪循環を生む。
痛みの知覚と中枢感受性:ストレスや不眠で交感神経が亢進すると痛みの閾値が下がり、同じ刺激でも強く痛みを感じるようになる(中枢性感作の促進)。
代謝・体重管理との関連:自律神経の乱れは代謝調節にも影響を与え、体重増加やインスリン抵抗性を通じて膝への負荷を高めることがある。
したがって、変形性膝関節症のマネジメントでは痛みそのものへの介入に加え、自律神経バランスの改善(睡眠・ストレスケア・適切な活動)が症状改善と再発予防に重要です。
東洋医学から見た変形性膝関節症(弁証と治療観)
東洋医学(中医学)的には、膝の痛みは「気血の停滞(瘀血)」「寒湿の侵入」「腎の虚弱」などの病理と結び付けられます。臨床的な弁証の代表例と対応は以下の通りです。
代表的な弁証パターン
寒湿阻滞(かんしつそたい):寒冷や湿気で痛みが重く、天候で増悪。触れると冷感を認める場合が多い。治療は温陽除湿を意図する。
瘀血阻滞(おけつそたい):外傷や長期の負担で血行が滞る。鋭い刺すような痛み、圧痛点がはっきりする。活血化瘀(血の流れを改善)を目標とする。
腎精不足・腎気虚(じんけつそん):年齢による衰弱や慢性化で、膝に力が入らない、夜間の痛みや腰のだるさも伴う場合。補腎・強腰を行う。
痰湿(たんしつ)・気血両虚:肥満や消化力の低下を伴い、関節に重だるさや浮腫感がある場合。運化を助け湿を除く方針。
鍼灸的介入の考え方(概説)
局所と遠隔の併用:膝周囲の阿是穴(圧痛点)や膝眼(しつがん)、陽陵泉・陰陵泉・足三里・委中など下肢の経穴を組み合わせ、局所の気血循環を改善する。
温補的手法:寒湿タイプには温灸や温熱刺激で陽気を補い血流改善を図る。
活血化瘀手法:瘀血が強い場合は瀉法や吸角(カッピング)等で瘀血の除去を補助する。
体質補正:腎虚や気血虚には補法(補腎、補気養血)を行い、再発しにくい支持力のある体を作る。
全身調整:自律神経の安定を目的に内関・神門・百会などを併用し、疼痛に伴う不眠・不安を軽減する。
東洋医学は「膝の痛み=局所問題」だけでなく、全身の気血水バランスと臓腑の状態を整えることで長期的な改善を目指す点が特徴です。
まとめ
変形性膝関節症は単なる「軟骨のすり減り」ではなく、生体力学的負荷・軟骨代謝・滑膜炎・骨の反応・神経感受性・自律神経・全身代謝が複雑に絡み合う多面的な慢性疾患です。痛みの緩和だけでなく、筋力・アライメント・体重管理・睡眠・ストレスケアといった全身的アプローチが重要になります。東洋医学(鍼灸)は局所の血流改善と全身のバランス調整を通じて疼痛軽減と再発予防に寄与できるため、保存的対応の一つとして有用です。症状や生活への影響が大きい場合は専門家と連携して、個別の方針を検討してください。
関連記事はこちらから
info_outline平井鍼灸院
- 住所
- 〒132-0035
東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号
 03-3683-7670
03-3683-7670
- 営業時間
- 火金 10:00~20:00
水 12:00~20:00
土 9:00~17:00
日 9:00~16:00 - 休業日
- 月曜・木曜・祝日
- アクセス
- JR総武本線平井駅から徒歩1分