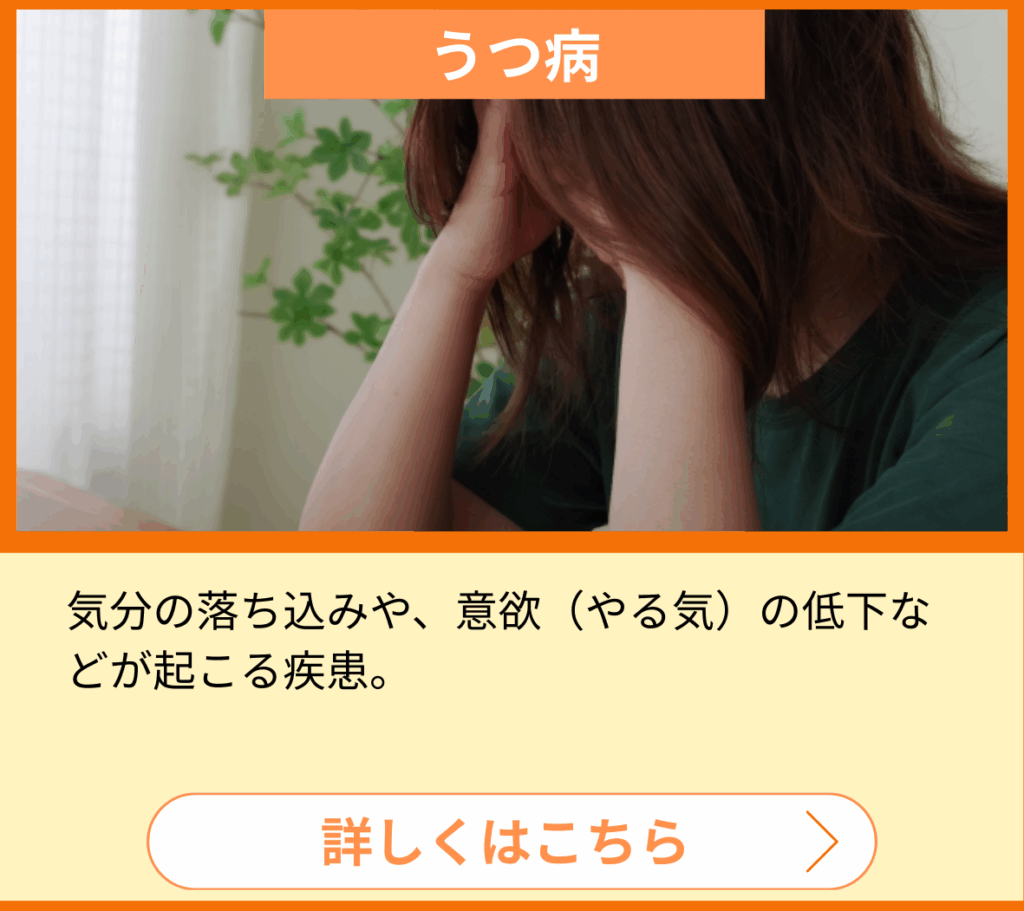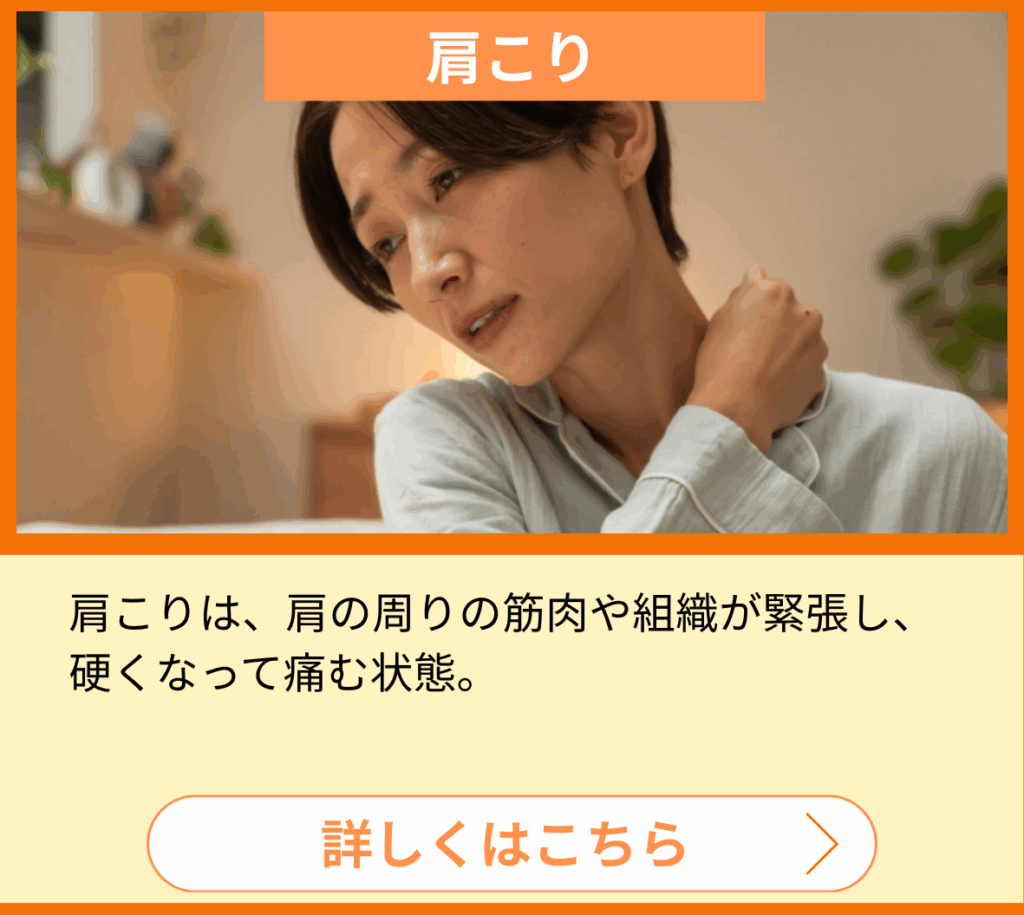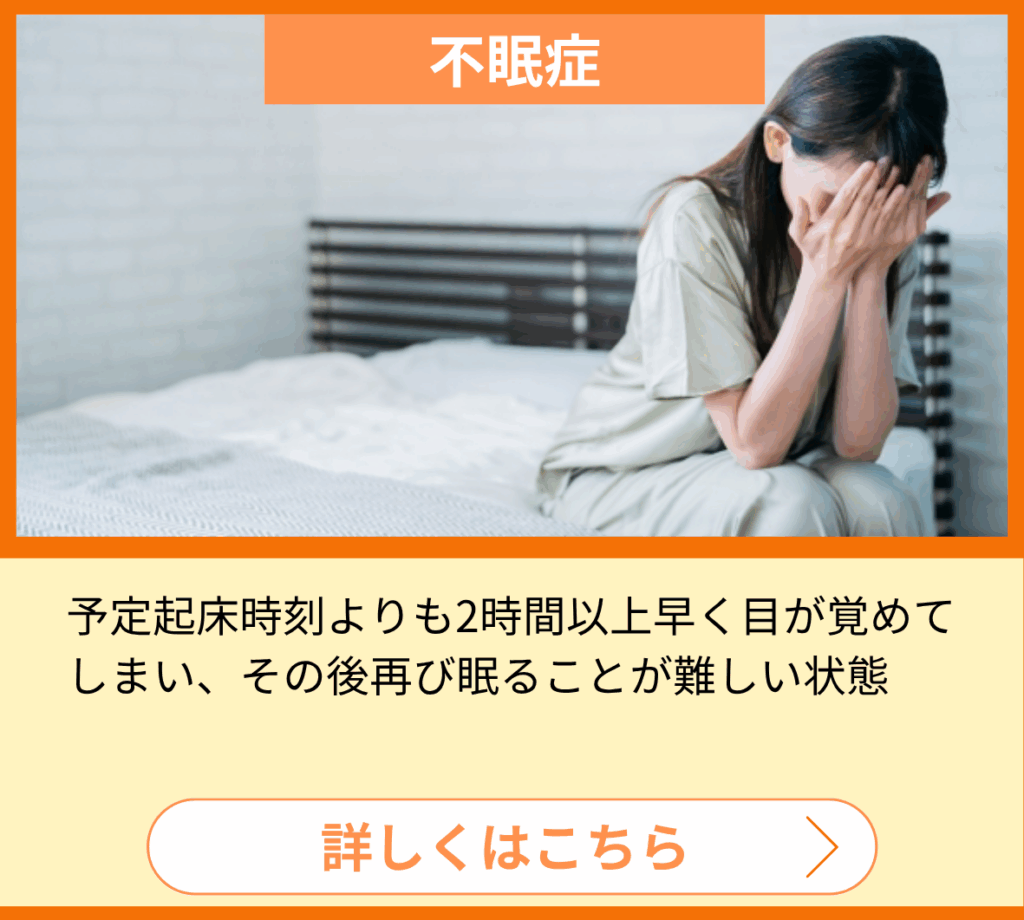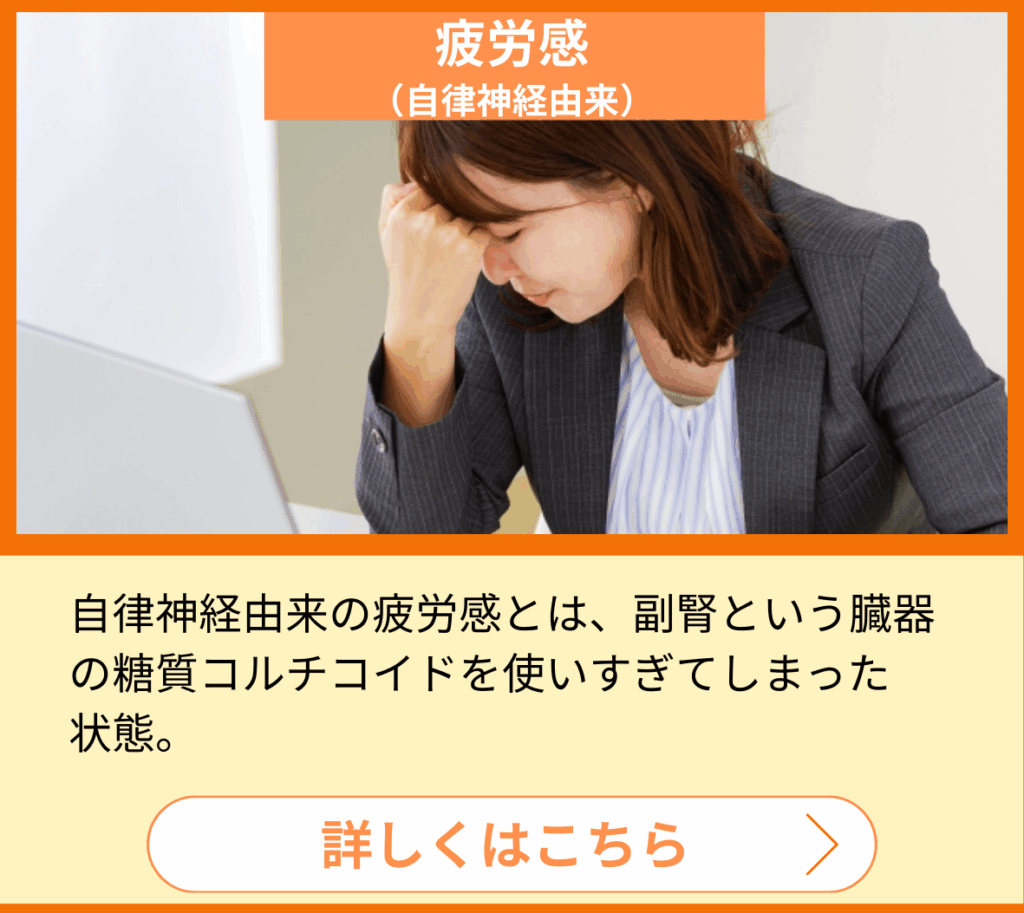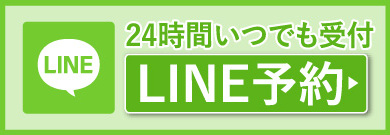HSPの治療法とは?薬や心理療法でうつを予防する具体的な方法

HSPは病気ではないため、HSPそのものに対する直接的な治療法は確立されていません。
しかし、HSPの気質が原因で生じる生きづらさやストレスが、うつ病などの精神疾患につながることはあります。
そのため、HSPに関連する治療とは、主にカウンセリングなどの心理療法や、併発した精神症状を和らげるための薬を用いたアプローチを指します。
これらの方法は、二次的な不調の予防と症状の緩和を目的として行われます。
HSPは治療の対象?まず知っておきたいHSPの基本
HSPは医学的な病名ではなく、生まれ持った気質を指す言葉であるため、それ自体が治療の対象となるわけではありません。
精神科や心療内科における診断基準にも含まれていません。
しかし、HSPの特性によって日常生活で強いストレスを感じ、うつ病や不安障害といった精神的な不調を併発することはあります。
その場合、治療の対象となるのは、HSPの気質ではなく、併発した精神疾患や具体的な症状になります。
HSPは病気ではなく生まれ持った「気質」
HSP(HighlySensitivePerson)とは、生まれつき感覚が鋭敏で、非常に感受性が強く、刺激に対して敏感な特性を持つ人を指す言葉です。
これは米国の心理学者エレイン・アーロン博士が提唱した概念であり、病名ではありません。
HSPには「深く処理する(物事を深く考える)」「過剰に刺激を受けやすい(疲れやすい)」「感情反応が強く共感力が高い」「ささいな刺激を察知する(光や音、匂いなどに敏感)」という4つの特性があるとされています。
全人口の約15~20%がこの気質を持つといわれており、特別なものではなく、あくまで個人の特性の一つとして捉えられています。
治療はHSPに伴う「生きづらさ」を軽くすることが目的
HSPは生まれ持った気質であるため、その特性自体を根本的に変える「治し方」は存在しません。
治療の目的は、HSPの特性をなくすことではなく、それに伴って生じる生きづらさや精神的な苦痛を軽減することにあります。
具体的には、外部からの刺激に過敏に反応して疲弊してしまったり、他者の感情に振り回されてしまったりする状況を、本人がうまくコントロールできるように支援します。
自身の特性を正しく理解し、適切な対処法を身につけることで、ストレスを溜め込みにくくし、精神的な安定を図ることが治療のゴールとなります。
HSPの悩みを相談できる病院での主な治療アプローチ
HSPの特性による生きづらさが深刻化し、日常生活に支障をきたすようになった場合、心療内科や精神科などの医療機関で相談することが可能です。
病院では、HSPという気質そのものではなく、そこから派生したうつ病や不安障害といった二次的な精神疾患に対して、専門的な治療アプローチが行われます。
主な方法として、カウンセリング、薬物療法、そして近年注目されているTMS治療などが挙げられます。
専門家との対話を通して自己理解を深めるカウンセリング
カウンセリングは、臨床心理士や公認心理師といった専門家との対話を通じて、自身の悩みや課題に向き合う心理療法です。
HSPの人は、自分の感じ方や考え方が他人と違うことに悩み、自己肯定感が低くなりがちです。
カウンセリングでは、そうした自身の特性を専門家と共に客観的に見つめ直し、ネガティブな思い込みを修正していく作業を行います。
認知行動療法などの手法を用いて、ストレスへの具体的な対処法を学んだり、繊細さを強みとして捉え直したりすることで、生きづらさの軽減を目指します。
安全な環境で自分の内面を語る体験は、孤立感の解消にもつながります。
不安や落ち込みを和らげるための薬物療法
HSPの気質そのものに効果を示す薬は存在しません。
薬物療法は、HSPの特性が原因でうつ病や不安障害、パニック障害などを併発し、日常生活に支障が出ている場合に行われます。
処方される薬は、気分の落ち込み、強い不安、不眠といった具体的な症状を緩和することを目的としています。
例えば、セロトニンなどの脳内神経伝達物質のバランスを整える抗うつ薬や、強い不安発作を抑える抗不安薬などが用いられます。
薬によって症状が安定することで、心に余裕が生まれ、カウンセリングなどの心理療法に集中しやすくなるという効果も期待できます。
磁気の力で脳機能に働きかけるTMS治療
TMS(経頭蓋磁気刺激法)治療は、うつ病などに対して行われる比較的新しい治療法です。
専用のコイルを頭部に当てて磁気を発生させ、脳の中でも気分のコントロールに関わる「背外側前頭前野」などの特定の部位を刺激します。
これにより、機能が低下している脳の働きを活性化させ、うつ症状の改善を目指します。
TMS治療は、薬物療法で十分な効果が得られない場合や、薬の副作用が強い場合に有効な選択肢となり得ます。
副作用が少なく、治療期間も比較的短いという特徴がありますが、実施している医療機関が限られており、保険適用外の自由診療となることも多いです。
日常生活で実践できるHSPの特性を活かすセルフケア
HSPの生きづらさを和らげるためには、専門家による治療だけでなく、日常生活の中で自分自身でできるセルフケアを取り入れることが非常に重要です。
自分の特性を理解した上で、刺激を調整したり、物事の捉え方を変えたりする工夫が有効な方法となります。
ここでは、日々の暮らしの中で実践できる具体的なセルフケアの方法をいくつか紹介し、ストレスを軽減しながらHSPの特性をポジティブに活かす道筋を探ります。
音や光など五感への刺激を減らすための環境調整
五感が鋭いHSPにとって、過剰な刺激は心身の疲労に直結します。
そのため、意識的に刺激をコントロールする環境調整は、有効なセルフケア方法です。
自宅では、照明を暖色系の間接照明に変えたり、遮光カーテンを利用したりして光の刺激を和らげることができます。
外出先や職場など騒がしい場所では、ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンや耳栓を活用すると音の刺激を遮断できます。
また、肌触りの良い天然素材の衣類を選んだり、香りの強い柔軟剤を避けたりすることも、不快な刺激を減らす工夫になります。
自分にとって快適な空間を確保し、こまめに休息をとることが大切です。
繊細さを「強み」として捉え直す思考のトレーニング
HSPの繊細さは、疲れやすさや気分の落ち込みにつながる反面、豊かな感受性や優れた共感力、物事を深く考える力といった強みにもなります。
この特性を短所としてではなく長所として捉え直す思考のトレーニングも、有効なセルフケアの方法です。
例えば、日記をつけ、その日に自分の繊細さがプラスに働いた出来事を書き出してみる習慣は自己肯定感を高めます。
また、物事を深く洞察できる能力を、仕事や趣味における分析、企画、創作活動などに活かす意識を持つことで、自分の特性を価値あるものとして受け入れられるようになります。
繊細さを武器と捉える視点を持つことが重要です。
人との適切な距離感を保ちストレスを軽減する方法
共感力が高く、他者の感情の影響を受けやすいHSPにとって、人間関係におけるストレス管理は重要な課題です。
すべての人に合わせようとすると心身が消耗してしまうため、自分と他者との間に適切な境界線(バウンダリー)を引く意識が有効な方法です。
相手の機嫌を損ねることを恐れず、無理な頼みは断る勇気を持つことや、SNSを見る時間を制限して情報過多を防ぐことも大切です。
また、大人数の集まりは避け、信頼できる少数の人々と深く関わるなど、自分にとって心地よい人間関係を選択していくことで、不要な精神的負担を大幅に減らすことができます。
自分と似た特性を持つ人と交流できるコミュニティに参加する
HSPの繊細さは周囲から理解されにくく、そのために孤独感や疎外感を抱えてしまうことがあります。
このような場合、自分と似た特性を持つ人々と交流できるコミュニティに参加することも有効なセルフケアの方法です。
オンラインのSNSグループや当事者会など、HSPの人が集まる場では、自分の感覚や悩みを安心して共有できます。
「自分だけではなかった」という安堵感を得られるだけでなく、他者の経験談からストレス対処のヒントをもらえることも少なくありません。
共感し合える仲間とつながることは、大きな精神的な支えとなり、自己受容を促すきっかけにもなります。
HSPの二次障害で起こる「うつ」と薬に関する正しい知識
HSPであること自体は病気ではありませんが、その繊細さゆえに日常的に多くのストレスを抱え込みやすく、結果としてうつ病や不安障害といった二次障害を引き起こすリスクが高いとされています。
二次障害の治療においては薬が用いられることもありますが、これはHSPの気質を治すものではなく、併発した精神症状を緩和するためのものです。
ここでは、HSPに伴ううつと、その治療で使われる薬について正しく理解しておくべき点を解説します。
HSPの特性ではなく併発した症状に対して薬が処方される
医療機関でHSPに関連して薬が処方される場合、HSPという気質そのものを変えるためのものではありません。
薬物療法の対象となるのは、HSPの特性が引き金となって生じた精神的な不調、すなわちうつ病や不安障害、適応障害などによって現れる具体的な症状です。
例えば、持続的な気分の落ち込み、意欲の低下、不眠、食欲不振、動悸、強い不安感といった症状を緩和する目的で薬が使用されます。
医師はこれらの併発した疾患を診断し、その治療の一環として、症状の改善と本人の苦痛軽減のために薬の処方を検討します。
治療で使われる抗うつ薬や抗不安薬の種類と効果
HSPが併発しやすい、うつ病や不安障害に対する薬物療法では、主に脳内の神経伝達物質の働きを調整する薬が用いられます。
代表的な抗うつ薬として、セロトニンの濃度を高めるSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)や、セロトニンとノルアドレナリンの両方に作用するSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)などがあります。
これらの薬は、気分の落ち込みや不安感を和らげ、意欲を高める効果が期待されます。
また、突発的な強い不安や緊張を抑えるために、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬が頓服として処方されることもありますが、依存性の観点から使用は慎重に行われます。
薬物療法を受ける際に注意すべき副作用のリスク
薬物療法には、効果だけでなく副作用のリスクが伴います。
特に抗うつ薬は、飲み始めの時期に吐き気、眠気、頭痛、めまいといった副作用が現れることがあります。
これらの症状は、体が薬に慣れるにつれて数週間で軽減することがほとんどです。
HSPの人は薬に対しても敏感に反応する可能性があるため、医師はごく少量から処方を開始し、慎重に増量していくのが一般的です。
まれに血圧の変動やふらつきなどが起こることもあります。
自己判断で服用を中止すると離脱症状が起こる危険性があるため、気になる症状があれば必ず処方した医師に相談することが重要です。
市販の精神安定剤を自己判断で服用することの危険性
ドラッグストアなどで手軽に購入できる、いわゆる「精神安定剤」や睡眠改善薬は、医療機関で処方される医薬品とは成分も作用も異なります。
これらは植物由来の成分などが中心で、一時的なイライラや気分の落ち込み、軽度の不眠を緩和する目的のものがほとんどです。
しかし、うつ病などの精神疾患が背景にある場合、これらの市販薬では根本的な改善は見込めません。
自己判断での服用を続けることは、適切な治療を受ける機会を遅らせ、かえって症状を悪化させる危険性があります。
精神的な不調が続いている最中であれば、安易に市販薬に頼らず、専門医の診察を受けるべきです。
HSPの治療についてどこに相談すればいい?
HSPによる生きづらさを感じ、専門的なサポートを求めたいと考えたとき、どこに相談すればよいか迷うかもしれません。
ここでは、HSPに関連する悩みを相談できる代表的な場所と、それぞれの特徴について説明します。
心療内科や精神科を受診するタイミングの見極め方
気分の落ち込みや不安感が2週間以上続く、夜眠れない、食欲がわかない、仕事や家事など普段できていたことが手につかないといった状態は、医療機関の受診を検討すべきサインです。
特に、消えてしまいたいという気持ち(希死念慮)が少しでも頭をよぎる場合は、すぐに精神科や心療内科を受診する必要があります。
HSPへの理解がある医療機関を探すことも大切ですが、まずはつらい身体的・精神的症状を緩和することが最優先です。
日常生活に深刻な支障が出ていると感じたら、ためらわずに専門家の助けを求めてください。
医療機関以外にもあるカウンセリングルームという選択肢
病気というほどではないけれど、人間関係の悩みや日々の生きづらさについて専門家とじっくり話したいという場合には、民間のカウンセリングルームを利用するのも一つの良い方法です。
カウンセリングルームでは、医師による診断や薬の処方は行われませんが、臨床心理士や公認心理師による専門的な心理療法を受けることができます。
医療機関よりも時間をかけて話を聞いてもらえることが多く、自分のペースで思考を整理し、自己理解を深めたい場合に適しています。
公的な相談機関や大学の心理相談室など、比較的安価に利用できる場所もあります。
まとめ
HSPは病気ではなく、生まれ持った気質です。
そのため、HSPそのものを対象とした直接的な治療法はありません。
しかし、その特性から生じる生きづらさやストレスが、うつ病などの二次障害につながることもあります。
治療のアプローチは、主にカウンセリングで自己理解を深めたり、併発した症状に対して薬物療法を行ったりすることで、苦痛を和らげることが目的です。
また、日常生活でのセルフケアも同様に重要となります。
お客様の声
info_outline平井鍼灸院
- 住所
- 〒132-0035
東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号
 03-3683-7670
03-3683-7670
- 営業時間
- 火金 10:00~20:00
水 12:00~20:00
土 9:00~17:00
日 9:00~16:00 - 休業日
- 月曜・木曜・祝日
- アクセス
- JR総武本線平井駅から徒歩1分

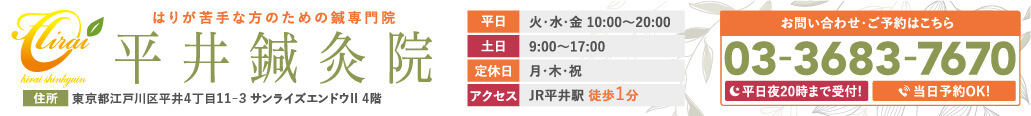

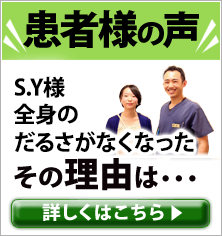
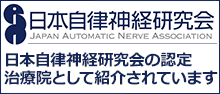
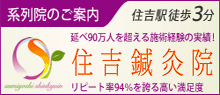

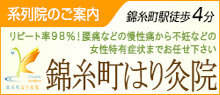
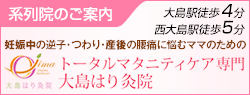
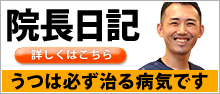
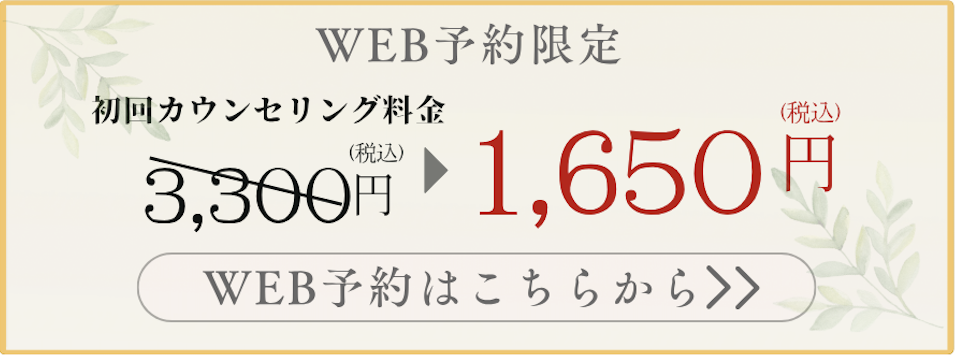

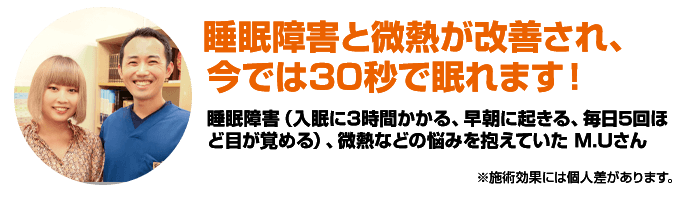
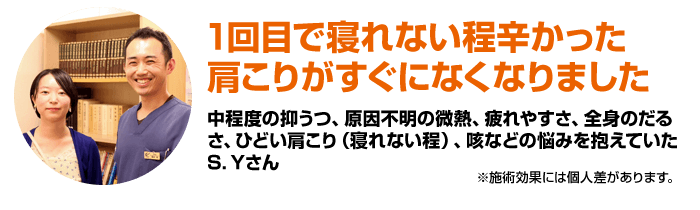
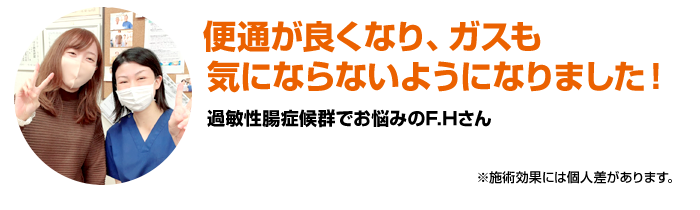
 【監修】
【監修】