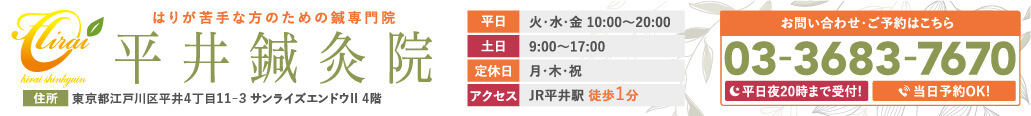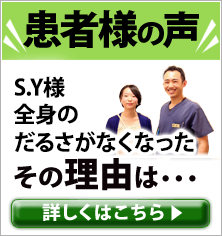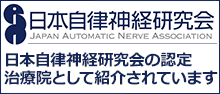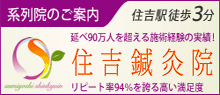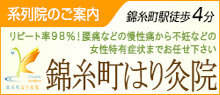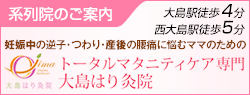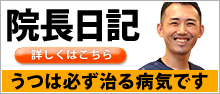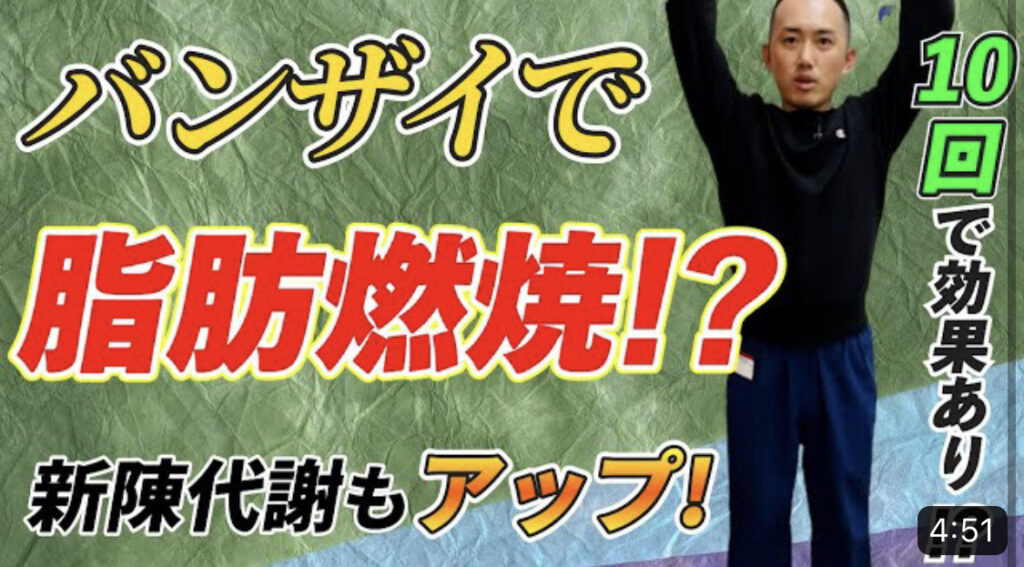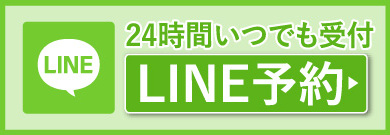東洋医学で診る春の特徴
こんにちは。江戸川区平井鍼灸院の今木です。
前回は、過敏性腸症候群が増えている原因とその症状についてお伝えしました。
今回は、春に向けての体調管理についてお伝えしていきます。

東洋医学では、春は自然界や人体のエネルギー(気)の動きが活発になる季節とされ、五行説の中で「木」に対応します。この「木」は成長や発展を象徴し、肝(かん)の働きと深く結びついています。以下、春の特徴を詳しく解説します。
春の特徴(東洋医学的視点)
1. 自然の特徴
- 春は「生発(せいはつ)」の季節であり、植物が芽吹き、生命活動が活発になる時期です。
- 寒さが和らぎ、陽気(エネルギー)が上昇するため、人体のエネルギーも外向きに動き始めます。
2. 対応する五行と臓腑
- 五行:木
- 木は成長や伸びる性質を持ち、春のエネルギーを象徴します。
- 柔軟性がありながらも、上に向かって伸びる力を秘めています。
- 臓腑:肝と胆(たん)
- 春は肝の働きが活発になる季節とされています。肝は「気血の流れを司る」臓器であり、情緒や目、筋(筋肉・腱)とも関連します。
- 胆は意思決定や判断力に関係し、肝の補佐をします。
3. 肝の働きと春の影響
気の流れを調整する(疏泄(そせつ)作用)
肝は気の流れをスムーズにする役割があり、春のエネルギーの上昇とともにその作用が重要になります。情緒や感情の安定
肝は怒りやイライラといった感情に関係します。春は感情の揺れが生じやすい時期でもあり、肝のバランスが崩れるとストレスや不安が高まることがあります。血の貯蔵と供給
肝は血を貯蔵し、必要に応じて全身に供給する役割があります。春は活動量が増えるため、血の循環を整えることが特に大切です。

4. 春に起こりやすい不調
情緒の乱れ
肝の気が滞ると、イライラや落ち込み、不安感が増す傾向があります。
→「春うつ」や「春のイライラ」として現れることも。筋肉や腱の硬さ
肝が筋を養うため、気の巡りが悪いと筋肉のこわばりや、こむら返りが起きやすくなります。目の疲れ
肝は目とも深く関連しているため、肝の働きが弱まると目の疲れ、かすみ目、乾燥感などが起こります。
5. 春におすすめの養生法
ストレスケア
肝の疏泄作用を整えるために、深呼吸や瞑想、軽い運動(散歩やヨガ)が効果的です。適度な活動
春は体を動かしてエネルギーを巡らせるのが大切です。適度に体を動かし、滞りを防ぎましょう。目を休める
肝を養うために、パソコンやスマートフォンの使用時間を減らし、目を休ませる工夫を。肝に良い食材を摂る
- 苦味や酸味のある食材(春菊、菜の花、レモン、梅干し)
- 緑の野菜(ほうれん草、小松菜、クレソン)
- 肝の働きをサポートする食材(クコの実、なつめ、山芋)
夜更かしを避ける
肝の働きが修復されるのは夜の時間帯(特に23時~3時)なので、早寝早起きを心がけると良いです。
まとめ
季節による体調の変化やその特徴を知る事で事前に対策が打てたり、予防ができたりします。旬の食材にはその季節に必要な栄養素が沢山含まれていますので、できるだけ旬のものを摂り入れていきましょう。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
江戸川区平井鍼灸院 今木 薫
 【監修】
【監修】
平井鍼灸院 院長 梅田俊
鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師
鍼灸師
【所属】
2015年~ 日本自律神経研究会
日本自律神経研究会
【資格】
2011年 国家資格はり灸師、あん摩マッサージ指圧師免許取得
2016年 自律心体療法上級者施術認定者取得
2018年 クレニアルテクニック上級施術認定者取得
info_outline平井鍼灸院
- 住所
- 〒132-0035
東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号
 03-3683-7670
03-3683-7670
- 営業時間
- 火金 10:00~20:00
水 12:00~20:00
土 9:00~17:00
日 9:00~16:00 - 休業日
- 月曜・木曜・祝日
- アクセス
- JR総武本線平井駅から徒歩1分