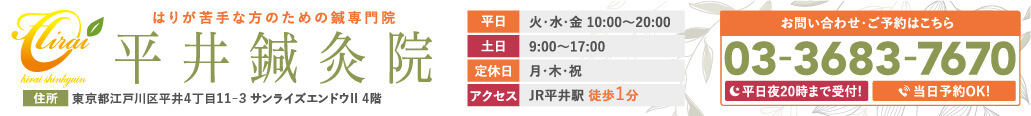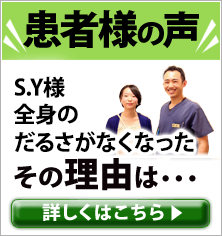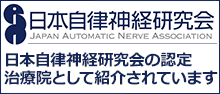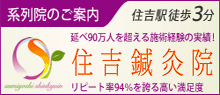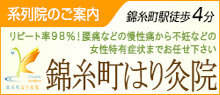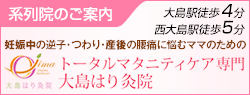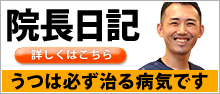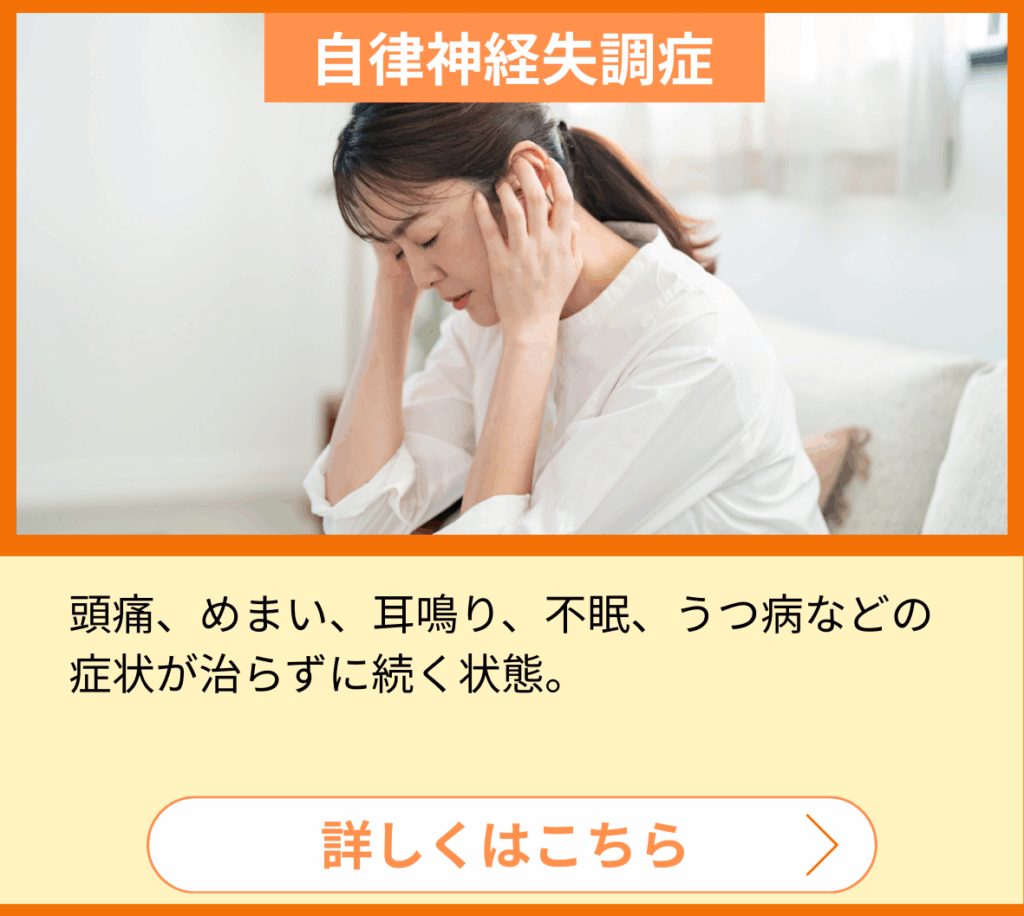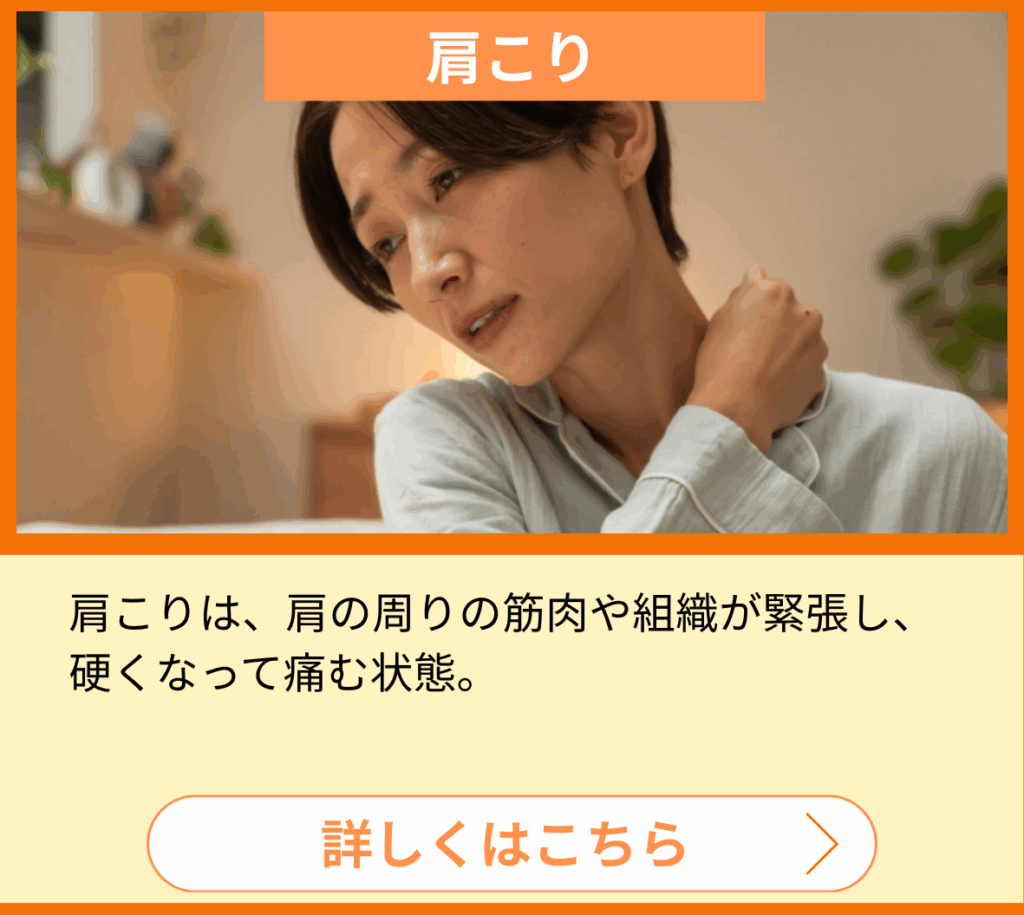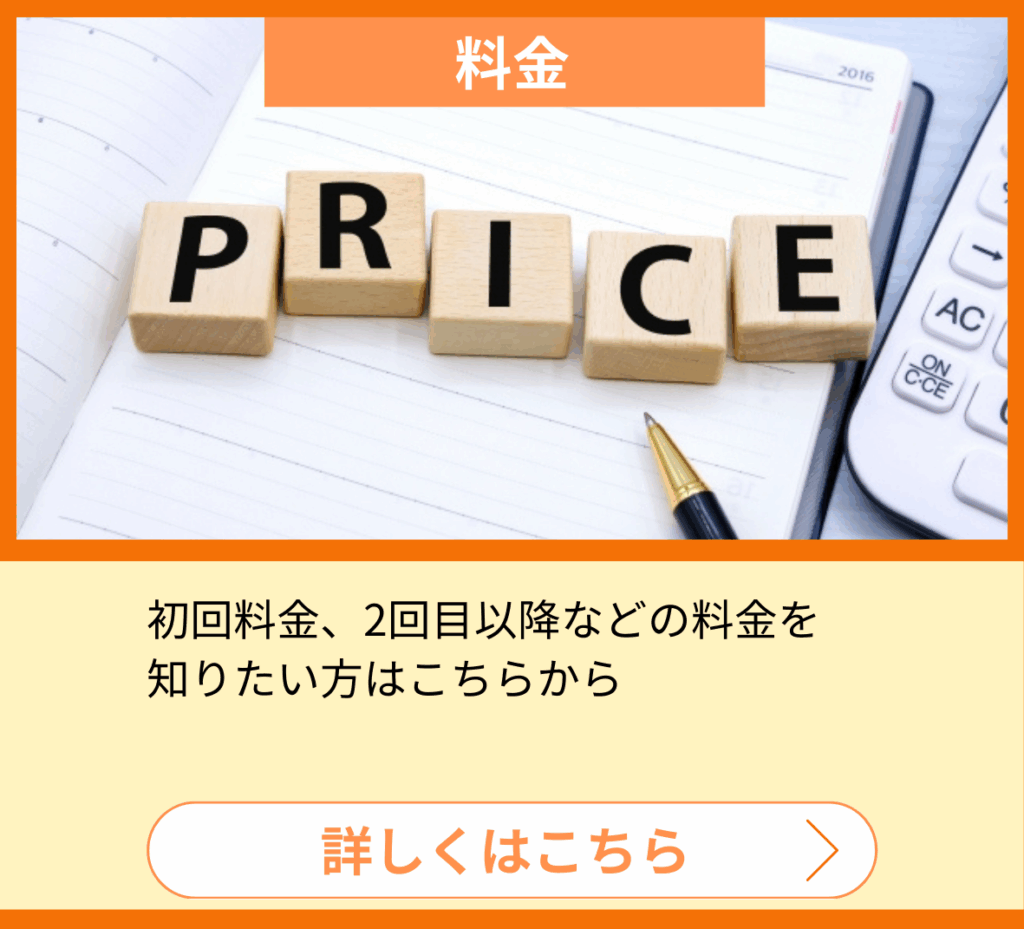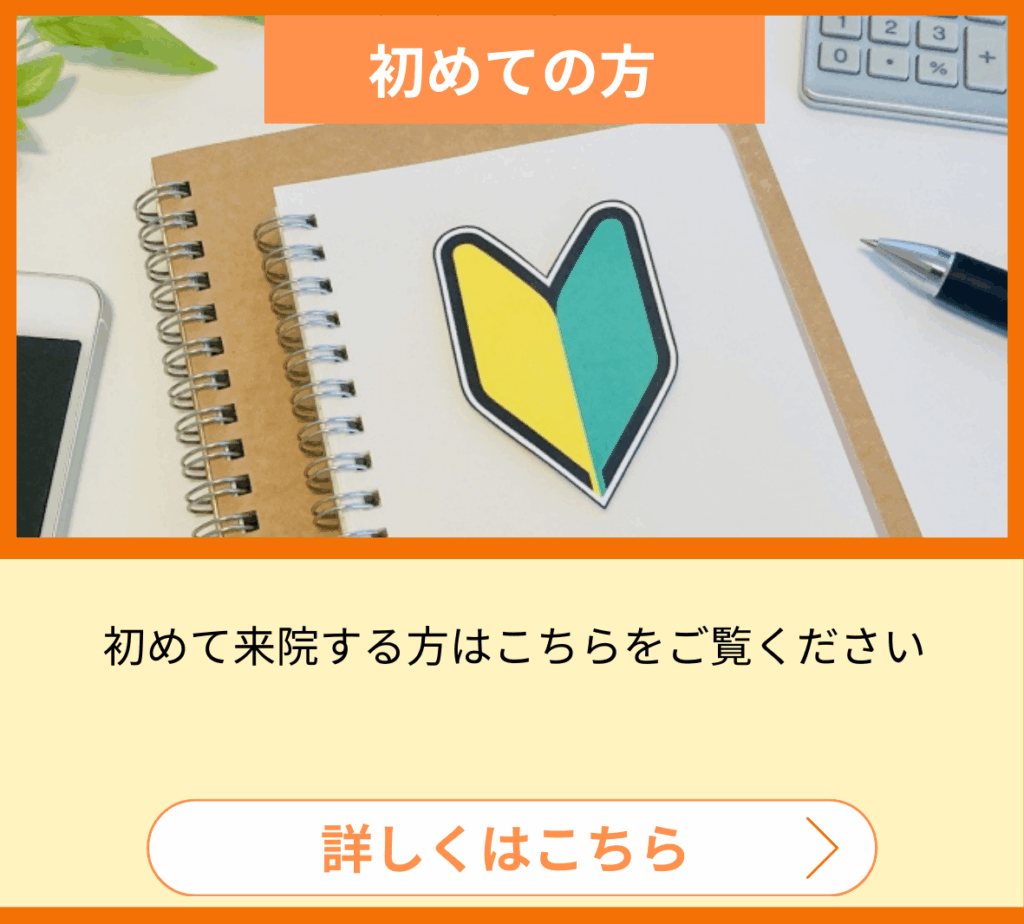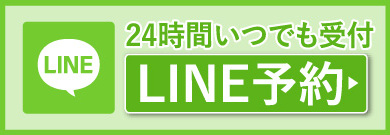肩甲骨周囲痛|自律神経の乱れが影響する痛みと鍼灸の視点
こんにちは。鈴木開登です。
「夕方になると肩甲骨の内側が重だるい」「背中の片側がずっと突っ張って痛い」――こうした訴えで来院される方が多く、デスクワークやスマホ姿勢、ストレスによる筋緊張が背景にあることが少なくありません。肩甲骨周囲痛は単に筋肉の問題だけでなく、頚椎や胸椎の機能不全、神経根の関連痛、自律神経の不調、さらには東洋医学的な臓腑のバランス不良が絡み合って生じることが多いのが特徴です。本記事では症状の現れ方、主要な原因と病態生理、自律神経との関係、東洋医学的な見立てまで丁寧に解説します。

肩甲骨周囲痛とは?
肩甲骨周囲痛とは、肩甲骨(肩のうしろにある大きな骨)周辺に感じる痛み・重だるさ・張り・しびれ感などの総称です。痛みは肩甲骨内側(脊柱寄り)や上縁、肩甲骨下角、肩甲間部(肩甲骨と脊柱の間)に出やすく、片側性・両側性どちらもあり得ます。放散痛として腕や首、頭部に関連症状が出ることもあります。発症の背景は多岐にわたり、慢性化すると日常生活や睡眠に影響することが多いです。
症状
鈍い重だるさや張り感(特に長時間の座位後や夕方に増強)
局所の刺すような痛みや、ズーンとくる深部痛
肩甲骨の内側にピンポイントの圧痛点(トリガーポイント)を触れると痛む
首・肩の可動域制限(腕を上げにくい、後ろに手を回しにくい)
肩甲間部から前胸部、腕への放散痛やしびれ(場合によっては頚椎由来)
ストレスや疲労で悪化、睡眠の妨げになることもある
症状の詳細(発症時間帯、姿勢での増悪・軽減、放散パターンなど)を把握することで、発症機序の推測に役立ちます。
西洋医学的視点
肩甲骨周囲痛は単一の病態ではなく、複数要因が重なって発生します。主な要素を整理します。
筋・筋膜性
長時間の不良姿勢(前傾姿勢、巻き肩)や反復動作により、僧帽筋・肩甲挙筋・菱形筋・棘上筋などが過緊張・疲労し、トリガーポイント(圧痛点)を形成。筋膜の滑走不良や局所血流低下が持続痛を招きます。
頚椎由来(神経根/椎間関節)
頚椎の退行変性や椎間孔の狭小化・椎間板変性に伴う神経根刺激は、肩甲間部や肩甲骨近傍に放散痛を引き起こすことがあります。しびれや筋力低下が合併する場合は神経学的要素が強いと考えられます。
肩関節・胸郭機能不全
肩甲骨の運動制御(スキャプラの協調)が障害されると、特定の筋に過負荷がかかり慢性疼痛につながります。胸郭の可動性低下も関連します。
外傷・運動誘発
スポーツや転倒、急激な筋収縮による筋線維や腱付着部の損傷が契機となることがあります。
内臓関連(鑑別)
まれに心・肺・肝など内臓由来の関連痛として背部痛が出ることがあり、全身症状が伴う場合は医療機関での評価が必要です。
痛みの持続化メカニズム
持続的筋緊張は局所の血流障害を生み、老廃物や発痛物質が蓄積します。さらに交感神経の亢進が血流を悪化させることで「痛みの悪循環」が形成され、慢性化・感受性の上昇(中枢性感作)へとつながります。
自律神経との関係
肩甲骨周囲痛と自律神経の相互作用は臨床上重要です。以下の点が症状の発現・慢性化に影響します。
交感神経の過活動:慢性的なストレスや過労により交感神経が優位になると、筋緊張が増し局所血流が低下。深部筋の硬化や疼痛が持続する。
副交感神経(回復機能)の低下:副交感機能が不十分だと夜間の回復が妨げられ、筋・筋膜の修復が遅延して慢性疼痛が助長される。
感覚過敏化(中枢性感作):自律神経不安定は脊髄・脳の痛覚処理にも影響し、わずかな刺激で強い不快を感じるようになる。
呼吸・胸郭運動の影響:浅い胸式呼吸は首肩筋を過剰に使わせ、肩甲骨周囲筋の負担を増大させる。呼吸パターンと自律神経は相互に影響する。
姿勢と自律神経の相互作用:慢性的な前傾姿勢は胸郭の動きを悪くし自律神経の乱れを招きやすい。これが筋緊張と痛みを増幅する一因となる。
これらのことから、肩甲骨周囲痛の理解には自律神経の状態を併せて評価することが重要です。自律神経の不安定は痛みの閾値や回復力に直結します。
東洋医学的観点
東洋医学では肩甲骨周囲痛を筋・絡・気血の滞りや臓腑の不調として捉え、弁証に基づいて全身と局所のバランスを判断します。代表的な弁証パターンは次の通りです。
瘀血(おけつ)タイプ
臨床像:刺すような鋭い痛み、圧痛が明瞭、慢性化しやすい。
着眼:活血化瘀(血の停滞を除く)を重視。寒湿(かんしつ)タイプ
臨床像:寒さや湿気で悪化、痛みが重だるい。
着眼:温補除湿で陽気を補う施術を念頭に。肝鬱・気滞タイプ
臨床像:ストレスや情緒的緊張と関連、張りや不快感が強い。
着眼:疏肝理気で気の巡りを改善する。気血両虚タイプ
臨床像:慢性的で体力低下を伴い、だるさや回復力の乏しさが目立つ。
着眼:補気養血で体の基礎力を上げる。
まとめ
肩甲骨周囲痛は単なる「筋肉のこり」ではなく、筋・筋膜の異常、頚椎由来の神経学的要素、胸郭・肩甲骨の機能不全、さらに自律神経のアンバランスや東洋医学的な臓腑の不調が複合して生じる多因子性の症状です。症状把握(発症パターン・誘因・放散様式)を丁寧に行うことで病態の本質に近づけます。西洋医学的な病態理解と東洋医学(鍼灸)的な弁証を組み合わせることで、症状の背景を多角的に評価できます。気になる症状がある場合は専門家に相談し、適切な対応をご検討ください。
関連記事はこちら
info_outline平井鍼灸院
- 住所
- 〒132-0035
東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号
 03-3683-7670
03-3683-7670
- 営業時間
- 火金 10:00~20:00
水 12:00~20:00
土 9:00~17:00
日 9:00~16:00 - 休業日
- 月曜・木曜・祝日
- アクセス
- JR総武本線平井駅から徒歩1分