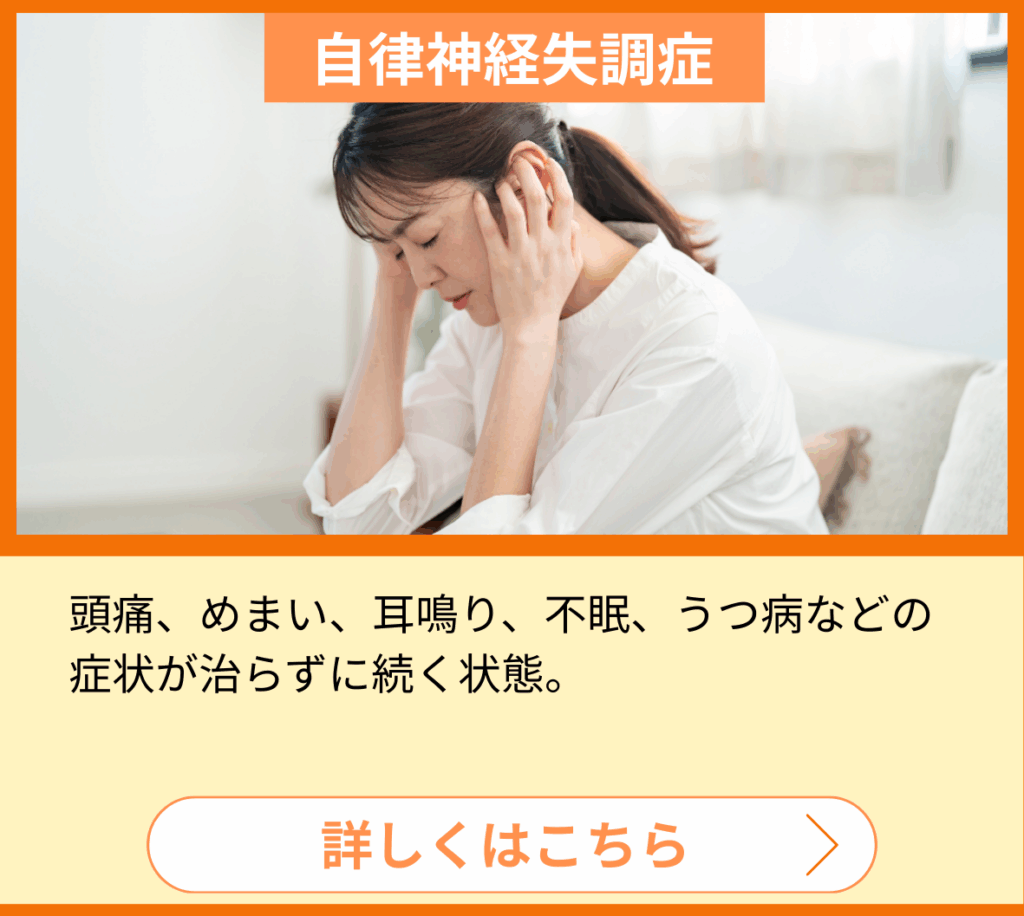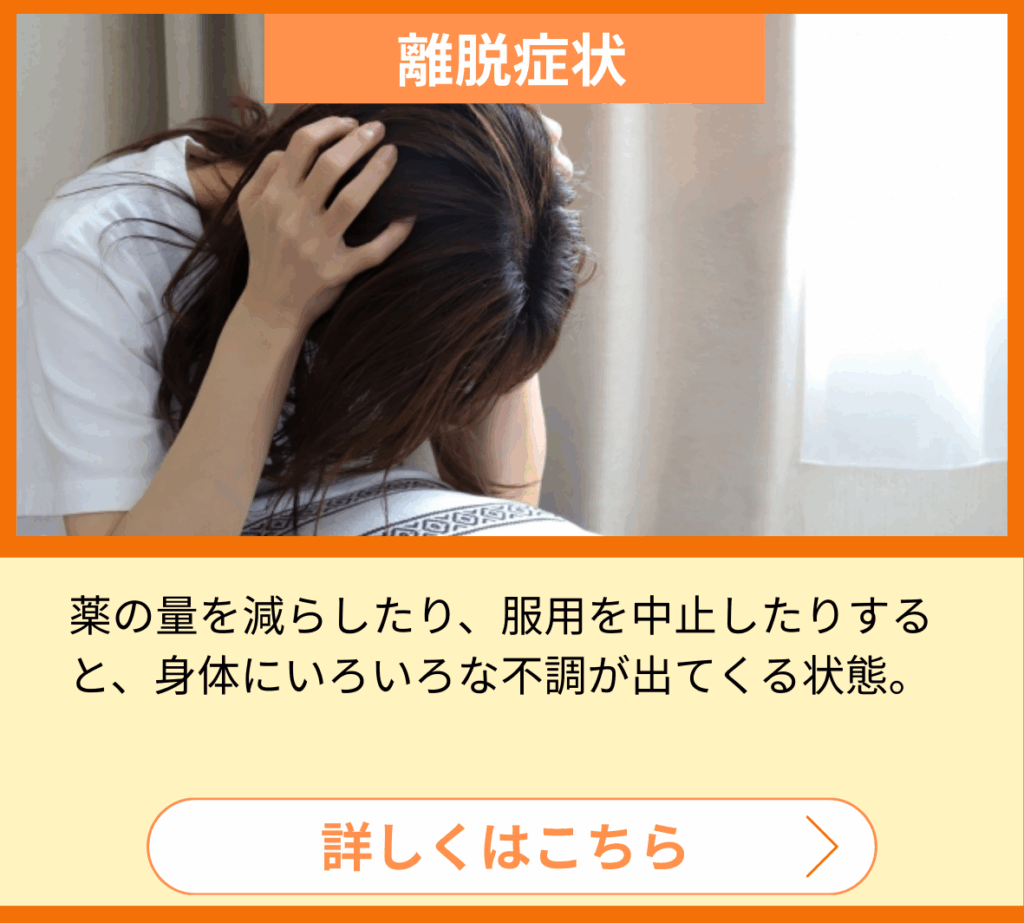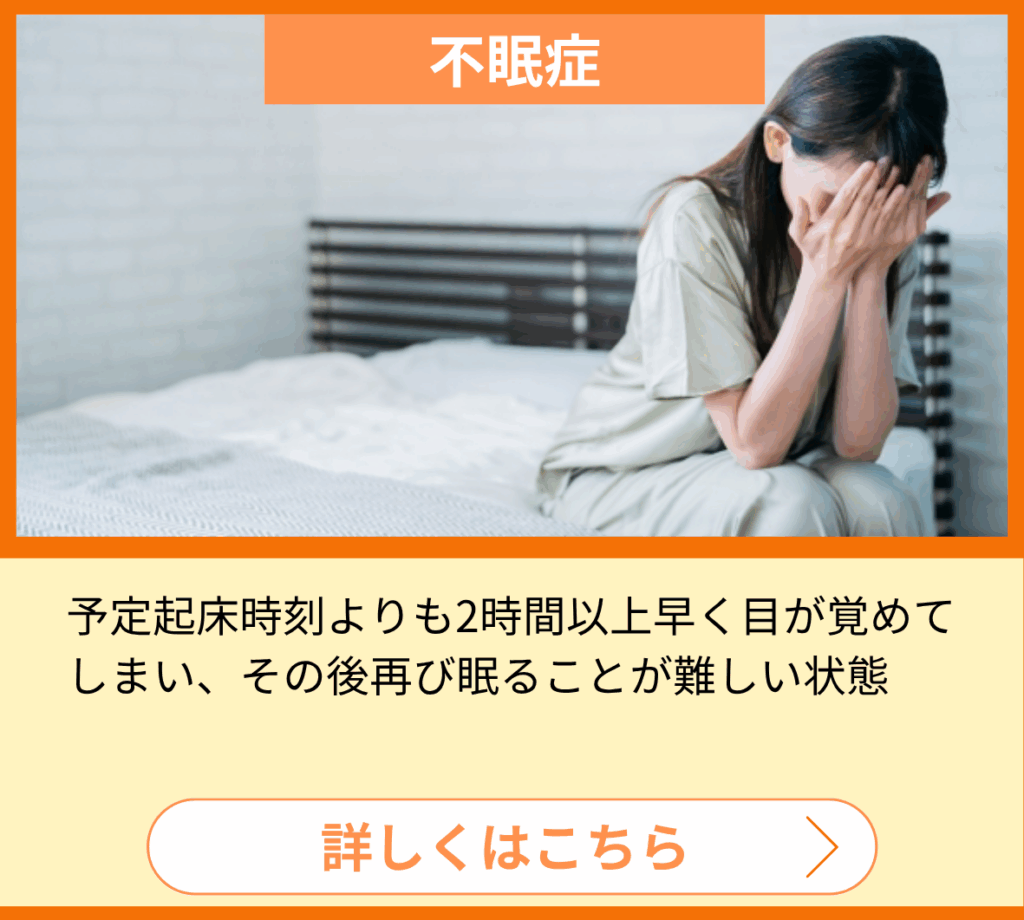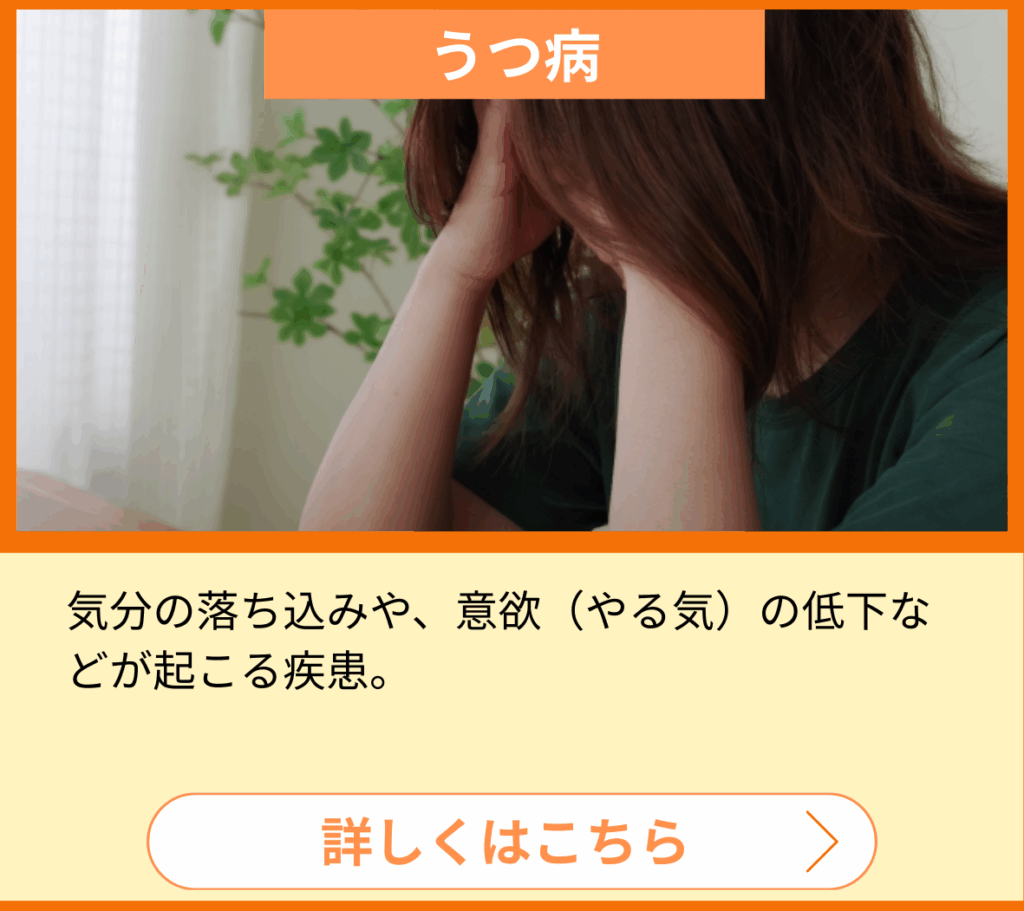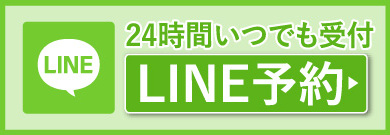肋間神経痛でずっと痛い肋骨。原因と治らない時の対処法

肋骨のあたりがチクチク、ズキズキと痛み、それが毎日続くと「何か悪い病気なのでは」と不安になるかもしれません。
その症状は、肋間神経痛の可能性があります。
肋間神経痛は、肋骨に沿って走る神経が何らかの原因で刺激されることで起こる痛みです。
この記事では、肋間神経痛の痛みがずっと続く原因や、症状を和らげるための対処法、そして病院を受診する目安について詳しく解説します。
長引く痛みの原因を理解し、適切に対処していきましょう。
まず確認したい肋間神経痛の主な症状
肋間神経痛の痛みは、その現れ方にいくつかの特徴があります。
例えば、体の右側だけ、あるいは左側だけといった片側に症状が出ることが多く、脇腹や背中など、肋骨に沿ったラインで痛みを感じるのが一般的です。
痛みの感覚も「電気が走るよう」と表現されることもあれば、「ズキズキする」「焼けるよう」と感じる場合もあります。
これから挙げる具体的な症状が、自身の状態と当てはまるか確認してみてください。
突然、脇腹や背中に電気が走るような痛みが起こる
肋間神経痛の代表的な症状は、前触れなく突然発生する、肋骨に沿った鋭い痛みです。
その痛みは「電気が走る」「突き刺さるよう」などと表現され、瞬間的に激しい痛みが現れることもあれば、ジクジクとした痛みが持続することもあります。
痛みの範囲は、背中から胸、脇腹、みぞおちにかけて広がることが多いですが、基本的には体の片側に限定して起こります。
深呼吸や咳、くしゃみといった些細な動きで痛みが誘発されたり、悪化したりするのも特徴の一つです。
症状の出方は人それぞれですが、日常生活に支障をきたすほどの強い痛みを感じるケースも少なくありません。
深呼吸や咳、くしゃみをすると痛みが悪化する
肋間神経痛では、胸郭の動きに伴って痛みが強くなるという特徴があります。
深呼吸や咳、くしゃみをすると、肋骨の間にある肋間筋が伸縮し、それに伴って肋間神経が刺激されるため、痛みが悪化します。
同様に、大声で話したり笑ったりする、寝返りをうつといった日常的な動作でも、胸郭が動くことで鋭い痛みが走ることがあります。
痛みのために無意識に呼吸が浅くなったり、咳をするのをためらってしまったりするかもしれません。
特に夜、寝ている間の寝返りなどで痛みが生じ、睡眠が妨げられることもあり、生活の質を大きく低下させる要因となります。
体をひねったり、腕を伸ばしたりすると痛みが響く
肋間神経は背骨から出て肋骨に沿って体の前面まで伸びているため、上半身の動きに大きく影響されます。
そのため、体をひねる、腕を伸ばす、前かがみになる、物を持ち上げるといった動作で神経が引き伸ばされたり圧迫されたりして、痛みが響くように感じられます。
靴下を履く、後ろを振り向くといった何気ない日常の動作でさえ、激痛が走ることもあります。
このような痛みを避けるために、無意識に体をかばうような姿勢を取り続けると、他の部位の筋肉まで緊張してしまい、肩こりや背中の張りを引き起こすなど、別の不調につながる可能性も考えられます。
肋間神経痛の痛みがずっと続くのはなぜ?考えられる原因
肋間神経痛の痛みが長引く背景には、さまざまな原因が考えられます。
原因がはっきりと特定できない「原発性肋間神経痛」と、何らかの病気や外傷が引き金となって起こる「続発性肋間神経痛」に大別されます。
続発性の場合は、その原因を突き止めて対処しない限り、痛みが改善しにくい傾向にあります。
自身の生活習慣や過去の病歴などを振り返り、痛みの原因を探る手がかりにしてみましょう。
ストレスや疲労の蓄積による筋肉の緊張
精神的なストレスや身体的な疲労が蓄積すると、自律神経のバランスが乱れ、全身の筋肉がこわばりやすくなります。
特に、背中や肩、胸周りの筋肉が持続的に緊張した状態になると、その間を走行している肋間神経が圧迫され、痛みやしびれを引き起こすことがあります。
デスクワークで長時間同じ姿勢を続けたり、育児や介護で体に負担がかかったりすることも、筋肉の緊張を高める一因です。
はっきりとした病気やケガがないのに肋間神経痛が続く場合、こうした心身のストレスが根本的な原因となっている可能性があります。
十分な休息やリラックスできる時間を確保し、心と体の緊張をほぐすことが求められます。
猫背などの悪い姿勢が神経を圧迫している
日頃の姿勢の癖も、肋間神経痛が長引く原因の一つです。
猫背や前かがみの姿勢を長時間続けていると、背骨、特に胸の部分にある胸椎に歪みが生じやすくなります。
背骨が歪むと、そこから出ている肋間神経の通り道が狭くなったり、神経が根本で圧迫されたりして痛みが生じます。
また、悪い姿勢は肋骨周りの筋肉のバランスを崩し、特定の筋肉に過度な負担をかけるため、筋肉の緊張からも神経が圧迫されやすくなります。
スマートフォンを長時間見下ろす姿勢や、足を組んで椅子に座る癖なども、体の歪みを助長し、結果として肋間神経痛のリスクを高めることにつながります。
帯状疱疹や過去のケガが影響している可能性
過去にかかった帯状疱疹が、長引く肋間神経痛の原因となっている場合があります。
帯状疱疹は、水ぼうそうのウイルスが神経に沿って再活性化する病気で、肋間神経は好発部位の一つです。
皮膚の発疹が治った後も、ウイルスによって傷つけられた神経が原因で「帯状疱疹後神経痛」として、数ヶ月から数年にわたり痛みが残ることがあります。
また、過去の交通事故や転倒による肋骨骨折、胸部の手術などが原因で、神経が損傷したり、周囲の組織と癒着したりして、後から痛みが出てくるケースも考えられます。
これらのように、はっきりとした原因がある場合は、それに応じた専門的な治療が必要です。
痛みを悪化させないために避けたい3つの行動
肋間神経痛のつらい痛みがあるときは、回復を妨げ、かえって症状を悪化させてしまう行動を避けることが重要です。
良かれと思って行ったセルフケアが逆効果になることも少なくありません。
ここでは、痛みが強いときに特に注意したい3つの行動について解説します。
これらのポイントを意識して、神経への余計な刺激を避け、安静を保つように心がけましょう。
重い荷物を無理な体勢で持ち上げる
重い荷物を持ち上げる動作は、肋骨周りの筋肉や関節に大きな負担をかけます。
特に、中腰や体をひねった不自然な体勢で持ち上げようとすると、肋間筋に急激な力が加わり、筋肉を傷めたり、肋間神経を強く圧迫したりする原因となります。
痛みがあるときは、できるだけ重いものを持つことは避けましょう。
どうしても荷物を運ぶ必要がある場合は、荷物を体にしっかりと引き寄せ、背筋を伸ばしたまま膝を曲げて腰を落として持ち上げるなど、体への負担が少ないフォームを意識することが大切です。
急な動きは避け、ゆっくりとした動作を心がけてください。
自己判断による過度なストレッチやマッサージ
痛みがあると、凝り固まった筋肉をほぐそうとストレッチやマッサージをしたくなるかもしれません。
しかし、原因がはっきりしない状態での自己判断によるケアは危険を伴います。
特に、痛み出したばかりの急性期で炎症が起きている場合、患部を強く揉んだり、無理に伸ばしたりすると、炎症が悪化して痛みがさらに強くなる可能性があります。
筋肉の緊張が原因の慢性的な痛みであっても、痛みのポイントを強く押しすぎるマッサージは、神経を過剰に刺激してしまう恐れがあります。
セルフケアを行う際は、あくまで「気持ち良い」と感じる範囲にとどめ、痛みを感じるような強い刺激は避けるべきです。
痛みを我慢して激しい運動を続ける
痛みは、体からの「これ以上負担をかけないで」というサインです。
そのサインを無視して運動を続けると、原因となっている部位の炎症を悪化させたり、神経の損傷を深刻化させたりする恐れがあります。
特に、ゴルフやテニス、野球の素振りなど、体幹をひねる動作を伴うスポーツは、肋間神経に直接的な刺激を与えるため、症状を悪化させるリスクが非常に高いです。
痛みを感じる場合は、まず運動を中止し、安静にすることが回復への第一歩です。
運動を再開する際は、医師に相談の上、ウォーキングなどの軽いものから始め、体の状態を確認しながら徐々に負荷を上げていくようにしましょう。
つらい痛みを和らげるために自宅でできる対処法
急な痛みや、なかなか病院に行けない状況で、少しでも症状を和らげたいときに試せるセルフケアがあります。
ただし、これらの方法はあくまで一時的な応急処置であり、根本的な解決にはなりません。
痛みが長期間続く場合や、我慢できないほどの激しい痛みがある場合は、必ず医療機関を受診してください。
ここでは、自宅でできる基本的な対処法を3つ紹介します。
安静を心がけ、楽な姿勢で過ごす
肋間神経痛の症状があるときは、無理に動かず安静にすることが最も重要です。
痛みを誘発するような動作を避け、神経への刺激を最小限に抑えることで、炎症の悪化を防ぎ、回復を促します。
横になる場合は、痛む側を上にして、抱き枕やクッションで体を支えると楽な姿勢を保ちやすくなります。
椅子に座る際は、背もたれに深く寄りかかり、背中が丸まらないように注意しましょう。
コルセットやさらしを巻いて肋骨の動きを適度に固定することも、動作時の痛みを軽減するのに役立つ場合があります。
自分が最もリラックスできる姿勢を見つけ、心身ともに休ませることを優先してください。
ぬるめのお風呂で体を温めて血行を促進する
筋肉の緊張や血行不良が原因で慢性的な痛みが続いている場合、体を温めることで症状が和らぐことがあります。
38〜40度程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かると、全身の血行が促進され、こわばった筋肉がほぐれて痛みの緩和が期待できます。
リラックス効果により、ストレス軽減にもつながります。
ただし、ズキズキと脈打つような強い痛みがある急性期や、患部に熱感がある場合は、温めることで炎症が悪化する可能性があるため避けるべきです。
温めるべきか冷やすべきか迷う場合は、自己判断せず、温めてみて痛みが強まるようなら中止してください。
患部を冷やして炎症を抑える(ズキズキ痛む場合)
打撲などのケガが原因であったり、急に痛み出してズキズキと脈打つような熱感を伴ったりする場合は、患部を冷やすアイシングが有効です。
冷やすことで血管が収縮し、炎症物質の広がりを抑え、痛みや腫れを和らげる効果が期待できます。
タオルで包んだ保冷剤や氷のうなどを、痛む部分に1回15〜20分程度を目安に当てます。
冷やしすぎると凍傷になる恐れがあるため、直接肌に当てたり、長時間連続して冷やし続けたりするのは避けてください。
感覚がなくなったら一度外し、時間を置いてから再び冷やすといった方法を繰り返します。
慢性的な痛みに対しては、冷やすと筋肉が硬くなることがあるため不向きです。
肋間神経痛の痛みはいつまで続く?治療期間の目安
肋間神経痛の痛みがどのくらい続くのかは、その原因や重症度、個人の回復力によって大きく異なるため、一概には言えません。
例えば、姿勢の悪さや一時的な筋肉の疲労が原因の軽度なものであれば、安静にしたり、生活習慣を改善したりすることで、数日から2週間程度で自然に軽快することが多いです。
一方で、胸椎椎間板ヘルニアや変形性脊椎症など、背骨に原因がある場合や、帯状疱疹後神経痛のように神経自体にダメージが残ってしまった場合は、治療が長引き、数ヶ月以上にわたって痛みが続くこともあります。
痛みが1週間以上改善しない、あるいは悪化する傾向にある場合は、原因を特定するためにも早めに医療機関を受診することが重要です。
なかなか治らない痛みは別の病気が隠れている可能性も
肋間神経痛だろうと自己判断していた痛みが、実は別の病気のサインである可能性も考えられます。
特に、痛みが長期間続く、痛みの性質が変わってきた、あるいは胸の痛み以外に息苦しさや吐き気といった別の症状が現れた場合には注意が必要です。
肋間神経痛と似た症状を示す病気の中には、緊急性の高いものも含まれるため、安易な自己判断は禁物です。
肋骨の骨折や内臓疾患が痛みの原因になっているケース
長引く胸の痛みは、肋間神経痛以外の病気が原因となっている可能性があります。
例えば、強い咳やくしゃみ、あるいは気づかないうちに、肋骨にひびが入っていたり、疲労骨折を起こしていたりする場合も、深呼吸や体を動かしたときに鋭い痛みが生じます。
さらに注意が必要なのは、心臓や肺、消化器などの内臓疾患です。
狭心症や心筋梗塞、気胸、胸膜炎、胆石症、膵炎といった病気が、関連痛として胸や背中に痛みを引き起こすことがあります。
特に、胸を締め付けられるような痛み、冷や汗、息切れ、吐き気などの症状を伴う場合は、命に関わる可能性もあるため、ためらわずに救急外来を受診するか、救急車を呼ぶ必要があります。
皮膚に発疹があれば帯状疱疹を疑う
肋間神経痛の原因として頻度の高いものに帯状疱疹があります。
帯状疱疹は、過去に感染した水ぼうそうのウイルスが、免疫力の低下などをきっかけに神経節で再活性化して起こる病気です。
初期症状として、体の片側の神経に沿ってピリピリ、チクチクとした皮膚の痛みが現れ、その数日後に同じ場所に赤い発疹や水ぶくれが帯状に広がります。
発疹が出るまでは肋間神経痛と区別がつきにくいですが、皮膚表面の違和感や痛みが先行する場合は帯状疱疹の可能性を考慮します。
帯状疱疹は、発症後72時間以内に抗ウイルス薬の投与を開始することが、症状の重症化や帯状疱疹後神経痛という後遺症を防ぐ上で非常に重要です。
そのため、疑わしい症状があれば、すぐに皮膚科を受診してください。
セルフケアで改善しない場合は病院へ!何科を受診すべき?
自宅でのセルフケアを試みても痛みが改善しない場合や、むしろ悪化していると感じる場合は、専門的な診断と治療が必要です。
痛みが1週間以上続いたり、日常生活に支障をきたすほどの強い痛みがあったりするなら、我慢せずに医療機関を受診しましょう。
しかし、いざ病院へ行こうと思っても「何科にかかれば良いのか」と迷うかもしれません。
ここでは、肋間神経痛が疑われる場合に受診すべき診療科について解説します。
まずは整形外科で骨や神経の状態を調べてもらう
肋骨や胸の痛みが続く場合、痛みの原因に応じて適切な診療科を選ぶことが重要です。打撲など物理的な原因が明らかな場合は整形外科が適していますが、胸の痛みは心臓、肺、消化器、神経など多岐にわたる原因が考えられます。
整形外科では、問診や身体診察に加え、レントゲンやMRIといった画像検査を行い、痛みの原因が骨、関節、筋肉、あるいは神経にあるのかを診断します。肋骨の骨折やひび、背骨(胸椎)の変形、椎間板ヘルニアといった器質的な問題がないかを確認することが、適切な治療への第一歩です。これらの検査で明らかな異常が見つかれば、それに対する治療(薬物療法、リハビリテーション、装具療法など)が開始されます。骨格や神経の問題が疑われる場合は、整形外科の受診が一般的な流れです。
しかし、以下のような症状がある場合は、他の診療科の受診も検討する必要があります。
①発熱や息苦しさ、息を吸った時の痛みがある場合:
肺炎や気胸などの可能性があり、呼吸器内科の受診が推奨されます。咳が続くことによる肋骨の痛みの場合も、呼吸器内科と整形外科の両方の受診が勧められます。
②胸の締め付けられるような痛みや圧迫感、動悸、冷や汗、吐き気、めまいなどがある場合:
心筋梗塞や狭心症といった循環器系の疾患の可能性があり、循環器内科を早期に受診することが重要です。強い痛みが続く場合は、救急科の受診も検討すべきです。
③胸焼けや酸っぱいものが上がってくる感じが伴う場合:
逆流性食道炎など消化器系の問題も考えられ、消化器内科が適していることがあります。
④痛み以外の症状がなく、どの診療科を選べばよいか迷う場合:
原因が多岐にわたる可能性を考慮し、一般内科を受診するのが良いでしょう。
まずはご自身の症状をよく観察し、適切な診療科を選択するようにしましょう。
原因が特定できない場合はペインクリニックも選択肢に
整形外科で検査をしても明らかな異常が見つからない、あるいは処方された薬を飲んでも痛みがなかなか改善しないという場合には、ペインクリニックの受診も選択肢となります。
ペインクリニックは、その名の通り「痛み」の治療を専門とする診療科です。
薬物療法に加えて、神経ブロック注射といったより専門的な治療法を用いて、痛みの緩和を目指します。
神経ブロック注射は、痛みの原因となっている神経の近くに局所麻酔薬などを注入し、痛みの伝達を遮断する治療法です。
これにより、つらい痛みを直接的に和らげ、痛みの悪循環を断ち切る効果が期待できます。
長引く難治性の痛みで悩んでいる場合に有効な選択肢です。
まとめ
肋間神経痛による肋骨周りの痛みが続く場合、その原因はストレスや悪い姿勢による筋肉の緊張から、帯状疱疹や内臓疾患といった病気まで多岐にわたります。
痛みが軽い場合は、安静を保ち、症状に応じて温めたり冷やしたりするセルフケアで様子を見ることもできます。
しかし、痛みが1週間以上続く、だんだん強くなる、あるいは息苦しさや発疹など他の症状を伴う際には、自己判断せずに医療機関を受診することが不可欠です。
まずは整形外科で骨や神経に異常がないか調べてもらい、原因に応じた適切な治療を受けることが、つらい痛みから解放されるための最も確実な方法です。
症例・患者さんの声

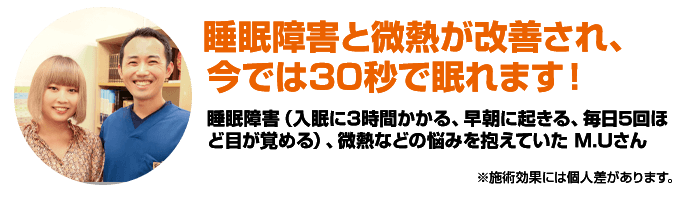
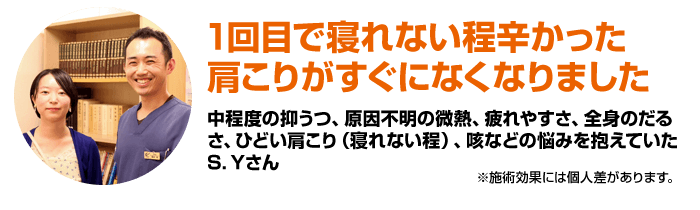
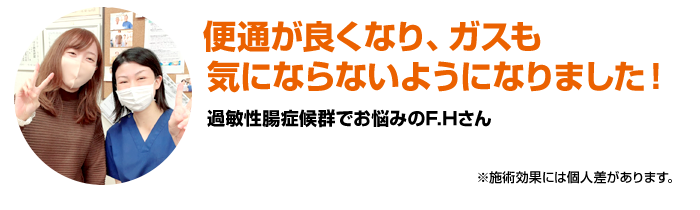
info_outline平井鍼灸院
- 住所
- 〒132-0035
東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号
 03-3683-7670
03-3683-7670
- 営業時間
- 火金 10:00~20:00
水 12:00~20:00
土 9:00~17:00
日 9:00~16:00 - 休業日
- 月曜・木曜・祝日
- アクセス
- JR総武本線平井駅から徒歩1分

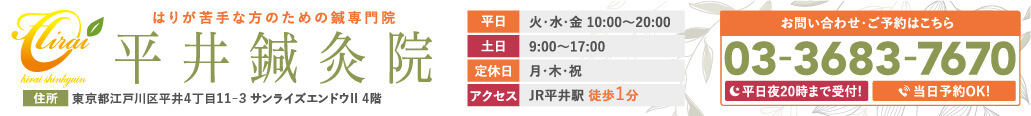

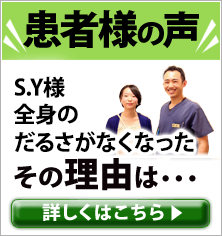
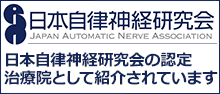
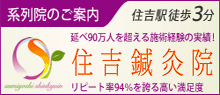

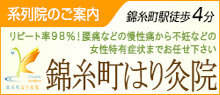
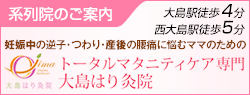
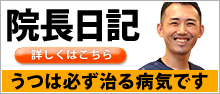
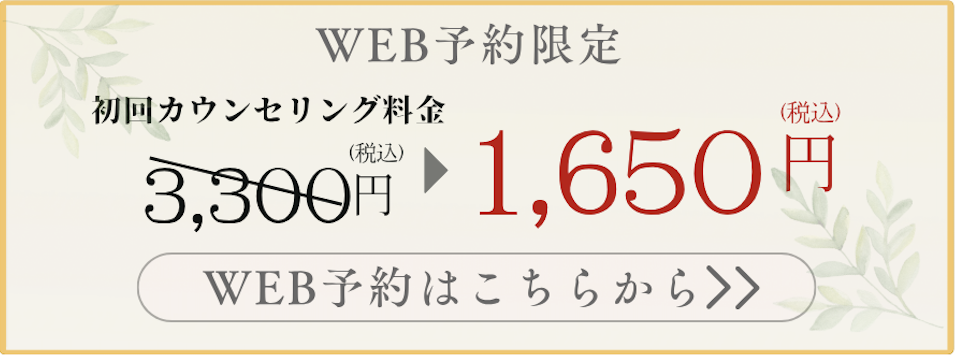
 【監修】
【監修】