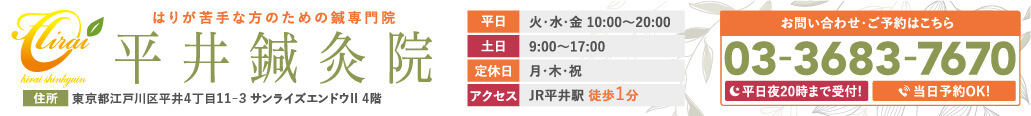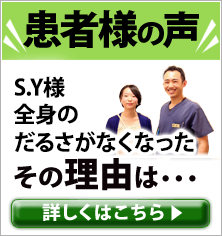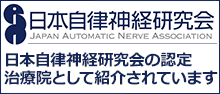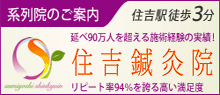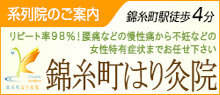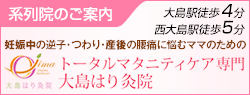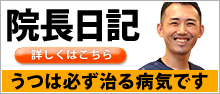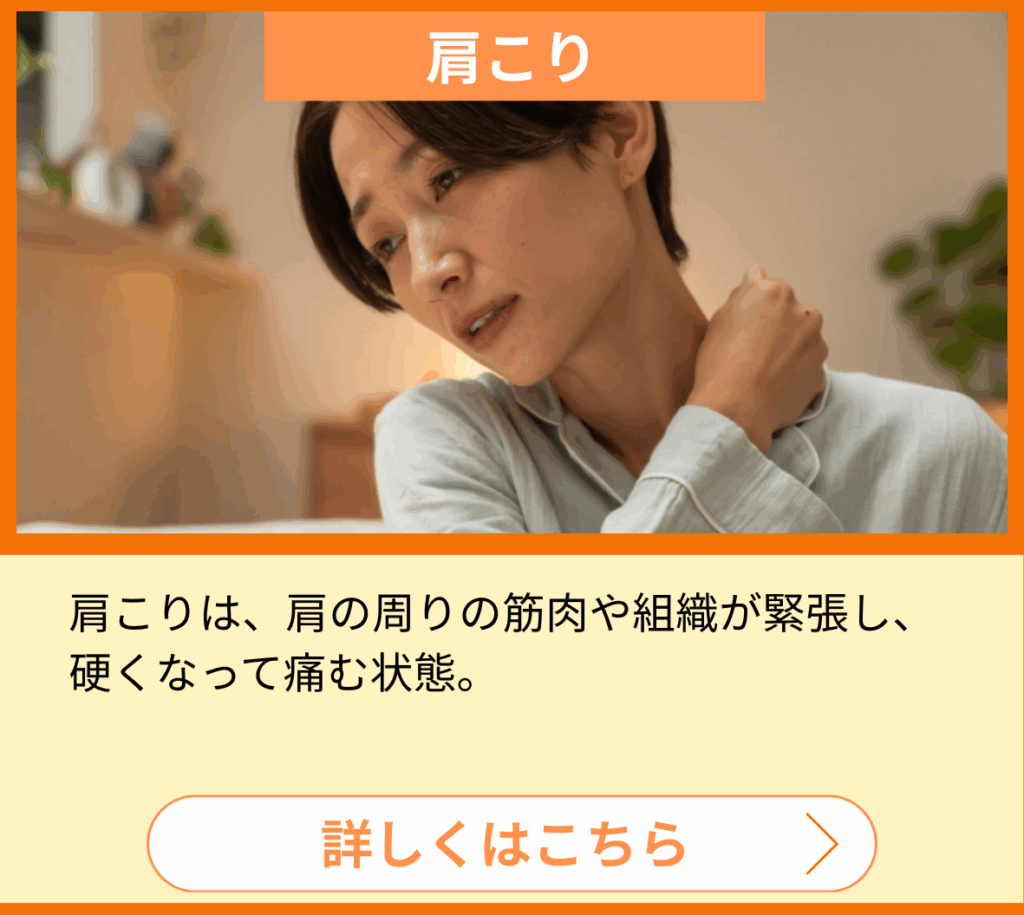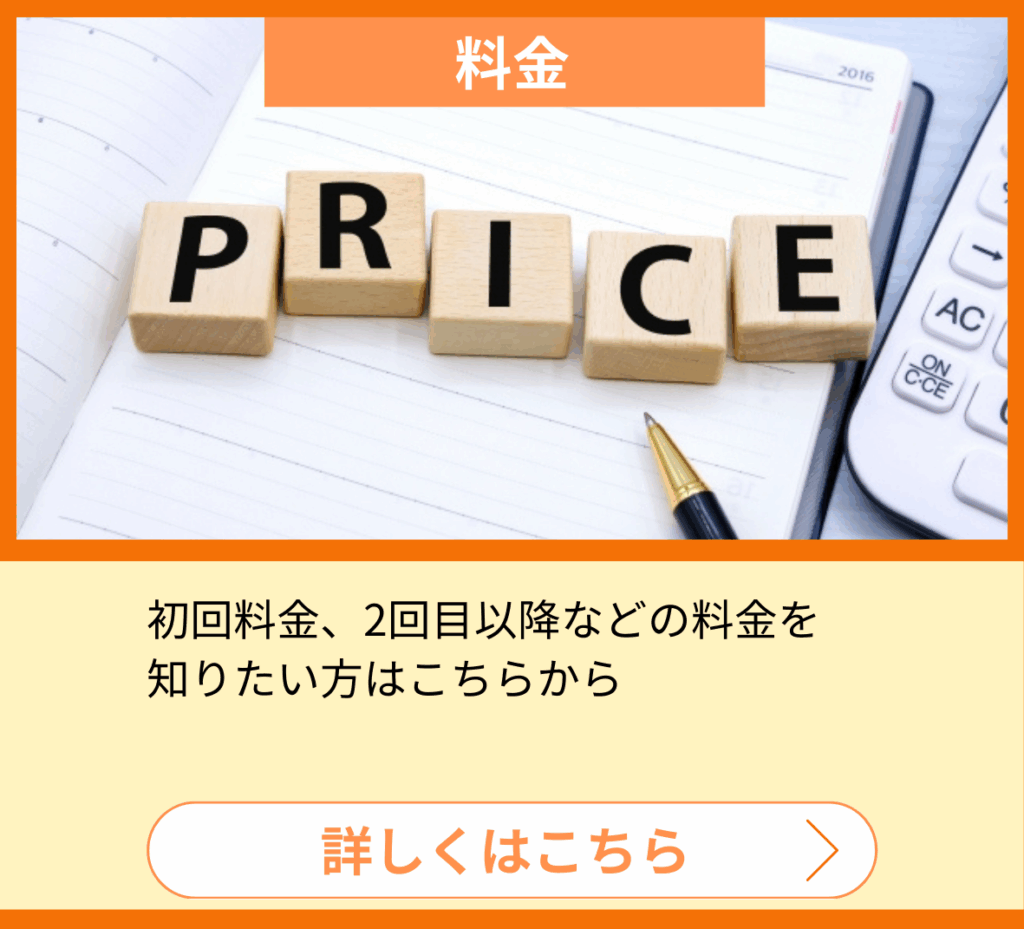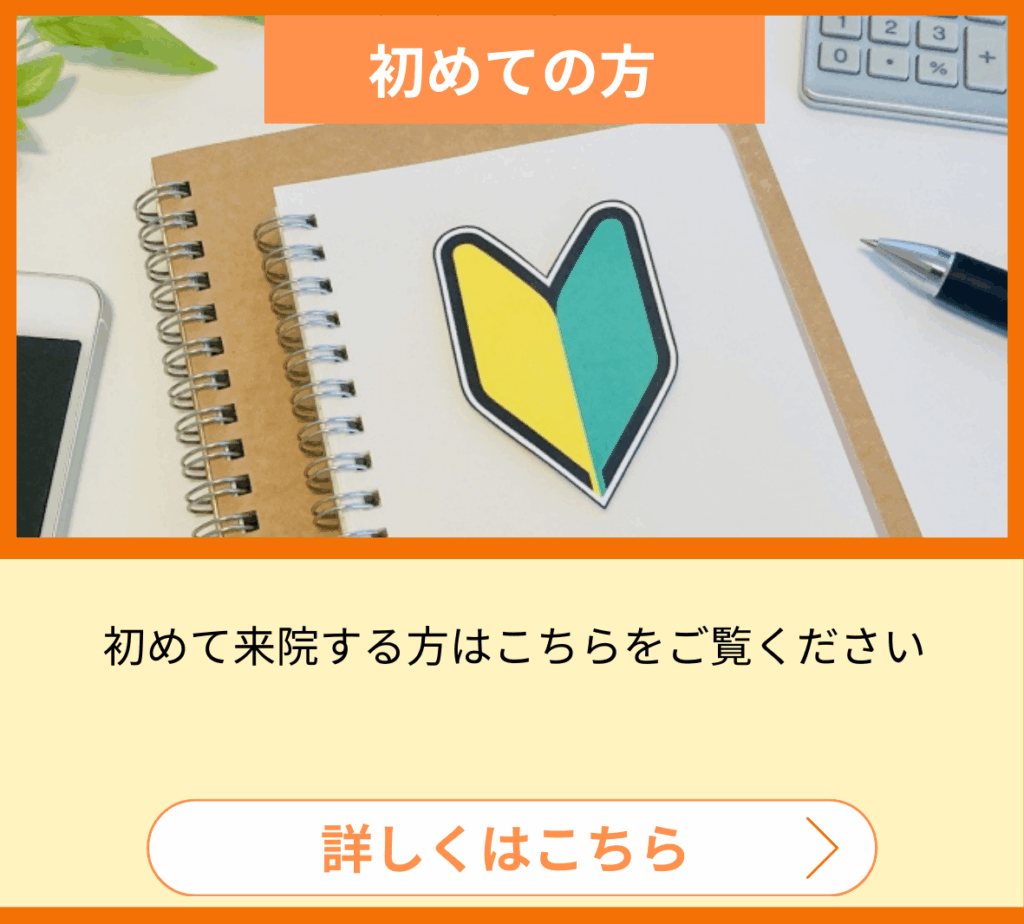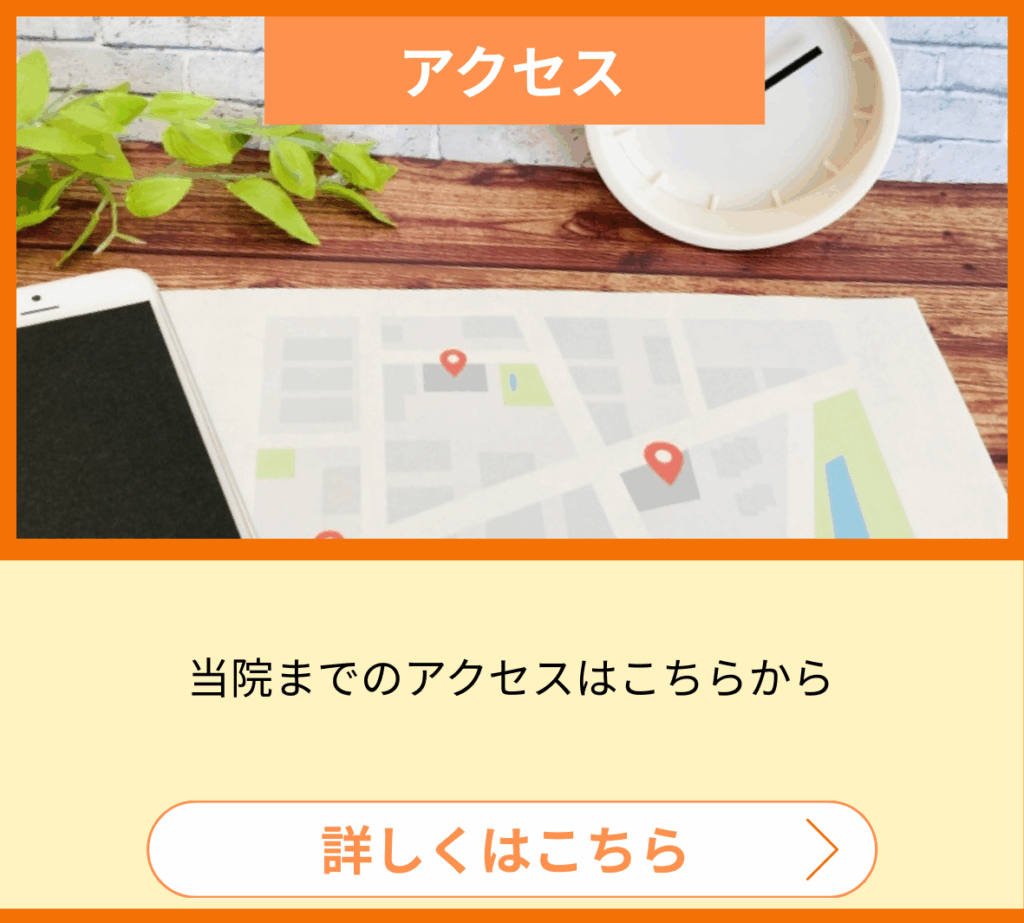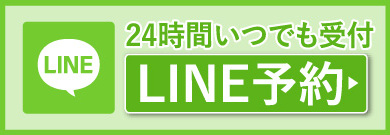緊張性頭痛とは? 症状・原因・治療法を西洋医学と東洋医学(鍼灸)から解説
こんにちは。平井鍼灸院の鈴木です。
「頭が締め付けられるように痛い」「長時間のデスクワークで頭が重い」そんな症状に悩まされていませんか?
その頭痛は、緊張性頭痛(きんちょうせいずつう)と呼ばれるタイプである可能性があります。

緊張性頭痛とは?
緊張性頭痛は、日本人に最も多いタイプの頭痛で、全頭痛患者の約7割を占めるといわれています。
特徴は、頭全体を「ギューッ」と締め付けられるような鈍い痛み。ズキズキとした拍動性の痛みを伴う偏頭痛とは異なり、鈍く重い感覚が持続するのが特徴です。
痛みは数時間から数日続くことがあり、慢性化すると「集中力の低下」「不安感や気分の落ち込み」を伴うこともあります。
まさに、心身の疲労が積み重なったサインといえるでしょう。
緊張性頭痛の主な特徴
後頭部からこめかみにかけて「締め付けられる」ような痛み
肩や首のこり・重だるさを伴う
長時間のデスクワーク・スマホ使用で悪化しやすい
めまいや軽い吐き気を伴う場合がある
偏頭痛のような「ズキズキ」ではなく、鈍く持続する痛み
痛みは軽度〜中等度だが、慢性的に続き生活の質を下げやすい
緊張性頭痛の原因とメカニズム(西洋医学的視点)
緊張性頭痛は、首や肩の筋肉のこわばりと血流障害が大きな原因です。
筋肉の過緊張
長時間同じ姿勢でいることや精神的ストレスにより、首や肩の筋肉が硬直します。血流の悪化
筋肉の硬直によって血管が圧迫され、酸素や栄養の供給が滞ります。痛み物質の蓄積
血流不足は「乳酸」などの老廃物を溜め込み、痛みを感じる神経を刺激します。
このようにして「筋肉のこり → 血流障害 → 神経刺激 → 頭痛」という悪循環が生まれ、頭全体に鈍い痛みが広がります。
自律神経と緊張性頭痛の関係
緊張性頭痛は、自律神経の乱れと深く関わっています。
交感神経優位の持続
ストレスや緊張状態が続くと交感神経が過剰に働き、血管が収縮し筋肉は硬直しやすくなります。副交感神経の抑制
身体を休ませる働きが低下し、回復力が落ちることで疲労や炎症が長引きます。悪循環の形成
筋肉の緊張 → 血流障害 → 痛み → さらにストレス → 自律神経の乱れ → 頭痛悪化
このループによって、慢性的に頭痛が繰り返されるのです。
東洋医学から見た緊張性頭痛
東洋医学では、緊張性頭痛は「気血の巡り」や「肝・脾の働きの乱れ」によるものと考えます。
肝気鬱結(かんきうっけつ)
精神的ストレスにより「気」の流れが滞り、頭痛や肩こりを引き起こす。気血両虚(きけつりょうきょ)
疲労や睡眠不足でエネルギー(気)や栄養(血)が不足し、頭に十分行き渡らず頭痛を生じる。痰湿(たんしつ)
体内の余分な水分(湿)が停滞し、頭が重だるい頭痛を引き起こす。
東洋医学では、このように**体質や生活習慣に応じた弁証(体質分類)**を行い、根本的な改善を目指します。
鍼灸でのアプローチ
緊張性頭痛に対して鍼灸では、筋肉の緊張を和らげるだけでなく、自律神経を整え、再発を予防することを目指します。
肝気鬱結型:太衝(たいしょう)、合谷(ごうこく)で気の流れを改善
気血両虚型:足三里(あしさんり)、三陰交(さんいんこう)で気血を補う
痰湿型:豊隆(ほうりゅう)、陰陵泉(いんりょうせん)で湿気を取り除く
また、風池(ふうち)・百会(ひゃくえ)・合谷(ごうこく)といった頭痛の代表的なツボを刺激し、頭部と首肩の血流を促進します。
まとめ
緊張性頭痛は、単なる首や肩のこりではなく、ストレスや生活習慣による自律神経の乱れが深く関わっています。
東洋医学では「気血の巡り」「肝・脾のバランス」を整えることで、頭痛を根本から改善し、再発しにくい体質を作ることを目指します。
鍼灸治療は、痛みの軽減だけでなく、自律神経の安定や疲労回復にも効果的です。
お困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
info_outline平井鍼灸院
- 住所
- 〒132-0035
東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号
 03-3683-7670
03-3683-7670
- 営業時間
- 火金 10:00~20:00
水 12:00~20:00
土 9:00~17:00
日 9:00~16:00 - 休業日
- 月曜・木曜・祝日
- アクセス
- JR総武本線平井駅から徒歩1分