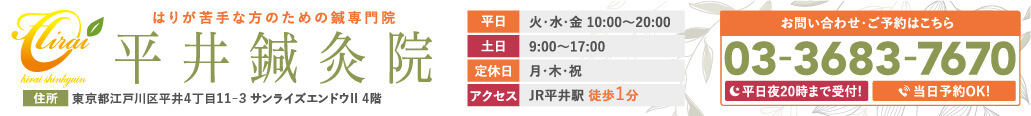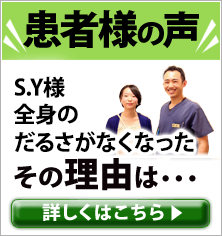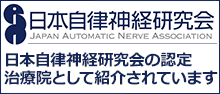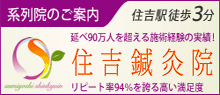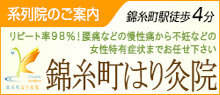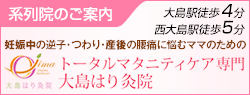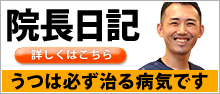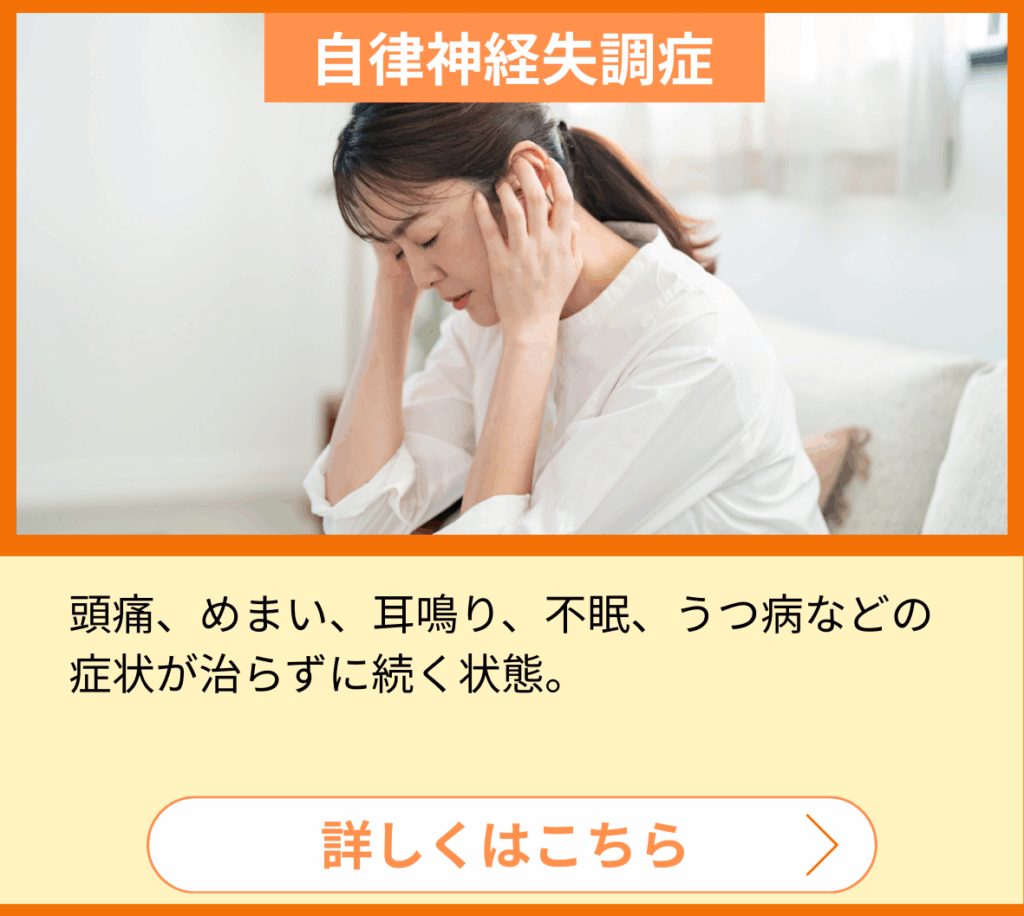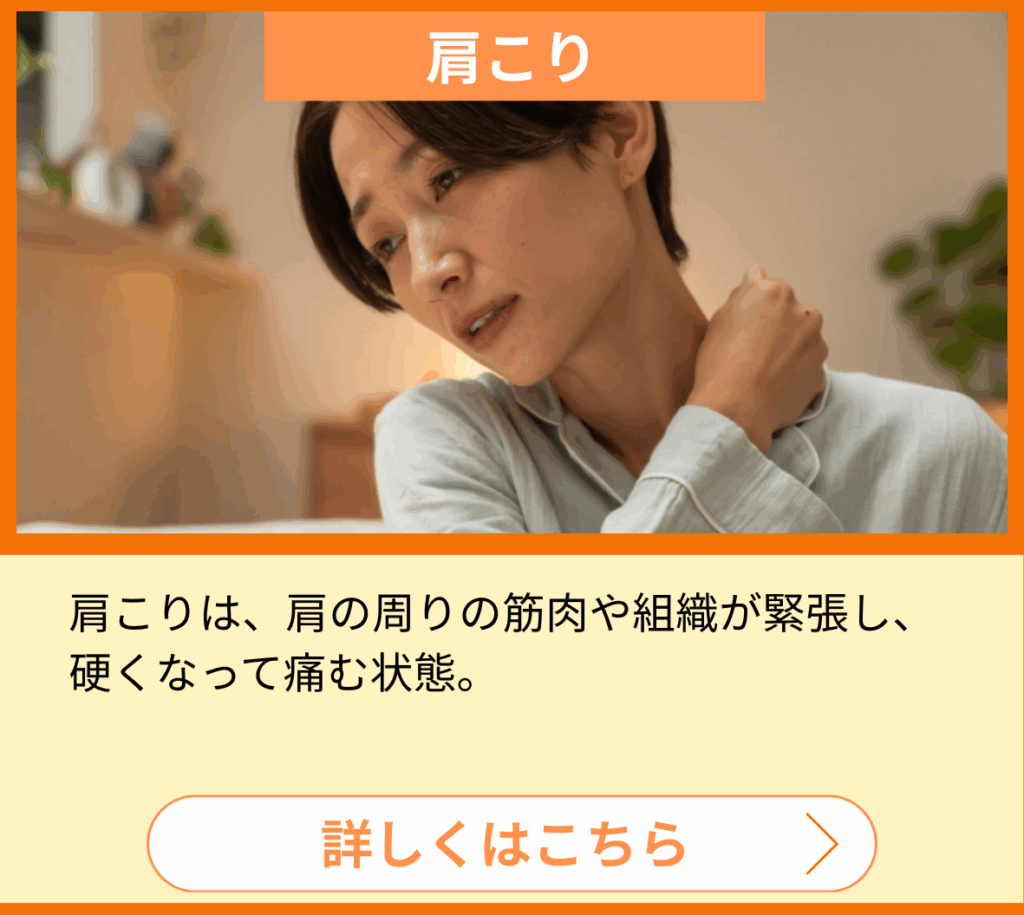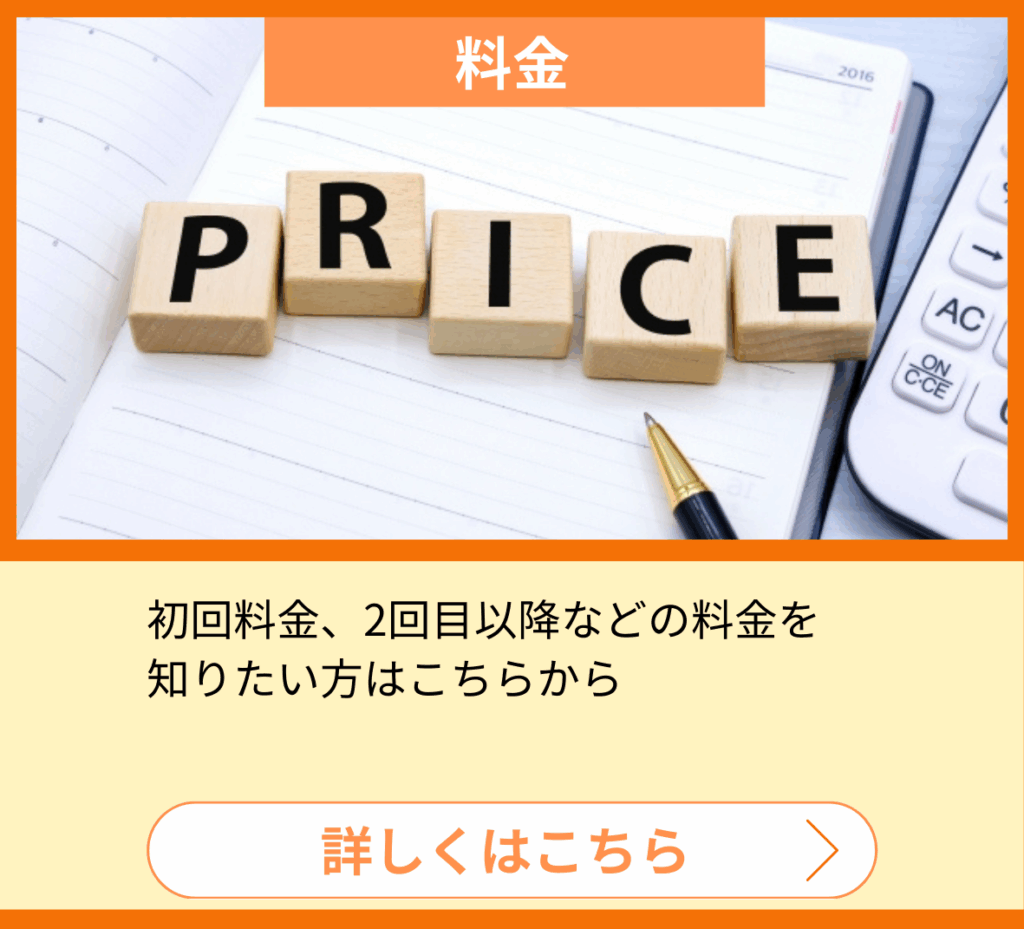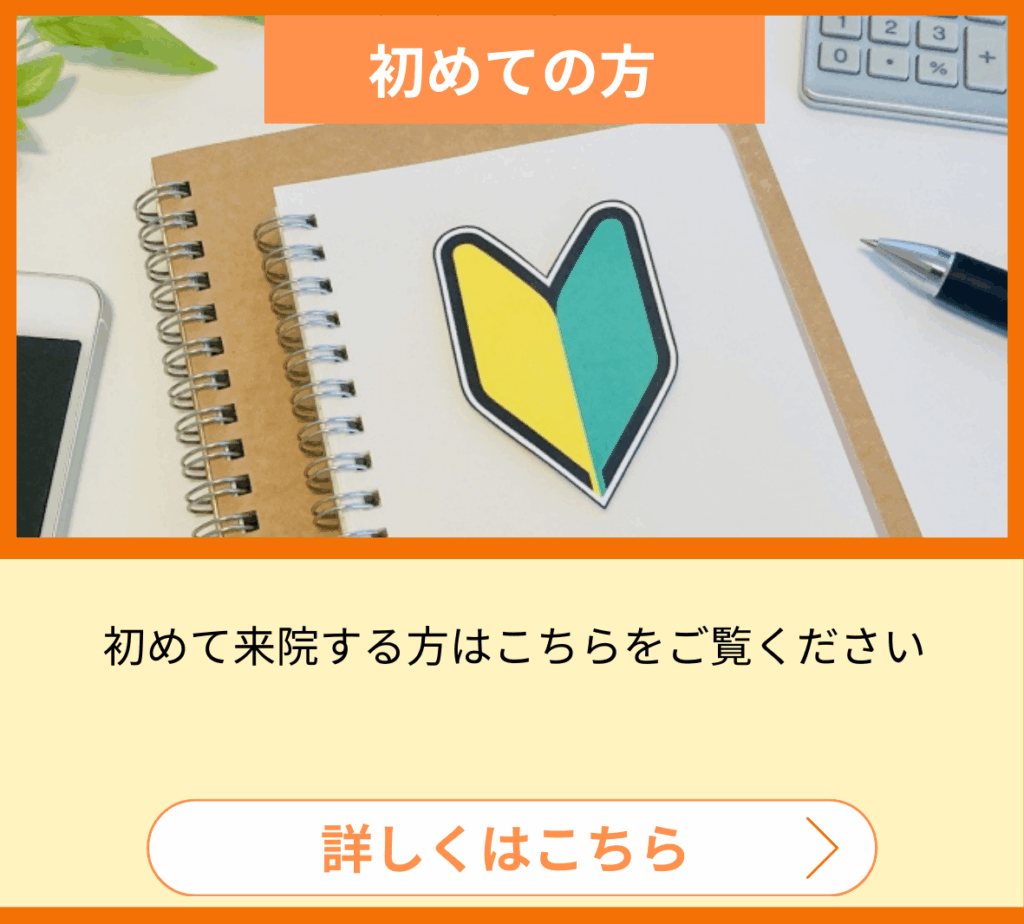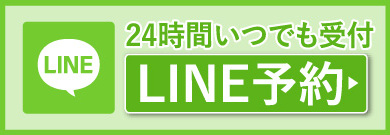慢性的なだるさと倦怠感の原因は?病院で異常なしでも安心できない理由
こんにちは。鈴木開登です。
「寝ても疲れが取れない」「常に体が重くてやる気が出ない」「病院で検査しても異常なしと言われた」――そんな慢性的な倦怠感に悩む方は少なくありません。現代社会ではストレス・不眠・栄養の乱れなどが積み重なり、体のエネルギーシステムが崩れてしまうことで、慢性的な疲労感や無気力につながることがあります。単なる疲れではなく、自律神経の不調や体質の乱れが関係しているケースも多いのです。
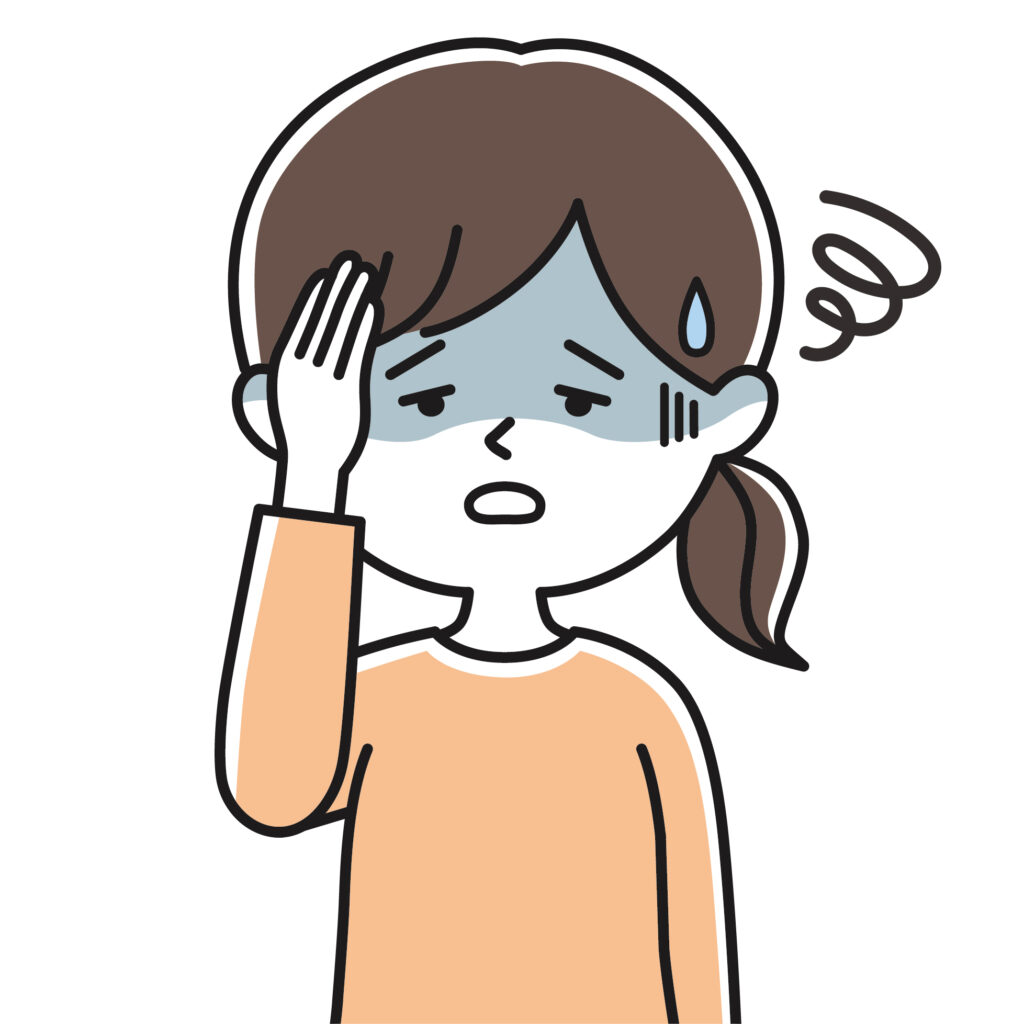
倦怠感とは?
倦怠感とは、体や心が常にだるく、活動する意欲が低下した状態を指します。大きく分けて以下の2つがあります。
身体的倦怠感:体が重い、疲れやすい、集中力が続かない
精神的倦怠感:やる気が出ない、気分が落ち込みやすい、ストレスで疲弊する
一時的な疲れとは異なり、休息を取っても改善しないことが特徴です。
倦怠感の症状とは?
全身のだるさや疲労感
集中力・思考力の低下
睡眠障害(眠れない、寝てもすっきりしない)
動悸・息切れ・めまい
食欲不振や胃腸の不調
抑うつ気分や不安感
これらは単独で出ることもあれば、複数が重なって慢性的な不調に発展することもあります。
西洋医学から見た倦怠感の原因
西洋医学的には、倦怠感の背景には以下のような原因が考えられます。
過労・睡眠不足:体の回復が追いつかない
ホルモン異常:甲状腺機能低下症、副腎疲労など
慢性疾患:肝臓・腎臓・心臓などの機能低下
貧血・低血糖:エネルギー不足で体がだるい
うつ病や慢性疲労症候群:精神的な要因による慢性倦怠感
特に「検査で異常なし」と言われても症状が続く場合は、自律神経や生活習慣の乱れが背景にあることが多いです。
自律神経と倦怠感の関係
自律神経は体のエネルギー消費や内臓の働きをコントロールしています。交感神経が過剰に働くと常に緊張状態となり、体が休まらず疲労が蓄積します。一方、副交感神経がうまく働かないと回復力が落ち、休んでも疲れが取れない状態になります。
また、ストレスや不安が長期間続くと自律神経が乱れ、睡眠障害や消化不良を引き起こし、さらに倦怠感を悪化させる悪循環に陥ります。
東洋医学から見た倦怠感
東洋医学では倦怠感を「気・血・水」の不足や滞りとしてとらえます。
気虚(エネルギー不足):食欲不振・疲れやすい・声に力がない
血虚(血の不足):めまい・集中力低下・不眠を伴う
気滞(気の滞り):ストレスによるイライラや胸のつかえ
痰湿(水分代謝の乱れ):体が重だるい・むくみ・頭のモヤモヤ感
鍼灸治療では「足三里」「関元」「三陰交」「百会」などのツボを使い、全身の巡りを改善しながら自律神経のバランスを整えることで、自然な回復力を高めていきます。
まとめ
倦怠感は単なる「疲れ」ではなく、自律神経や体質の乱れ、ホルモンや栄養不足など複数の要因が絡み合った不調です。鍼灸では全身の巡りを整え、自律神経を安定させることで根本改善を目指すことができます。
「疲れているだけ」と我慢せず、慢性的な倦怠感にお悩みの方は一度ご相談ください。
info_outline平井鍼灸院
- 住所
- 〒132-0035
東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号
 03-3683-7670
03-3683-7670
- 営業時間
- 火金 10:00~20:00
水 12:00~20:00
土 9:00~17:00
日 9:00~16:00 - 休業日
- 月曜・木曜・祝日
- アクセス
- JR総武本線平井駅から徒歩1分