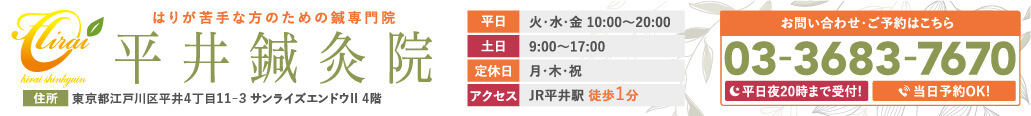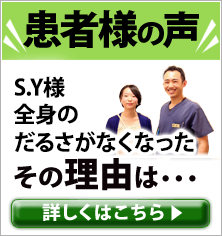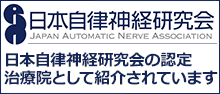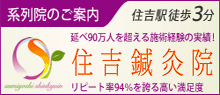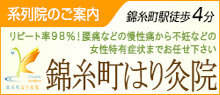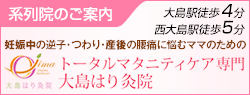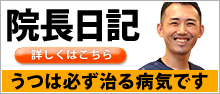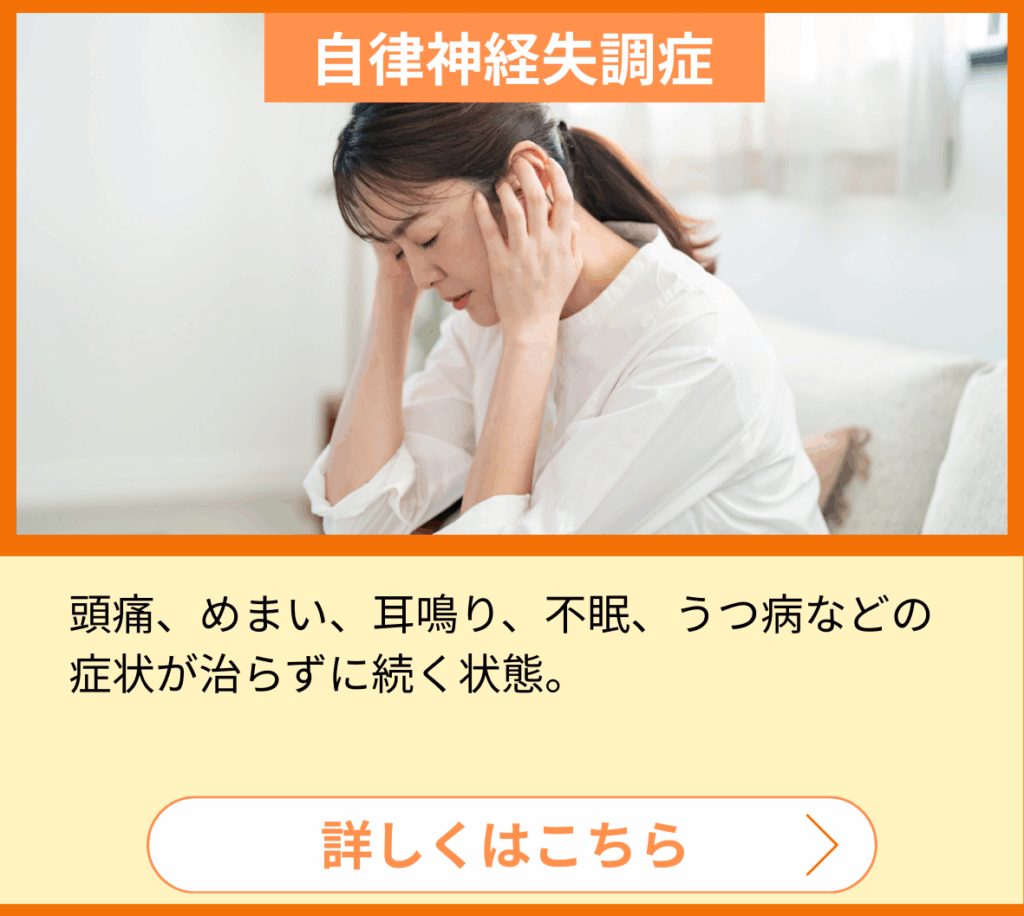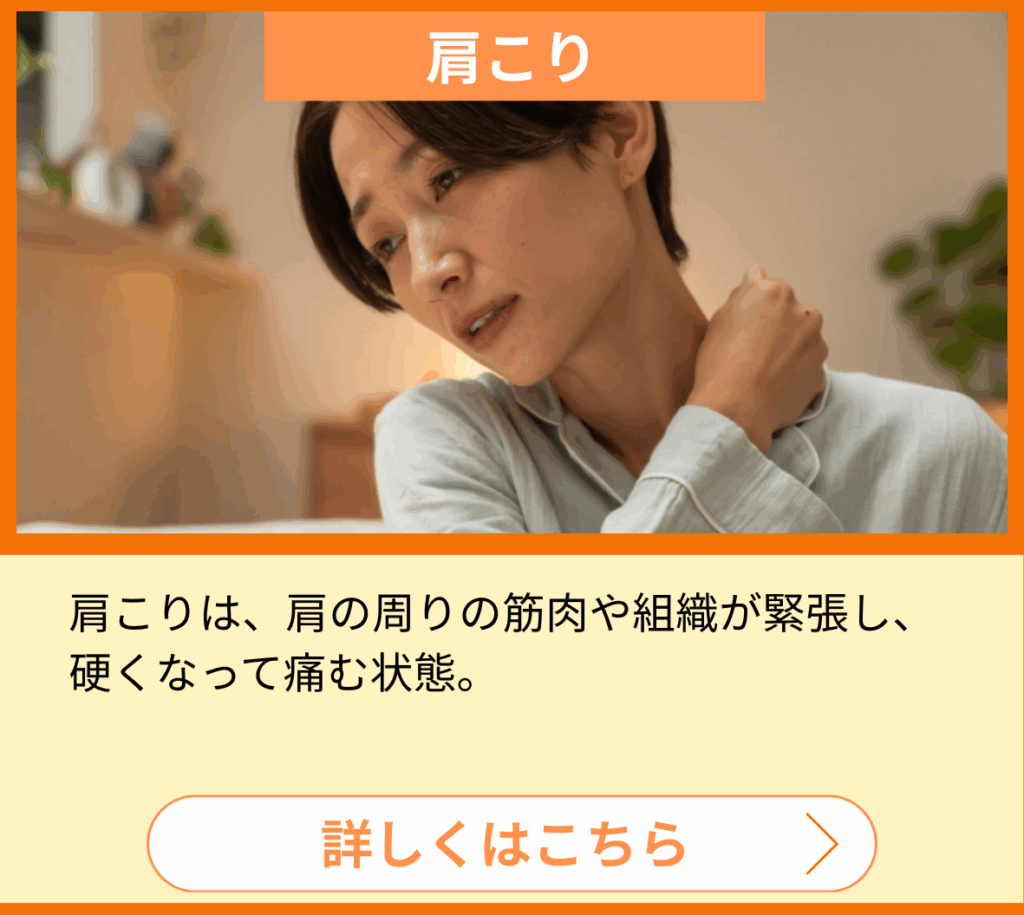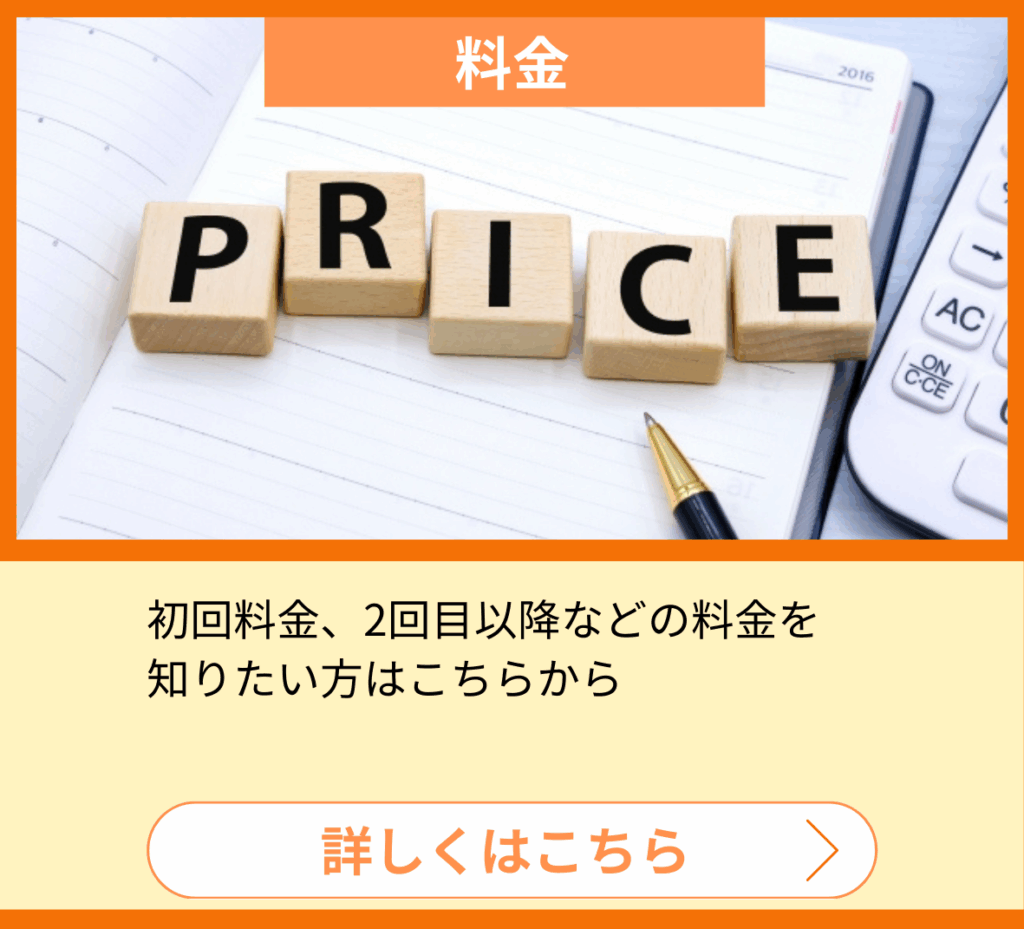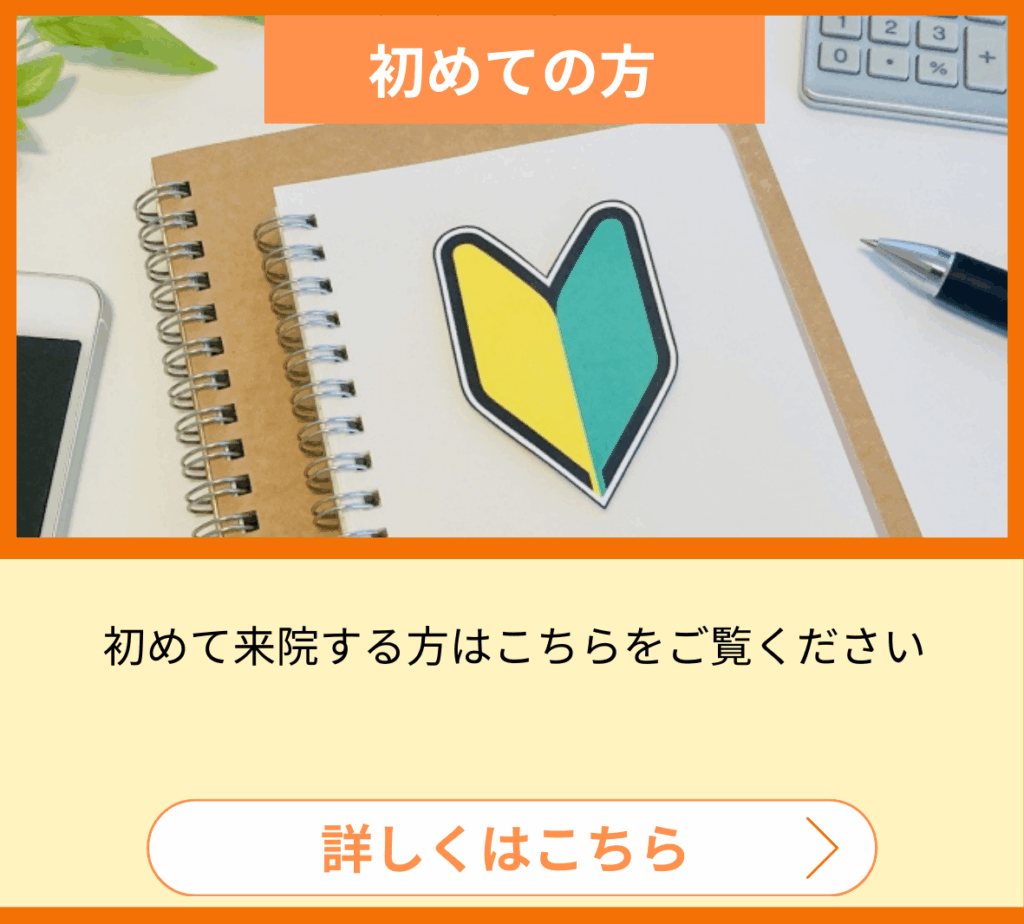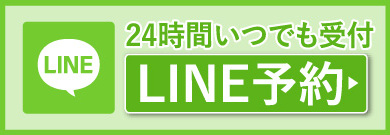下痢・便秘・腹痛でお困りの方へ:過敏性腸症候群と自律神経、鍼灸の選択肢
こんにちは。鈴木開登です。
「お腹が張る・下す・便が出ない…」といった不調が、検査では大きな異常がないのに繰り返す──そんなお悩みはありませんか?過敏性腸症候群(IBS)は消化器の器質的疾患がないにもかかわらず腹痛や便通異常が慢性的に続き、日常生活に支障をきたします。近年は「腸—脳(gut–brain)軸」「腸内フローラ」「自律神経」の関わりが注目されており、西洋医学的理解と東洋医学(鍼灸)の見立てを組み合わせることで改善の幅が広がります。ここでは原因・メカニズム・自律神経との関係・東洋医学的弁証と鍼灸の着眼点を詳しく解説します。

過敏性腸症候群(IBS)とは?
IBSは腹痛・腹部不快感を主症状に、便通異常(下痢型・便秘型・混合型・分類不能型)が続く機能性消化管障害です。内視鏡や血液検査で明らかな器質的病変が見つからない一方で、患者さんは強い苦痛を抱えます。症状は慢性で反復し、ストレスや食事、睡眠の乱れで悪化しやすいのが特徴です。
症状(どのように現れるか)
反復する腹痛や腹部不快感(便通で軽快・増悪することが多い)
便通異常:下痢、便秘、またはその両方が交互に現れる(混合型)
腹部膨満感・ガスが溜まりやすい・おならが増える
排便の切迫感や残便感(便が出てもスッキリしない)
ストレスや不安、睡眠不足で増悪することが多い
全身の倦怠感や頭痛・めまいを伴うことがある(腸—脳相互作用の影響)
症状は個人差が大きく、生活に与える影響もさまざまです。
西洋医学から見た主な原因と病態生理
IBSは単一原因では説明できず、複数の要因が重なって発症・持続すると考えられています。主要メカニズムを整理します。
1. 腸管運動異常(モチリティの乱れ)
腸の蠕動運動や分節運動のタイミング・強さが不規則になると、下痢や便秘が起きやすくなります。腸の過敏な収縮が腹痛の原因になることがあります。
2. 内臓知覚過敏(visceral hypersensitivity)
同じ腸の刺激でも痛みを強く感じやすい状態。通常は気にならないガスや拡張でも強い不快感や痛みを引き起こします。
3. 腸内微生物叢の変化(ディスバイオーシス)
腸内細菌のバランス変化がガス産生、短鎖脂肪酸の生成、粘膜の免疫反応に影響し、症状を助長することがあります。抗生物質使用後や感染性腸炎後に発症するケースも知られています。
4. 低度炎症・免疫活性化
一部のIBS患者では腸粘膜に微小な炎症や免疫細胞の活性化が見られ、感覚過敏や運動異常を助長します。
5. 腸粘膜バリアの障害(透過性の増大)
腸管の透過性が増すと、微生物や食物成分が粘膜を刺激しやすくなり、免疫反応や神経の過敏化につながります。
6. 神経伝達物質の関与(セロトニンなど)
腸は全身のセロトニンの大半を産生しており、セロトニンの異常は腸運動・分泌・感覚に影響します。
これらが相互に作用して、個々人で異なる「IBSの表現型(下痢主導、便秘主導、混合)」を作り出します。
自律神経との関係 — 腸と脳をつなぐ要の役割
IBSにおける自律神経(交感神経・副交感神経)の関与は極めて重要です。ポイントを整理します。
腸—脳軸(gut–brain axis):腸と脳は迷走神経や脊髄を介して双方向に情報をやり取りしています。情緒やストレスが腸の運動・分泌・知覚に影響し、逆に腸の状態が不安や気分に影響します。
交感/副交感のアンバランス:ストレスや不安で交感神経が過剰になると腸の蠕動や血流が乱れ、下痢や腹痛を誘発しやすくなります。逆に副交感(迷走神経)機能低下は消化・吸収・修復を妨げます。
起立・活動時の自律反応と症状悪化:自律神経の反応性が不安定な方は食後・心理的負荷・時間帯で症状が大きく揺れる傾向があります。
中枢感受性の変化:自律神経の乱れが中枢(脊髄・脳幹・前帯状回など)での痛み処理を変え、低刺激で強い不快を感じるようになることがあります。
臨床では、ストレス管理や睡眠改善、呼吸法などで自律神経を整えるとIBS症状が軽くなるケースが多く見られます。
東洋医学から見たIBSの見立て(弁証)と鍼灸的着眼点
東洋医学ではIBSを「気の失調」「脾(消化)の働き低下」「痰湿(湿邪)」「肝の疏泄失調」などの組合せで捉えます。代表的パターンと臨床像、鍼灸での着眼点を示します。
1. 肝気鬱結(ストレス型)
臨床像:腹部の張り・ガス・腹痛がストレスや情緒の変動で悪化する。便通は変動しやすい。
鍼灸の着眼:気の巡りを良くして肝の疏泄を助ける。代表穴:太衝(LR3)、合谷(LI4)、行間、期門。
2. 脾胃虚弱(消化力低下型)
臨床像:下痢傾向、食後の腹部不快・下痢、倦怠感、食欲不振。
鍼灸の着眼:補脾益気、消化機能を高める。代表穴:足三里(ST36)、中脘(CV12)、脾兪(BL20)。
3. 痰湿阻滞(湿重型)
臨床像:腹部膨満感、粘っこい便、体が重だるい。冷えや湿気で悪化。
鍼灸の着眼:利湿化痰、運水の促進。代表穴:豊隆(ST40)、陰陵泉(SP9)、三陰交(SP6)。
4. 気滞血瘀(循環不良型)
臨床像:腹部の強い差し込み痛、圧痛点あり、慢性化で停滞が目立つ。
鍼灸の着眼:活血化瘀、局所の圧痛点(阿是穴)への対応。代表穴:血海(SP10)、委中(BL40)、阿是。
自律神経調整の観点
東洋医学では肝の疏泄(気の巡り)と腎・脾の基礎(体力・代謝)を整えることで自律神経のバランスを回復させます。内関(PC6)や合谷(LI4)、百会(GV20)などを用いて不安・睡眠障害・自律機能不安定にも同時に働きかけます。
鍼灸で期待できること(臨床的効果の方向性)
腸管の過敏性や運動パターンの安定化(痛み・下痢・便秘の軽減)
腸—脳軸を介した不安・ストレス反応の緩和(自律神経バランス改善)
腹部のガスや膨満感の軽減、腹痛の頻度低下
体質(脾気・腎気)の底上げによる回復力向上
臨床では弁証に基づく配穴と、生活習慣改善を組み合わせることで持続した改善が期待できます。
まとめ:IBSは腸だけの問題ではない — 全身を整える視点が重要
IBSは腸の運動・感覚・免疫・腸内フローラ・自律神経・中枢処理が複雑に絡む多因子疾患です。
ストレスや生活リズムの乱れは自律神経を通して腸に直接影響し、症状の増悪や慢性化を招きます。
東洋医学(鍼灸)は弁証に基づき「気血・脾腎・肝」など体質面を整えつつ、自律神経の安定化に働きかける補完療法として有用です。
症状が続く場合はまず専門医での評価を受けたうえで、鍼灸や食事・睡眠・ストレス対策を組み合わせることでQOLの改善を図るのが現実的です。
お腹の不調でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
関連記事はこちら
info_outline平井鍼灸院
- 住所
- 〒132-0035
東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号
 03-3683-7670
03-3683-7670
- 営業時間
- 火金 10:00~20:00
水 12:00~20:00
土 9:00~17:00
日 9:00~16:00 - 休業日
- 月曜・木曜・祝日
- アクセス
- JR総武本線平井駅から徒歩1分