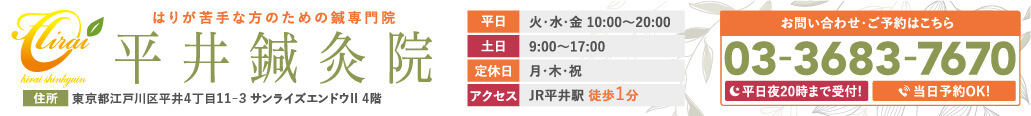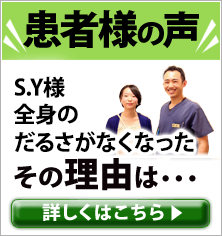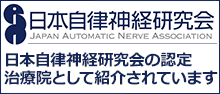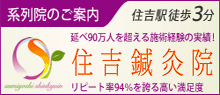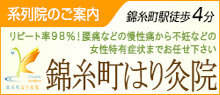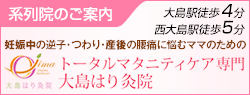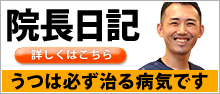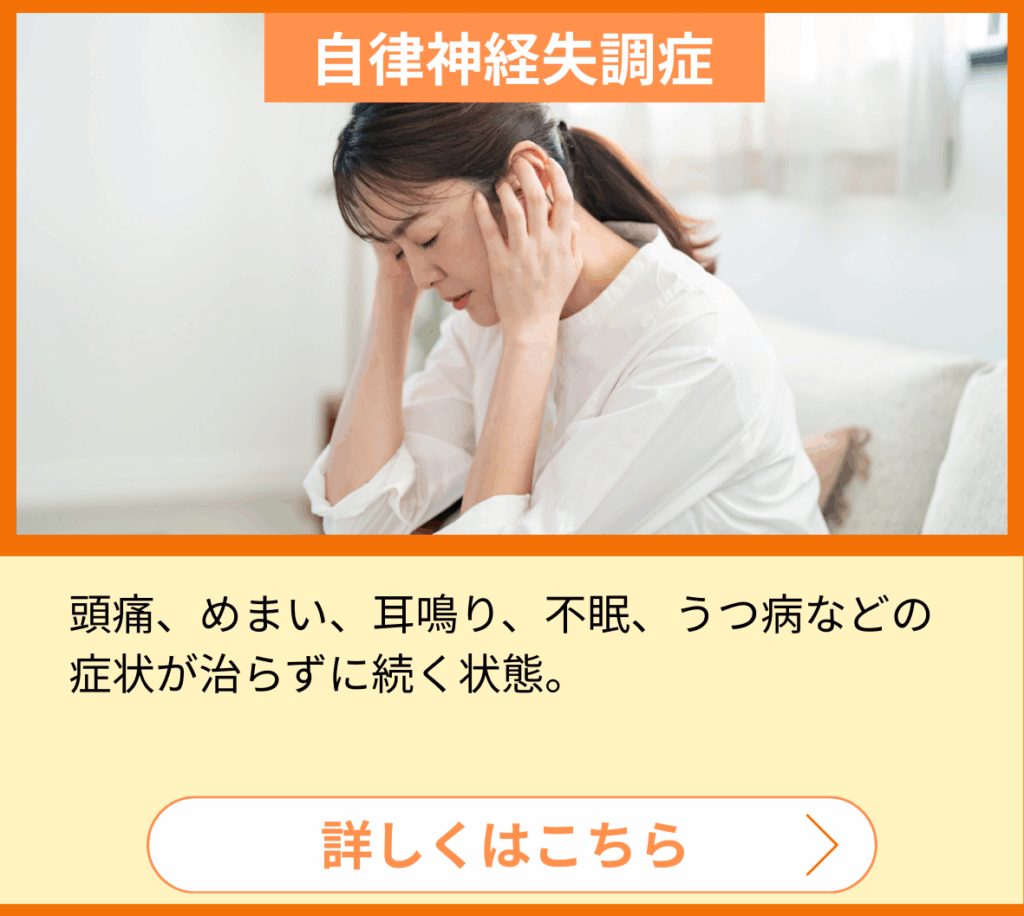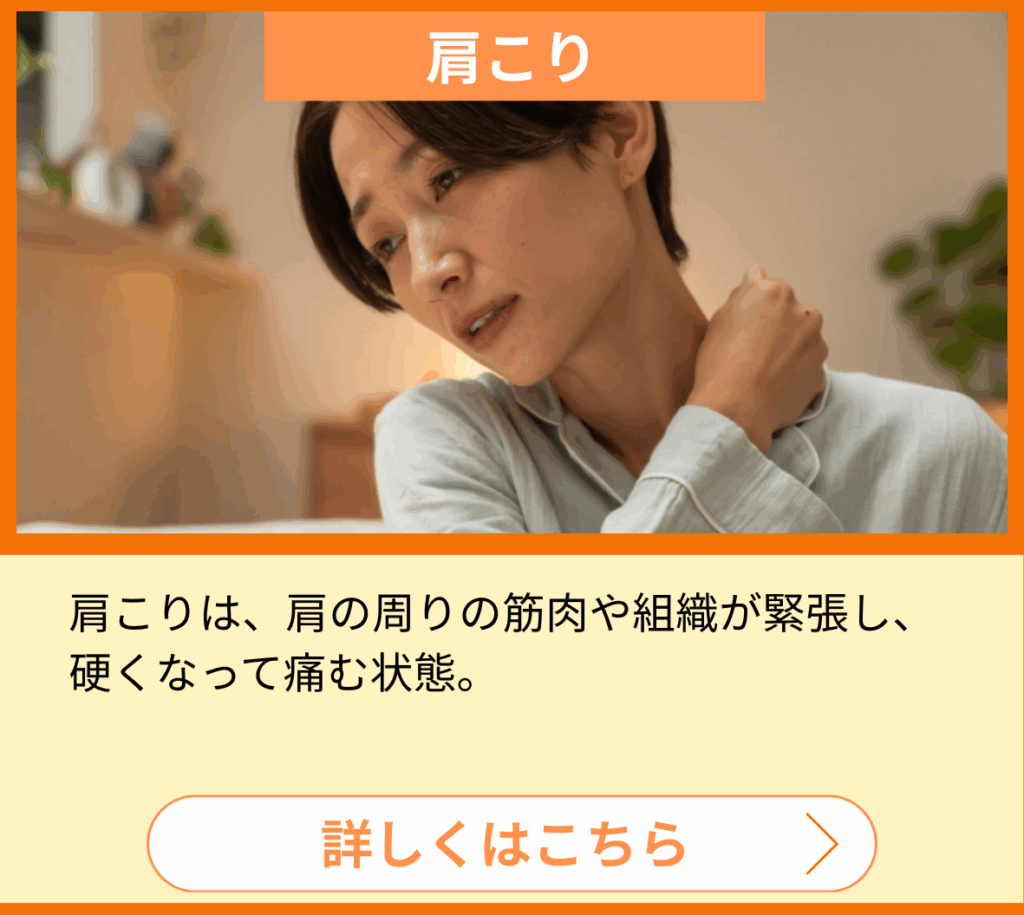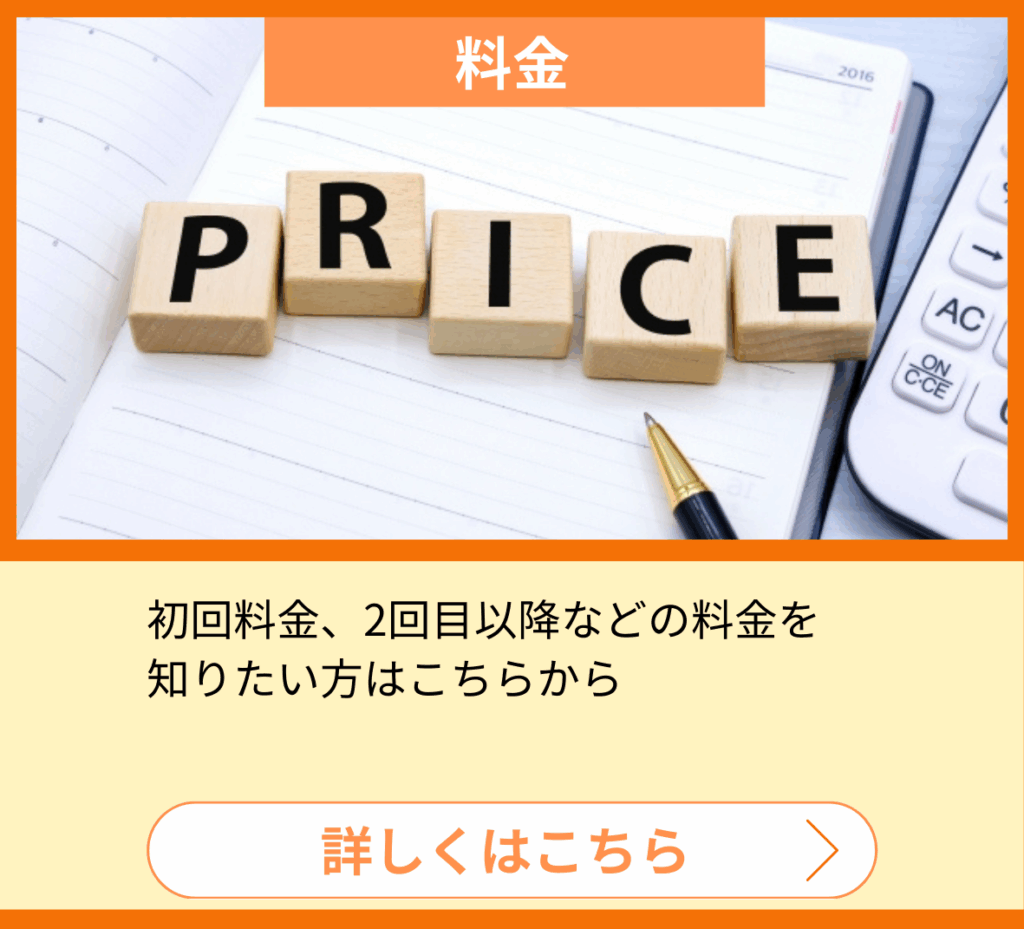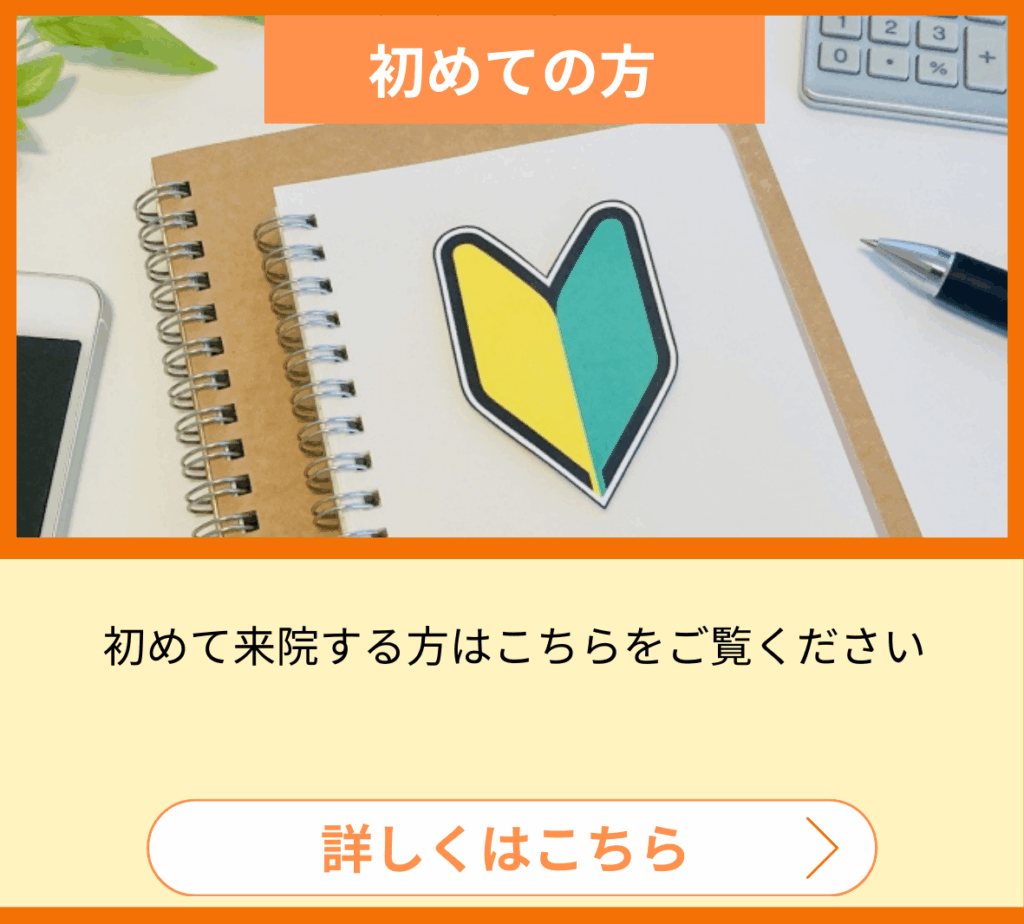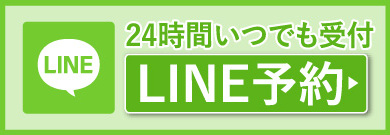起立性調節障害|朝の立ちくらみ・だるさの原因と自律神経の関係
こんにちは。鈴木開登です。
「朝 起き上がるとフラフラする」「登校や出勤がつらくて家を出られない」――特に思春期の子どもや若年者、また疲れやストレスの多い方からこうした相談を受けることが増えています。起立性調節障害(orthostatic dysregulation / orthostatic intolerance)は、立位や起立時に血圧や心拍の調節がうまくいかず、めまい・立ちくらみ・倦怠感などを引き起こす状態です。本稿では病態の本質、なぜ自律神経が関わるのか、東洋医学(鍼灸)的な見立てと介入の考え方をわかりやすく解説します。

起立性調節障害とは?
起立性調節障害(OD)は、姿勢変換(寝る→立つ、座る→立つ)に伴う循環調整が不適切で、脳や全身への血流・酸素供給が一時的に不安定になることで様々な症状を生じる状態を指します。若年者・思春期に多く、学校生活や日常活動が制限される原因になります。ODは単一疾患というより「自律神経による循環・血圧調整機能の失調」が中心となる症候群であり、以下のような多様な表現型があります(起立性低血圧、起立性頻脈症候群:POTSに類似する表現など)。
症状(どのように現れるか)
起立・立ち上がり時のめまい・ふらつき・立ちくらみ
立位での頭重感・倦怠感・息切れ・動悸
長時間立っていられない、座位や臥位で楽になる傾向
朝が起きにくい・登校や出勤が困難になる(特に若年者)
集中力低下・疲労感・頭痛・吐き気・不快感を伴うことが多い
時に起立時に血圧低下を来し、失神に至ることもある(頻度は状況により異なる)
症状は個人差が大きく、日内変動(時間帯で変わる)や天候・体調・ストレスで増減します。
西洋医学的視点
起立時には重力により下肢・腹部に血液が移動しますが、正常では自律神経(特に交感神経)の働きで静脈収縮・心拍増加・末梢血管抵抗の調節が起き、脳血流が保たれます。ODではこの自律応答が不十分または過剰にズレるために症状が出ます。代表的な病態要素は以下です。
血管反応の低下:静脈還流を高めるための血管収縮が弱く、下肢に血液が貯留しやすい。
心拍・血圧の不安定性:心拍数や血圧が過剰に増加(頻脈)したり低下したりして循環が不安定になる(POTS様、あるいは起立性低血圧)。
血液量の不足:慢性的な脱水傾向や血液量減少があると起立耐性が落ちる。
神経伝達物質・受容体の感受性変化:ノルアドレナリン等の神経伝達物質の放出や受容体の反応性の変化が自律調節に影響する。
中枢の調節異常:視床下部や脳幹での体位情報処理やホメオスタシス(恒常性)維持が不安定化している可能性。
合併症的要因:慢性疲労、睡眠障害、うつ・不安などが背景にあると症状の悪化や慢性化を招きやすい。
これらの要素が単独あるいは組み合わさって起立時に自律神経反応が不適切となり、ODの多様な症状を生みます。
自律神経との関係 — 起立調節の中枢と末梢
自律神経(交感/副交感)は、起立時の即時応答で最も重要な役割を担います。起立性調節障害の核心はまさにこの自律神経の“切り替え”の不具合です。
交感神経の役割:立ち上がりと同時に交感神経が活性化して心拍を上げ、末梢血管を収縮させることで血圧を維持します。ODではこの反応が弱かったり、あるいは過剰で不安定になったりします(反応性の乱れ)。
副交感神経の関与:迷走神経系の過反応は一部の失神に関与する場合があり、交感・副交感の協調が崩れると立位耐性が低下します。
血流と脳灌流の維持:自律神経の不適切な応答で脳への灌流が低下するとめまい・意識障害・集中力低下が生じる。
感受性と心理的増幅:自律神経の不安定性は身体感覚への注意を高め、症状の主観的重症度を増幅する(不安→交感亢進→症状増悪のループ)。
発症年齢と思春期の特異性:思春期は自律神経系と内分泌系の再編期であり、成長ホルモン・性ホルモンの変動が自律反応に影響してODが顕在化しやすいと考えられます。
臨床的には、自律神経の調整がODの改善とQOL回復に直結するケースが多く、自律神経を安定化させる介入が重要です。
東洋医学的観点(弁証と鍼灸的見立て)
東洋医学では起立性調節障害を単に血圧の問題と捉えず、気(エネルギー)・血(栄養)・津液(体液)・臓腑のバランスとして総合的に評価します。若年者に多い点を踏まえて、臨床でよくみられる弁証パターンと鍼灸の着眼点を示します。
代表的な弁証パターン
気血両虚(きけつりょうきょ)
臨床像:疲れやすく顔色が淡く、立ち上がるとふらつく。動悸や息切れ、倦怠感を伴うことが多い。
鍼灸着眼:補気補血により基礎体力と起立時の回復力を高める。代表穴:足三里(ST36)、気海(CV6)、脾兪(BL20)、心兪(BL15)。腎気虚(じんきょ)/腎陽虚(冷えが強いタイプ)
臨床像:体力低下・冷え・腰膝のだるさを伴い、朝の立ち上がりが特に苦手。
鍼灸着眼:補腎壮陽で基礎の「気」を補う。代表穴:腎兪(BL23)、命門(GV4)、太谿(KI3)。気機不利・肝鬱(ストレスや情緒的要因)
臨床像:ストレスや情緒の変動でめまいや動悸が増える。自律神経の変動が背景にある場合に多い。
鍼灸着眼:疏肝理気で気の巡りを整え、自律神経の安定を図る。代表穴:太衝(LR3)、合谷(LI4)、内関(PC6)。痰湿阻滞(体液代謝の乱れ)
臨床像:体が重だるく立位での不快感が強い、むくみを伴うことがある。
鍼灸着眼:利湿化痰・運水を促す。代表穴:陰陵泉(SP9)、豊隆(ST40)、三陰交(SP6)。
鍼灸的アプローチの概念
鍼灸では局所(首肩・胸部の緊張)と全身(気血・腎脾肝の調整)を組み合わせて、自律神経の切り替えを整えることを目指します。具体的には、内関(PC6)・神門(HT7)で不安や自律の乱れに働きかけ、足三里(ST36)・気海(CV6)で体力を補い、腎兪(BL23)・命門(GV4)で腎気を支える配穴がよく用いられます。刺激は患者の体力に合わせて穏やかに行い、反応を見ながら段階的に調整します。
まとめ
起立性調節障害(OD)は「立つ」という日常の動作に伴う自律神経の調節不全が核心であり、めまいや倦怠感、登校・出勤困難など生活の質に直結する症状を生みます。西洋医学的には血管反応・心拍・血液量・中枢調節の不均衡が関与し、東洋医学(鍼灸)は気血津液や臓腑のバランスを整えることで自律神経の安定化と回復力の強化を図ります。まずは原因の把握(専門医での評価)を前提に、自律神経を整える視点で生活リズムやストレスケア、必要に応じた鍼灸的サポートを組み合わせることが改善の近道となります。お悩みの方はお気軽にご相談ください。
関連記事はこちら
info_outline平井鍼灸院
- 住所
- 〒132-0035
東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号
 03-3683-7670
03-3683-7670
- 営業時間
- 火金 10:00~20:00
水 12:00~20:00
土 9:00~17:00
日 9:00~16:00 - 休業日
- 月曜・木曜・祝日
- アクセス
- JR総武本線平井駅から徒歩1分