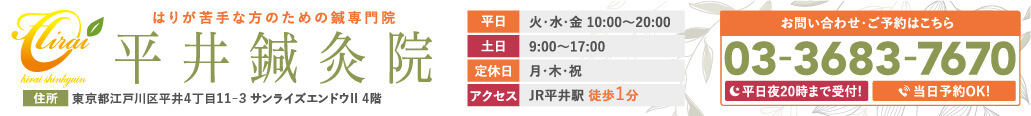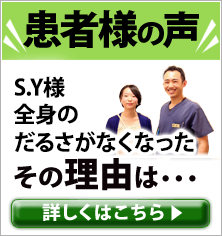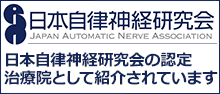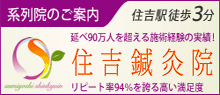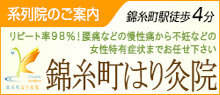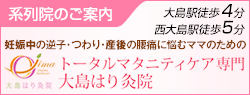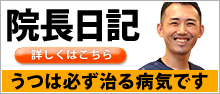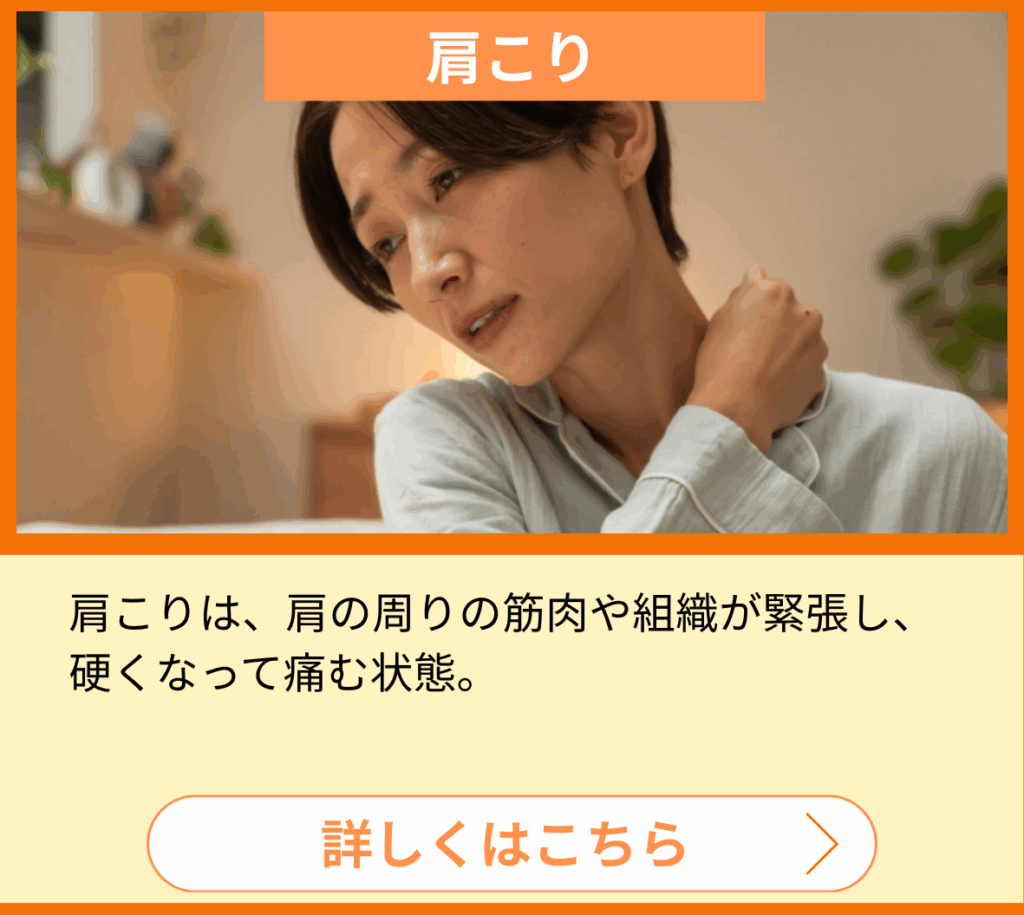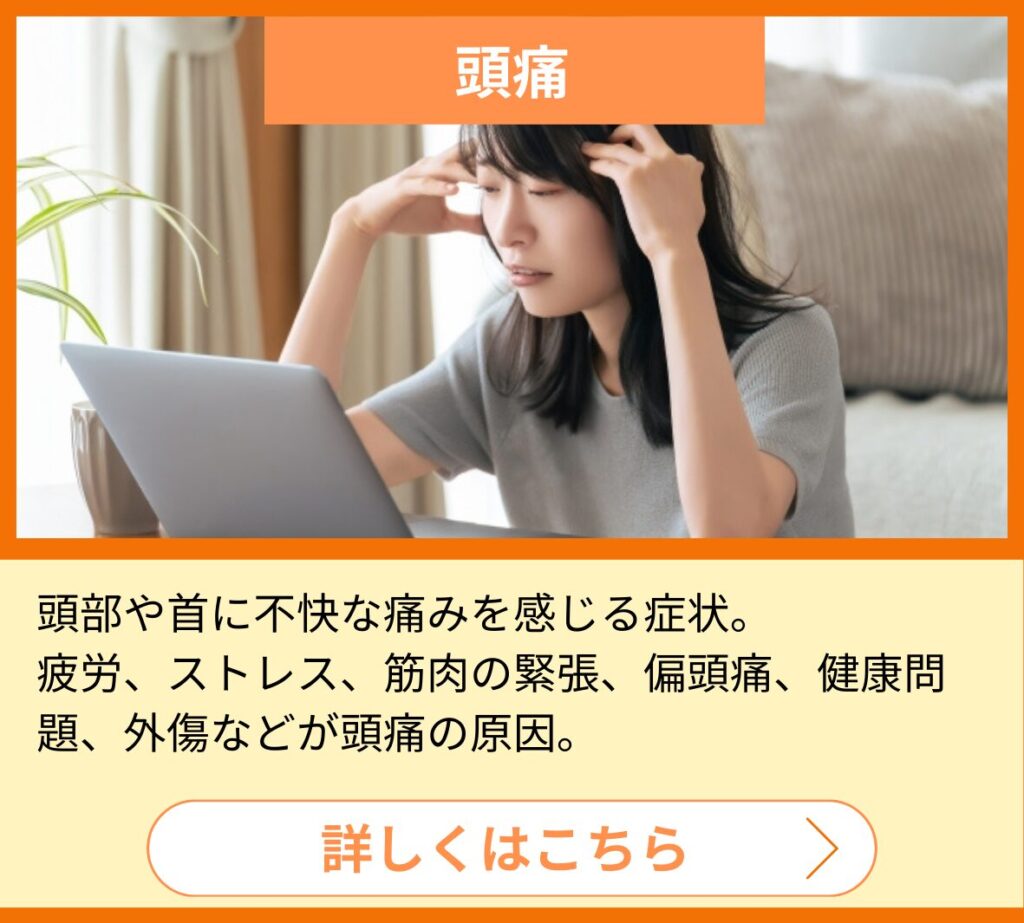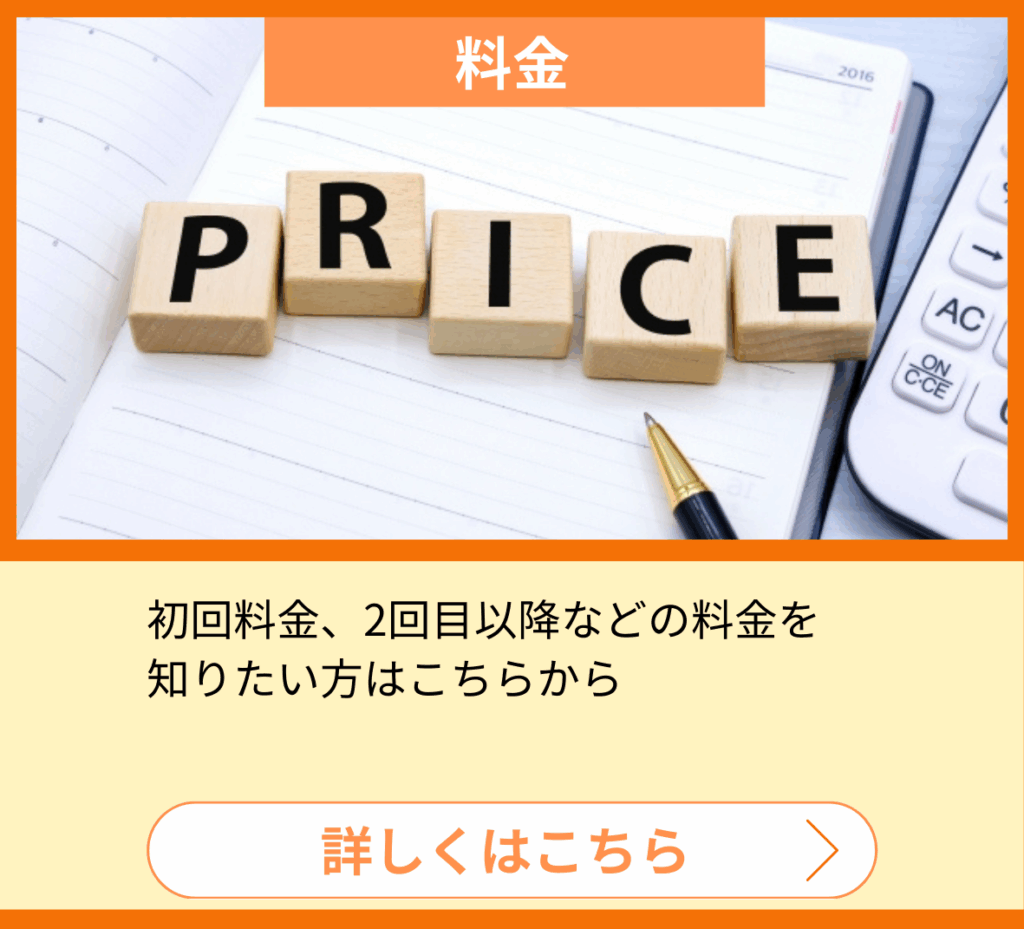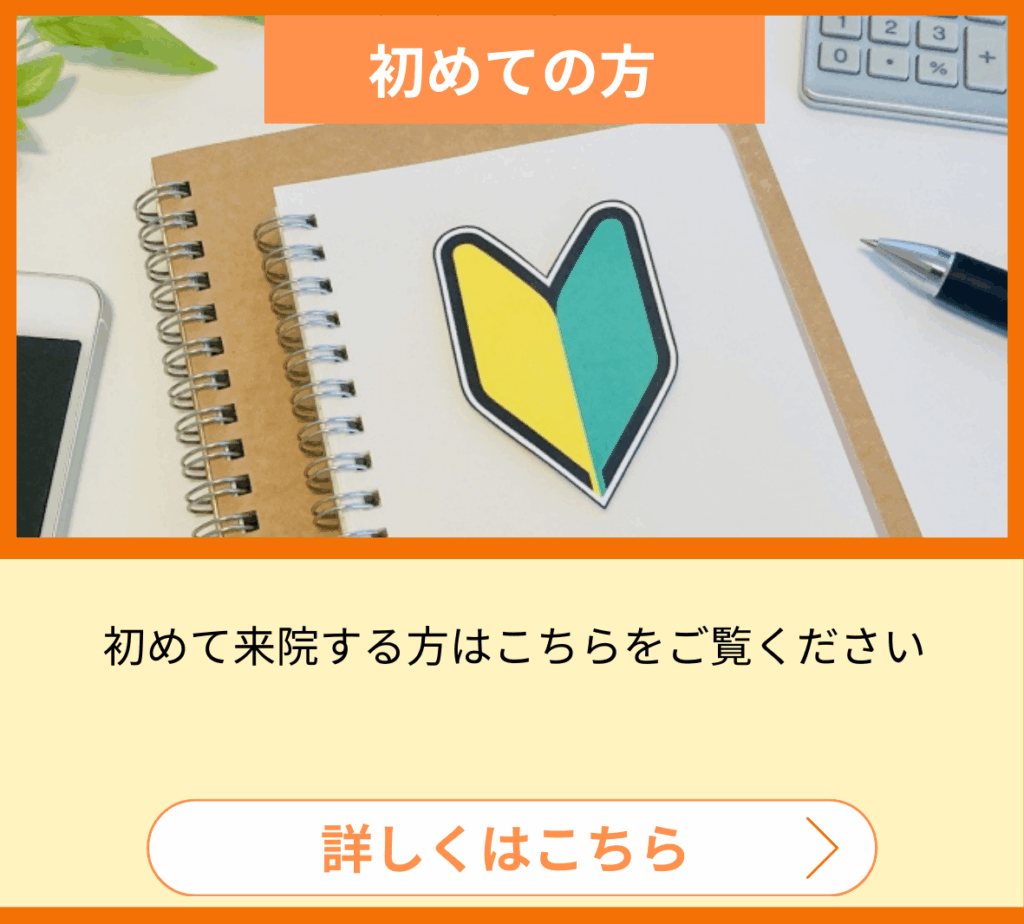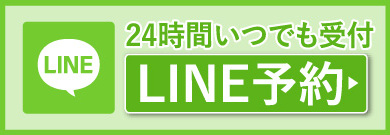緊張型頭痛と片頭痛 ― 自律神経の関係と鍼灸でできること
こんにちは。鈴木開登です。
「頭が締め付けられるように重い」「ズキズキ脈打つ痛みで日常生活に支障がある」――頭痛の訴えは多彩で、治療法やセルフケアも原因により変わります。ここでは、緊張型頭痛と片頭痛の違いをはっきりさせ、なぜ自律神経が関係するのか、東洋医学(鍼灸)からどのように見立てるかを詳しく解説します。
緊張型頭痛とは?
緊張型頭痛は最も一般的な頭痛タイプで、頭全体または両側に「締め付けられるような」「重だるい」痛みが続くのが特徴です。痛みは鈍く持続的で、数時間〜数日続くことが多く、吐き気や強い光過敏(フォトフォビア)はあまり伴わないのが典型です。長時間の同一姿勢、眼精疲労、頚肩部の筋緊張、慢性ストレスなどが主な誘因となります。
主な特徴(整理)
痛み:鈍い・圧迫感・締め付け感
部位:頭全体/後頭部〜側頭部にかけて多い
随伴症状:首肩こり、疲労感、時に軽度の光・音過敏
経過:数時間〜数日、慢性化すると毎日或いは頻発する
片頭痛(偏頭痛)とは?
片頭痛は血管・神経系の複合的な機序によって起きる発作性の頭痛で、**発作的に起きる「ズキズキした脈打つ痛み」**が特徴です。片側性で始まることが多く、悪心・嘔吐・光・音への過敏、運動で増悪する点が緊張型頭痛と異なります。前駆症状(オーラ:視覚障害など)を伴うことがあるほか、遺伝的素因や女性ホルモンの影響を強く受けます。
主な特徴(整理)
痛み:鋭い・脈打つ(ズキズキ)
部位:片側が多いが両側になることも
随伴症状:悪心・嘔吐、強い光・音過敏、歩行や日常動作で増悪
経過:数時間〜72時間程度の発作が典型(個人差あり)
誘因:月経周期、睡眠不規則、空腹、アルコール、特定の食品、ストレスの増減 など
緊張型頭痛と片頭痛の違い(比較ポイント)
痛みの性状:緊張型=鈍い締め付け感。片頭痛=脈打つ鋭い痛み。
随伴症状:緊張型=首肩こり・軽度の過敏。片頭痛=吐き気・強い光音過敏・活動で悪化。
発作性:片頭痛は明確な発作性(急に悪化し、数時間〜数日続く)。緊張型は持続性・慢性的になりやすい。
誘因:緊張型は筋骨格的ストレスや姿勢不良、眼精疲労が中心。片頭痛は神経血管反応、ホルモンや代謝の変動、特定食材など多様。
治療反応:片頭痛は専用のトリプタン等で効果が出ることがある一方、緊張型は筋緊張緩和や生活習慣改善が効きやすい。
ただし両者が重なること(混合型)や、片頭痛に首肩こりが強く出る場合もあるため、個々の症状を丁寧に拾うことが重要です。
西洋医学的病態生理(なぜ起きるか)
緊張型頭痛のメカニズム(要点)
筋緊張と末梢感覚入力:頚肩の筋肉・筋膜の慢性的な緊張が頭部の感覚入力を増やし、痛みをもたらす。
末梢から中枢への感作:慢性的な筋刺激が脊髄レベル・脳幹での感受性を高め(中枢性感作)、軽い刺激でも痛みを感じやすくなる。
心理社会的因子:持続的ストレスや不安が筋緊張を高め、痛み反応を増幅する。
片頭痛のメカニズム(要点)
三叉神経血管系の活性化:三叉神経が血管や髄膜を刺激し、CGRPなどの神経ペプチドが放出され血管と炎症の変化を誘導する。
皮質拡がり抑制:オーラを伴う場合、脳皮質での一過性の電気興奮とその後の抑制波が生じることが示唆されている。
遺伝的素因・ホルモン・環境トリガー:女性・家族歴が多い。月経・睡眠・食事の変化で閾値が下がる。
中枢感受性の変化:反復発作で中枢が過敏となり発作が起きやすくなることがある。
自律神経との関係
共通点(両者とも自律神経と深く関係)
ストレスや睡眠障害は交感神経優位を招き、痛みの閾値を下げる。
自律神経のアンバランスは血管の収縮・拡張、消化機能、睡眠回復に影響し、頭痛の発症・悪化に寄与する。
緊張型頭痛における自律神経の役割
慢性的な交感神経の緊張→筋緊張持続→局所血流低下→疲労物質(乳酸等)蓄積→痛み。
副交感神経の働きが弱いと夜間の回復が不足し慢性化しやすい。
片頭痛における自律神経の役割
発作期には副交感神経的反応(例:涙、鼻汁)や交感神経の変動が見られることがあり、三叉神経–自律神経間の相互作用が重要視される。
発作前後に自律神経機能が変動し、前兆や回復に関与する(起床時の自律反応、睡眠の乱れが誘因になりやすい)。
CGRPを中心とする血管と神経の反応は自律神経調節とも関連する。
まとめると、自律神経は頭痛の発生閾値や持続・増悪の程度を決める重要なモジュールであり、両方の頭痛で自律神経を整えることが臨床的に有効です。
東洋医学(鍼灸)的見立て — 弁証と対処の考え方
東洋医学では、頭痛は気血の巡りの乱れ・臓腑の不調・痰湿や瘀血の停滞などとして把握します。緊張型と片頭痛それぞれでよくみられる弁証例と代表的な配穴(代表例)を示します。
緊張型頭痛(弁証と配穴の例)
肝気鬱結(ストレス型)
臨床像:首肩のこわばり、イライラ、頭が締め付けられる。
配穴例:合谷(LI4)、太衝(LR3)、風池(GB20)、肩井(GB21)、天柱(BL10)。気血両虚(慢性疲労型)
臨床像:疲れやすく締め付け感が慢性的。
配穴例:足三里(ST36)、気海(CV6)、三陰交(SP6)、百会(GV20)。瘀血型(慢性のこりと痛み)
臨床像:局所が鋭く固定した痛み、圧痛点。
配穴例:阿是穴(圧痛点)、委中(BL40)、陽陵泉(GB34)、行間(LR2)。
片頭痛(弁証と配穴の例)
肝陽上亢/肝火(ストレス・閾値低下)
臨床像:ズキズキした高音域の痛み、イライラ、目の充血。
配穴例:太衝(LR3)、合谷(LI4)、風池(GB20)、百会(GV20)、内関(PC6)。痰濁阻滞(低音の重さやめまいを伴うもの)
臨床像:頭が重くすっきりしない感覚、吐き気を伴うことも。
配穴例:中脘(CV12)、豊隆(ST40)、足三里(ST36)、風池(GB20)。血虚(貧血や体力低下に伴う)
臨床像:疲労感とともに発作が起きやすい。
配穴例:血海(SP10)、三陰交(SP6)、足三里(ST36)、合谷(LI4)。
鍼灸では局所(首・肩・頭部)の緊張を緩めると同時に、弁証に基づいて全身の気血の巡り・臓腑のバランスを調整し、自律神経の安定化を図ります。痛みの性状や誘因(睡眠・月経・食事)を丁寧に聴取して配穴を決めます。
鍼灸で期待できる効果
頚肩の筋緊張緩和 → 緊張型頭痛の頻度・強度低下
自律神経の調整(交感の抑制・副交感の誘導) → 発作閾値の上昇、睡眠改善
血流改善・局所代謝の正常化 → 痛みの回復促進
ストレス・不安の軽減 → 発作誘因の減少
複数回の施術で症状の頻度や生活の制限が改善するケースが多く、セルフケアと組み合わせることで効果が安定しやすくなります。
まとめ
緊張型頭痛と片頭痛は症状・機序・治療の起点が異なる頭痛群ですが、どちらも自律神経の状態が発症閾値や慢性化に影響する点では共通しています。緊張型では主に筋骨格的緊張と末梢→中枢の感作が中心、片頭痛では三叉神経血管系・中枢の過敏性・ホルモンや遺伝的因子が重要です。東洋医学(鍼灸)は弁証に基づく個別対応で筋緊張を緩める+自律神経を整える+気血の巡りを改善することを通じて、両者の頭痛に対して補完的に効果を発揮します。
頭痛の頻度が高い、生活に支障が出る、いつもと違う痛み方がある場合は専門医にご相談のうえ、鍼灸や生活習慣の見直しを組み合わせると改善の幅が広がります。
関連記事はこちら
info_outline平井鍼灸院
- 住所
- 〒132-0035
東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号
 03-3683-7670
03-3683-7670
- 営業時間
- 火金 10:00~20:00
水 12:00~20:00
土 9:00~17:00
日 9:00~16:00 - 休業日
- 月曜・木曜・祝日
- アクセス
- JR総武本線平井駅から徒歩1分