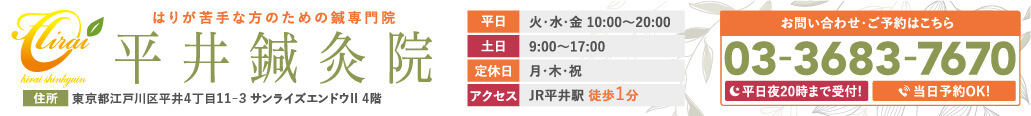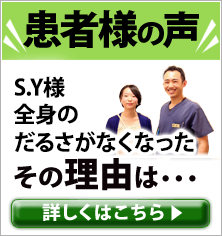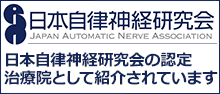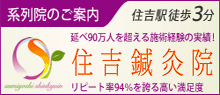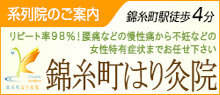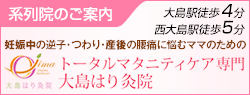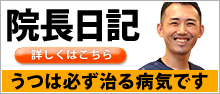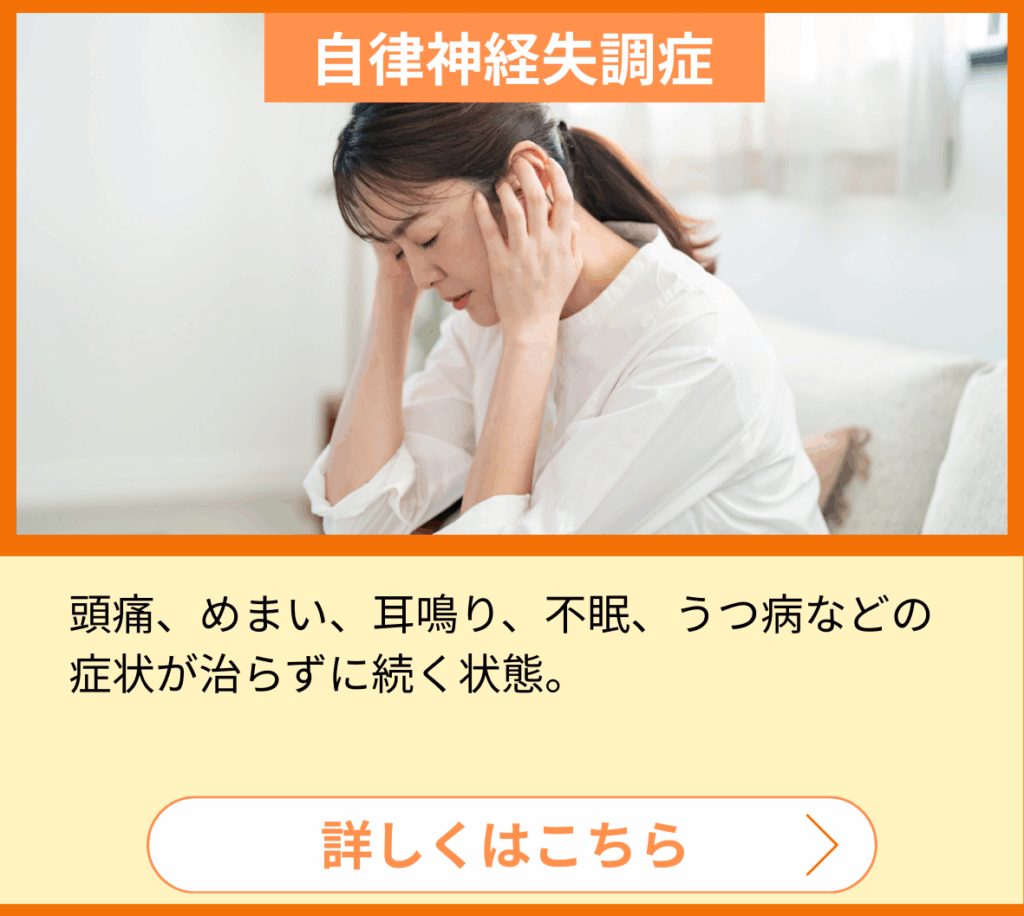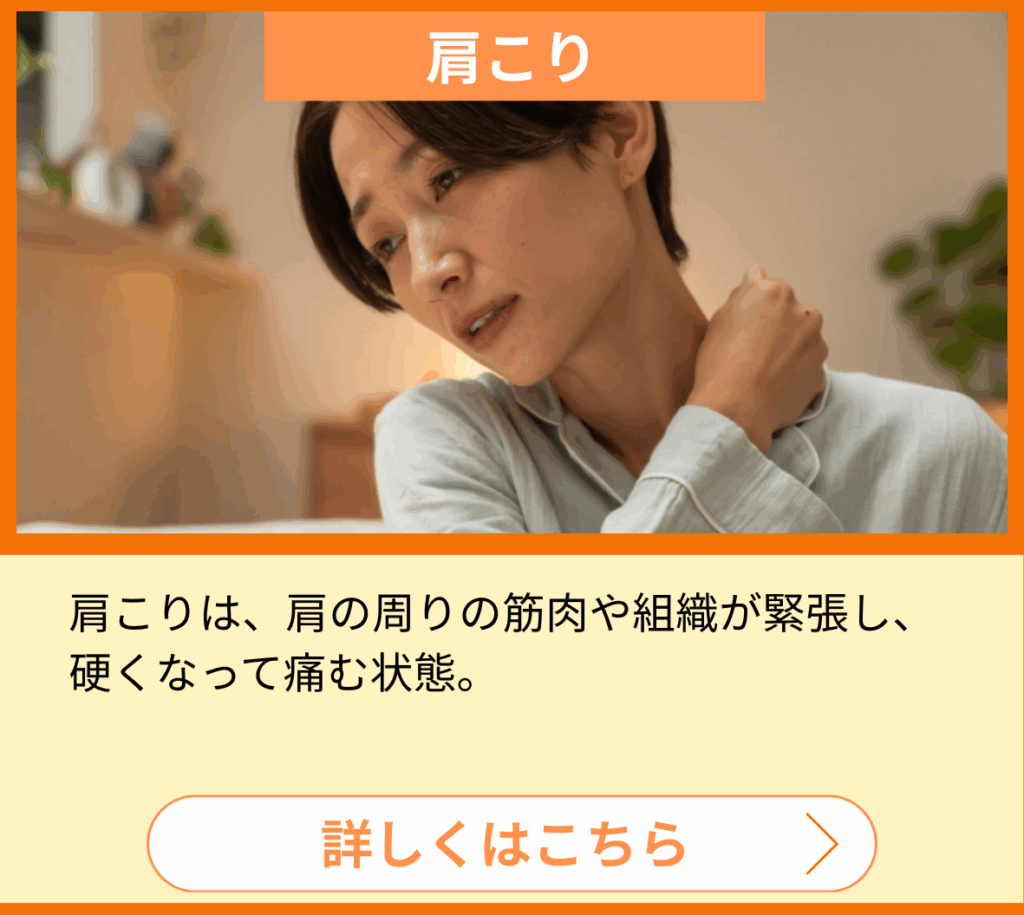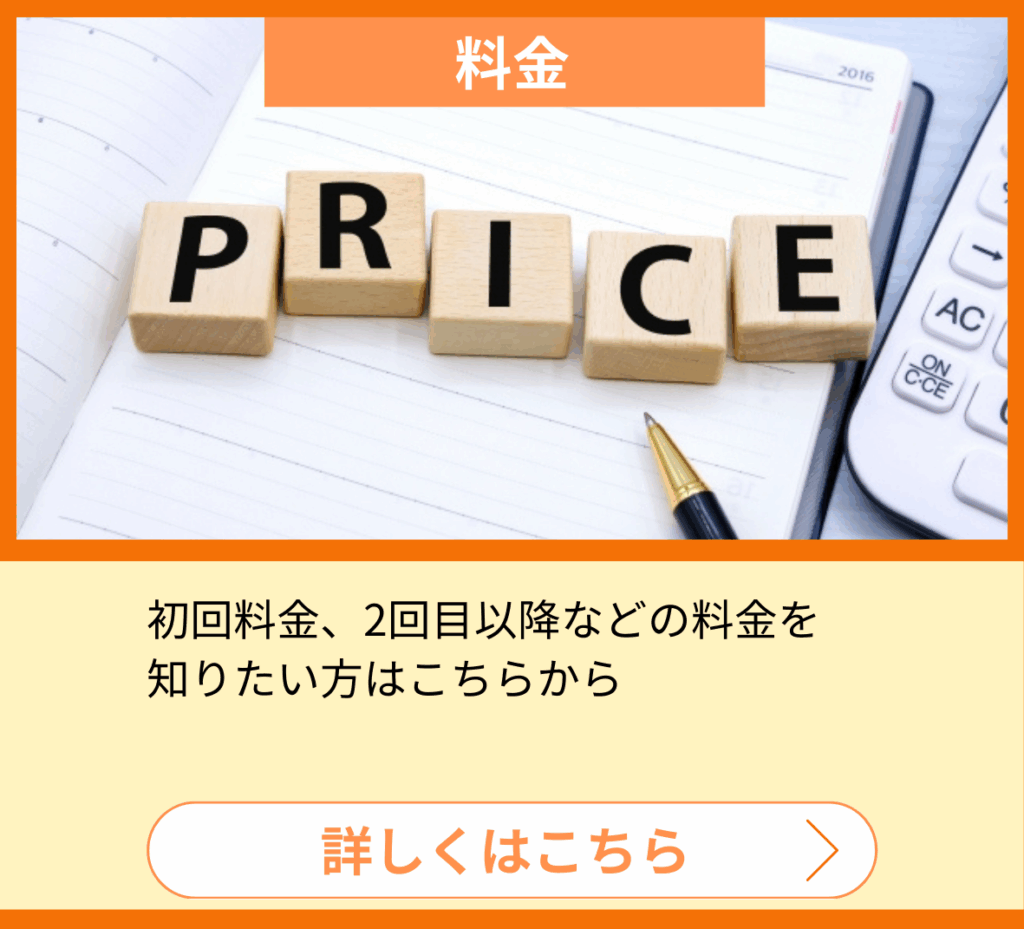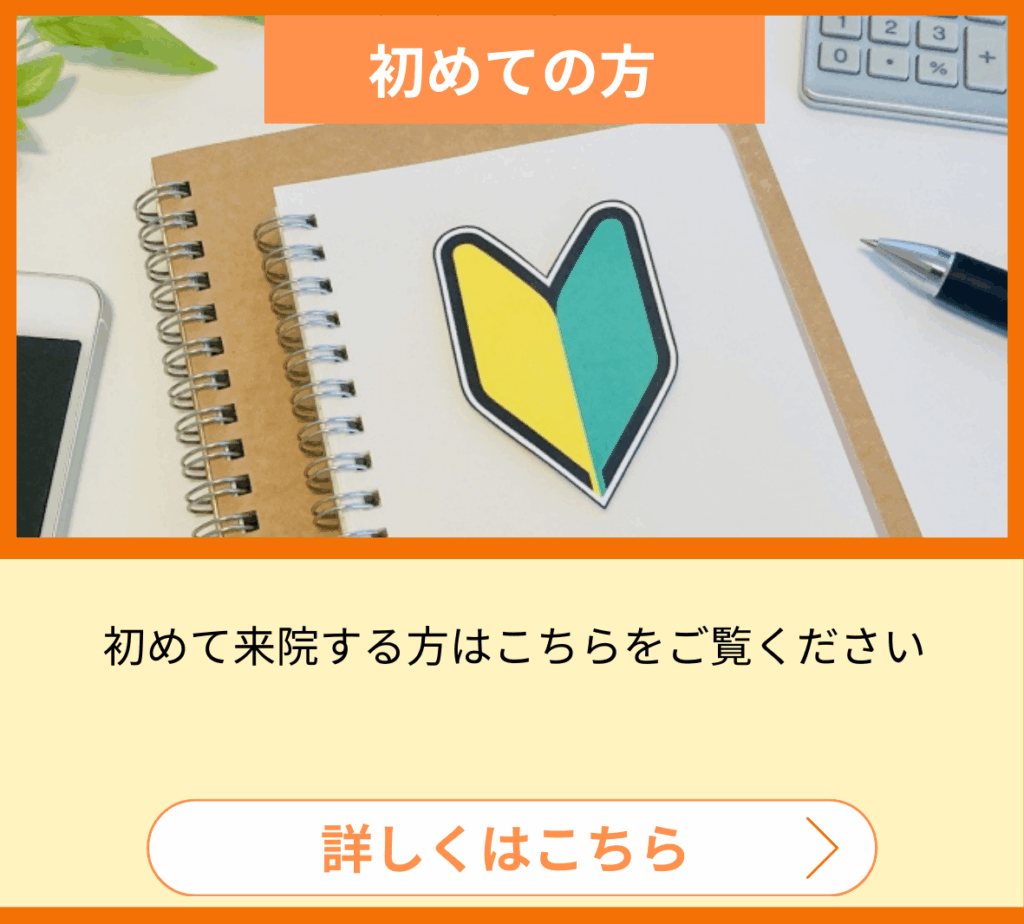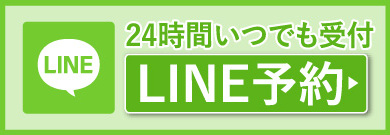慢性じんましん|原因がわからない症状と自律神経の関係をわかりやすく解説
こんにちは。鈴木開登です。
「皮膚に突然赤い盛り上がり(じゅくっとした発疹)が出てかゆくなる」「薬を飲むと治まるがすぐ再発する」――慢性的に繰り返す蕁麻疹(じんましん)はQOLを大きく下げます。検査で明確なアレルギー原因が見つからないことも多く、原因不明で悩まれている方が非常に多いのが現状です。本記事では、慢性蕁麻疹の定義・症状・西洋医学的な病態生理、自律神経との関係、東洋医学(鍼灸)からの見立てとアプローチ、日常でできる対策まで詳しく解説します。

慢性蕁麻疹とは?
慢性蕁麻疹は、6週間以上にわたって反復してじんましんが出る状態を指します。一般に「蕁麻疹(じんましん)」は一過性の皮膚の膨疹(丘疹・紅斑)と強い掻痒(かゆみ)を伴い、数時間〜数日で消えることが多いですが、これが何度も繰り返す場合を慢性と呼びます。原因が特定できないことが多く、「慢性特発性蕁麻疹(慢性自発性蕁麻疹:CSU)」と診断されることが多い一方、物理的刺激(温度・圧迫・運動)で誘発されるタイプもあります。
症状
突然、境界のはっきりした赤い膨疹(膨隆疹)が出現し非常に強いかゆみを伴う
発疹は数時間〜24時間程度で消えるが、別の場所に再出現することが多い
膨疹はサイズや形が変わりやすく、融合する場合もある
時に血管性浮腫(顔面や唇・まぶた・手足が腫れる)を伴うことがある
日内変動や季節・温度・ストレスで悪化・寛解を繰り返す
生活の質の低下、睡眠障害、不安・うつ状態を伴うことがある
蕁麻疹が長引く場合は、症状のパターン(出やすい誘因、出現時間帯、伴う全身症状)を記録しておくと診断・対策に役立ちます。
西洋医学的視点(主な原因と病態生理)
慢性蕁麻疹の中心的メカニズムは 皮膚の肥満細胞(マストセル)や好塩基球の脱顆粒(デグラニュレーション) によるヒスタミンなどのメディエーター放出で、これが血管透過性を高めて膨疹・かゆみを引き起こします。主な関連因子は以下の通りです。
自己免疫性機序:自己抗体(IgG)がマストセル表面の受容体(FcεRI)やIgEに結合して活性化することで慢性の脱顆粒が起きるタイプが存在します(自己免疫性蕁麻疹)。
ヒスタミン以外のメディエーター:ヒスタミン以外にもプロスタグランジン、ロイコトリエン、サイトカイン、補体因子などが関与しており、多面的な炎症反応が起きます。
好塩基球・肥満細胞の機能異常:感受性が上がっている、あるいは制御機構が壊れている場合に症状が反復します。
感染・炎症・内臓疾患:慢性炎症(歯科・副鼻腔・慢性扁桃炎等)や甲状腺自己免疫(橋本病など)との関連が指摘されることがあります。
薬剤・食物・環境因子:特定薬剤(例:NSAIDsなど)、アルコール、極端な温度・日光・圧迫などは誘因となりうる。
物理性蕁麻疹:圧迫(圧迫蕁麻疹)、寒冷、温熱、運動誘発など、物理刺激で出るタイプもある。
病態は単純な「アレルギー反応」だけでは説明できず、免疫学的・神経血管的な要素が重なった複合的機序であることが理解されています。
自律神経との関係 — ストレスと皮膚免疫の橋渡し
自律神経系(交感神経・副交感神経)は皮膚の血管調節、炎症反応、免疫細胞の働きにも影響を及ぼします。慢性蕁麻疹と自律神経の関係は臨床的にも重要です。
ストレスと交感神経活性化:心理的ストレスは交感神経を活性化し、ノルアドレナリンや関連物質を介して肥満細胞の反応性を高めることがあります。その結果、刺激に対して過敏にヒスタミン等を放出しやすくなります。
迷走神経・副交感の低下:副交感神経が十分に働かないと炎症の制御が不十分になり、慢性化しやすい傾向があります(自律神経のバランスが重要)。
神経因性炎症:皮膚末梢の知覚神経から放出される物質(神経ペプチド)が血管透過性や肥満細胞を刺激し、かゆみ・発赤を誘発する。自律神経と感覚神経は互いに影響を与えるため、ストレスや睡眠不足で症状が増悪することが多い。
睡眠・生活リズムとの相互作用:睡眠不足や夜間覚醒は自律神経の回復を妨げ、炎症や発疹の再発リスクを高めます。
臨床的には、ストレス管理・睡眠改善・リラクセーションが症状のコントロールに寄与するケースが多く見られます。自律神経を整えることは再発予防の重要な一手です。
東洋医学から見た慢性蕁麻疹
東洋医学(中医学)的には、蕁麻疹は総じて「風(ふう)」と関連づけられます。風は“動く”性質を持ち、皮膚に浮腫や移動性の発疹を作る特徴が蕁麻疹と合致します。慢性化の背景には「気血の不足」「脾(消化・運化)の弱り」「腎や肝の失調」「湿や熱の停滞」などが考えられます。代表的な弁証パターンと着眼点は次の通りです。
風寒襲表(ふうかんしゅうひょう)型
臨床像:発疹が白っぽく、冷えや寒さで悪化。かゆみは比較的強い。
攻法(着眼):解表散寒(風寒を散らす)。代表穴:風門(BL12)、風池(GB20)、合谷(LI4)。風熱(ふうねつ)型
臨床像:発赤が強く熱感を伴い、赤く熱っぽい蕁麻疹が出る。飲酒・辛い物で悪化することが多い。
攻法:清熱解表。代表穴:曲池(LI11)、合谷(LI4)、大椎(GV14)。痰湿阻滞(たんしつそたい)型
臨床像:体が重だるく、痰や湿が停滞している印象。発疹が盛り上がって消えにくい。
攻法:利湿化痰、健脾(脾を助ける)。代表穴:陰陵泉(SP9)、豊隆(ST40)、足三里(ST36)。気血両虚(きけつりょうきょ)型
臨床像:慢性的で体力が落ち、発疹が淡く出やすくなる。疲労や倦怠感を伴う。
攻法:補気養血。代表穴:足三里(ST36)、気海(CV6)、脾兪(BL20)。血瘀(けつお)型(慢性の瘀血)
臨床像:刺すような痛みや色調の変化、慢性化して滞りがある。
攻法:活血化瘀。代表穴:血海(SP10)、委中(BL40)等。
東洋医学は「全身のバランス」を見て配穴を決めます。蕁麻疹は再発しやすいため、即効的に痒みを抑える局所アプローチに加えて体質(脾腎肝)を整えることが長期改善に重要です。
鍼灸で期待できること
かゆみ・発赤の短期緩和:局所や関連経穴への刺激で血管透過性や神経性炎症を抑制し、痒みや発赤を和らげることが期待されます。
自律神経の安定:内関(PC6)・神門(HT7)・百会(GV20)などを用いて交感神経の過緊張を鎮め、再発しにくい体質へと導く補助効果。
体質改善(脾気・腎気の補強、湿熱の除去):慢性化の背景にある内臓の弱りを補うことで再発頻度の低下が期待できる。
ストレス緩和と睡眠改善の支援:ストレスが誘因となる場合、精神面の安定を図ることで症状軽減に繋がる。
※鍼灸は補完療法であり、重篤な全身症状(呼吸困難、急速な顔面浮腫等)がある場合は速やかに医療機関を受診することが必要です。
まとめ
慢性蕁麻疹は単なる「皮膚の異常」ではなく、免疫学的・神経学的・自律神経的・生活習慣的な要素が複雑に絡み合う症候群です。西洋医学では肥満細胞脱顆粒や自己免疫機序が重要視され、東洋医学では「風・湿・熱・気血の不足」など体質の観点から診ます。鍼灸は自律神経の安定化、痒みや炎症の局所緩和、体質改善を通じて慢性化した蕁麻疹の補助療法として有用です。まずは専門医による評価で重篤な原因を除外したうえで、自律神経を整える生活習慣改善と東洋医学的アプローチを組み合わせると改善の幅が大きくなります。お悩みの方はお気軽にご相談ください。
関連記事はこちら
info_outline平井鍼灸院
- 住所
- 〒132-0035
東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号
 03-3683-7670
03-3683-7670
- 営業時間
- 火金 10:00~20:00
水 12:00~20:00
土 9:00~17:00
日 9:00~16:00 - 休業日
- 月曜・木曜・祝日
- アクセス
- JR総武本線平井駅から徒歩1分