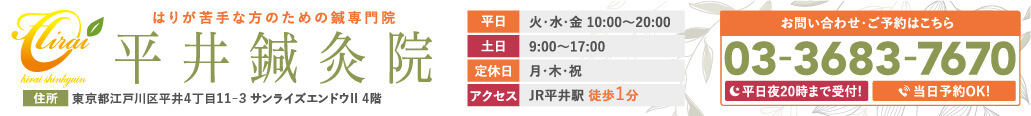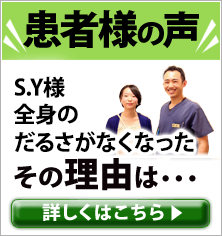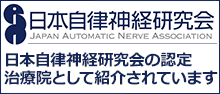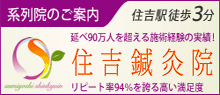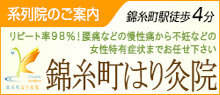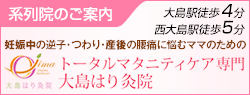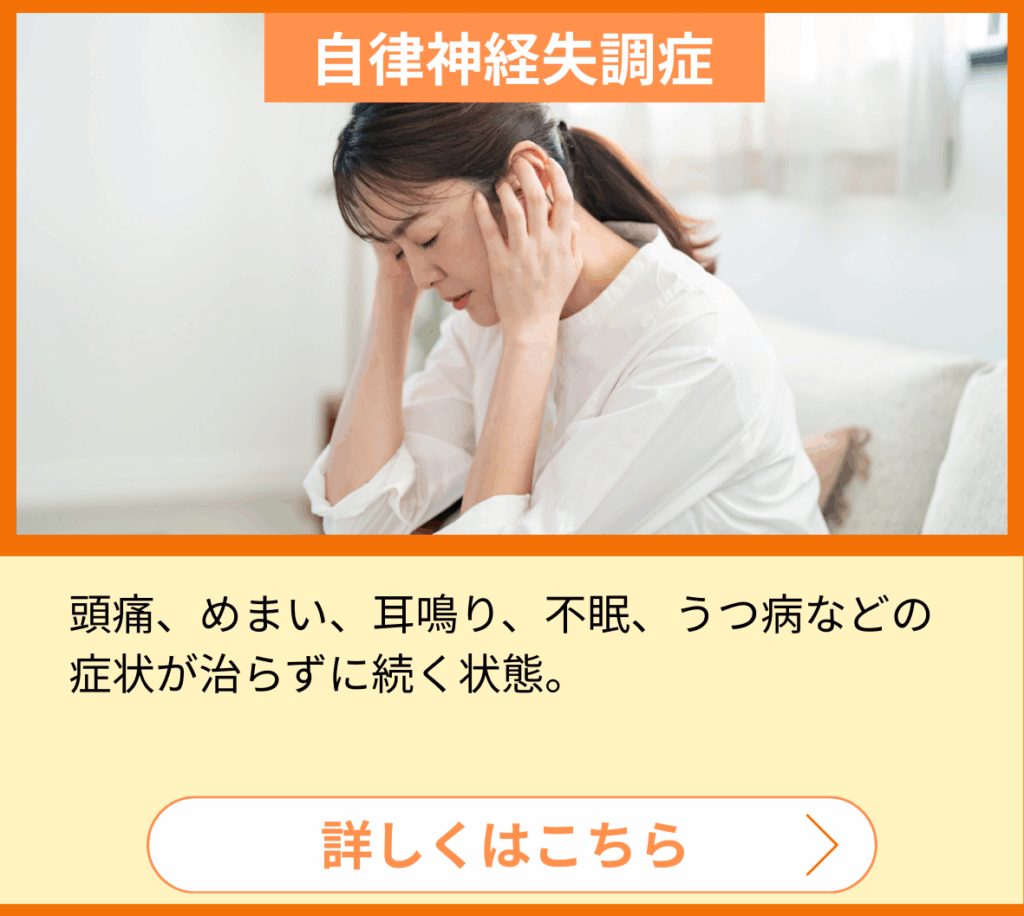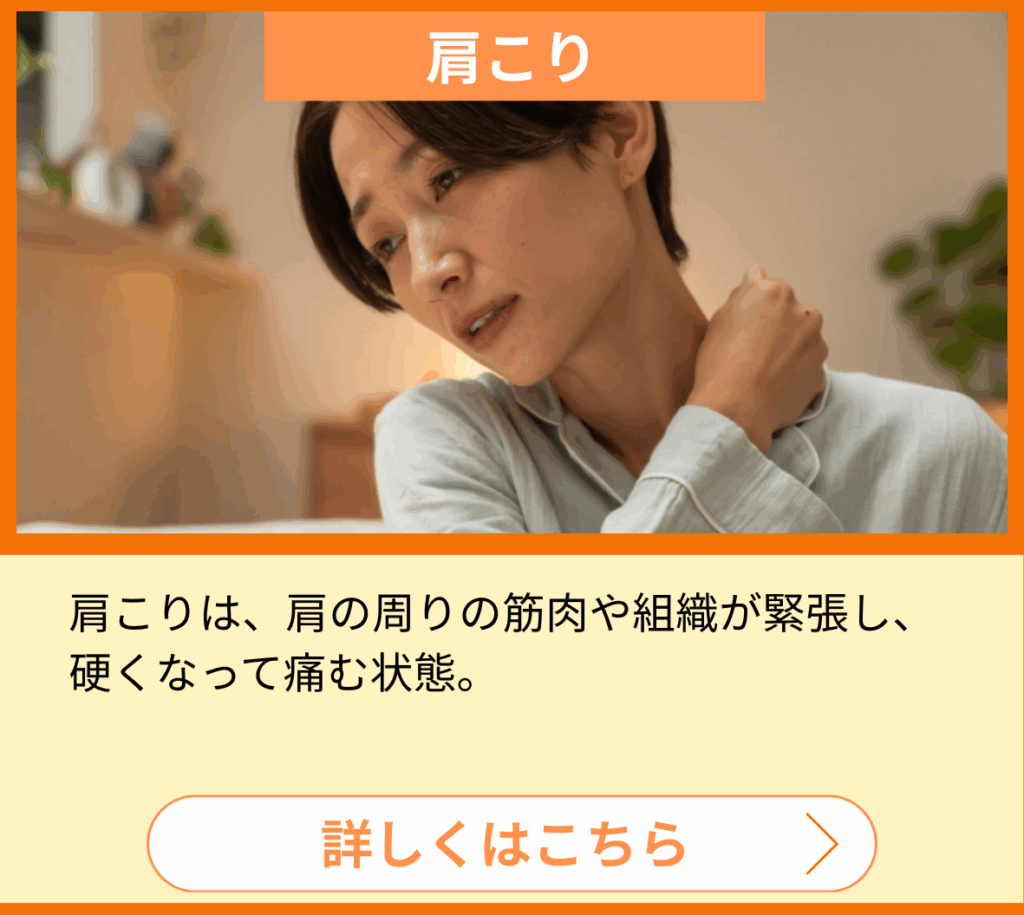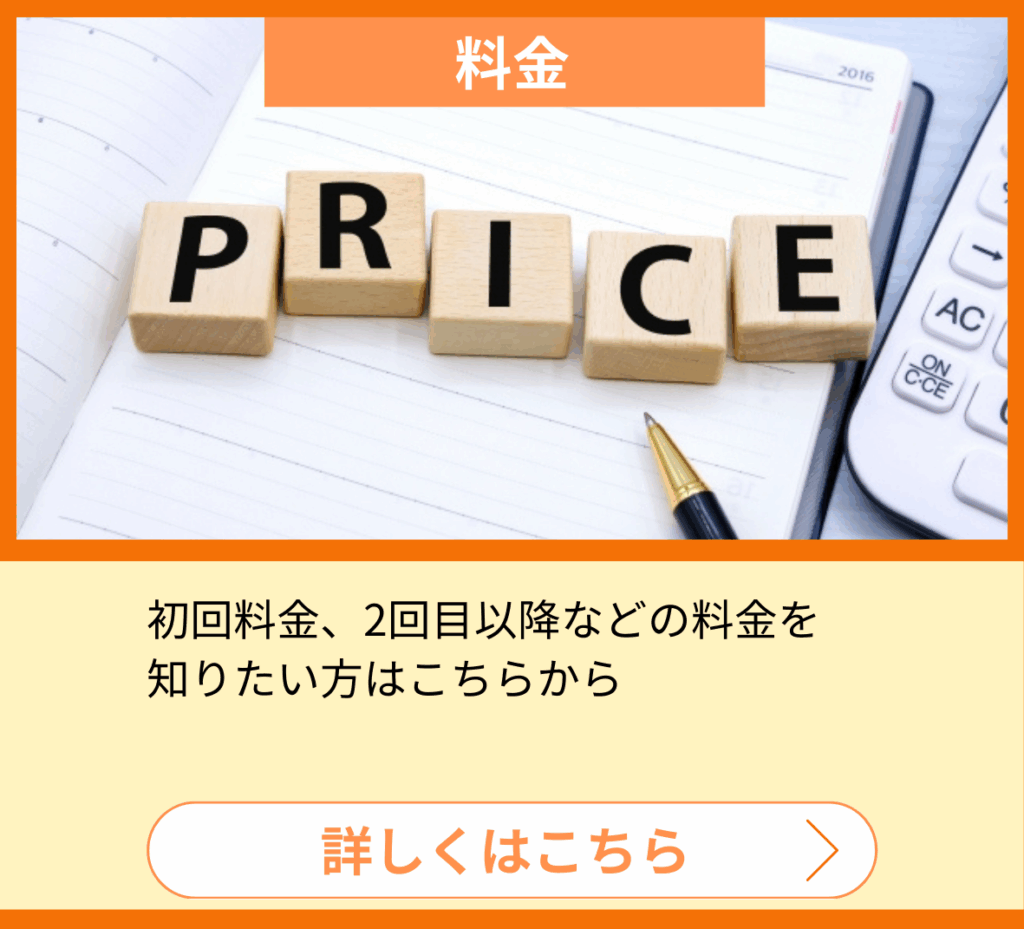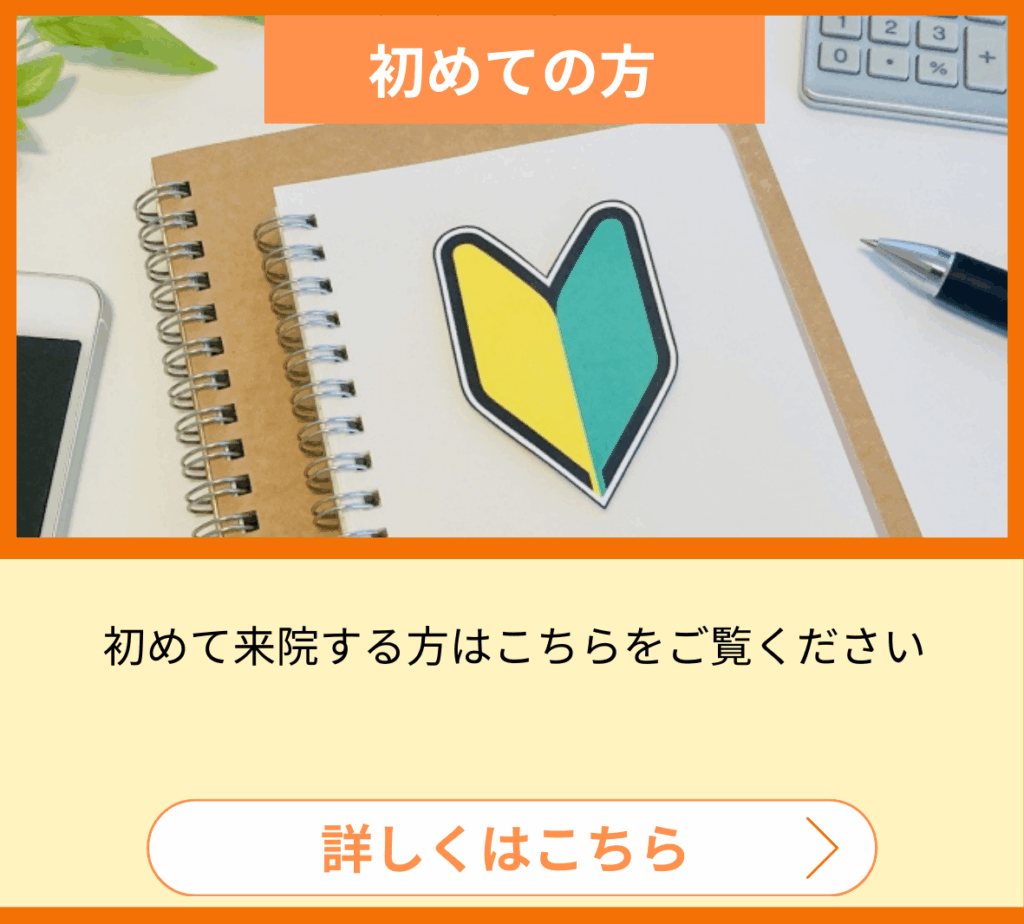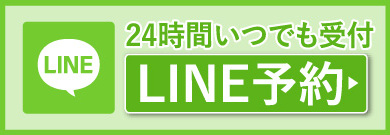季節の変わり目の不調はなぜ起きる?自律神経とからだの仕組みを解説
こんにちは。鈴木開登です。
「季節の変わり目になるといつも体調を崩す」「朝晩の寒暖差で頭痛やだるさが出る」――こうした訴えをよく伺います。季節の移り変わりは気温・湿度・日照時間・気圧・アレルゲンなどが同時に変化するため、体の調整機能(特に自律神経)が影響を受けやすくなります。ここでは、季節変化による不調の仕組みを西洋医学的に整理し、自律神経との関係、さらに東洋医学(中医学)的な見立てで深掘りします。

季節の変わり目に出やすい不調(例)
朝晩のだるさ・倦怠感、やる気が出ない
入眠困難・中途覚醒などの睡眠障害
頭痛(緊張型、天候変化に誘発される片頭痛など)
胃腸症状(食欲不振、下痢・便秘の増悪)
関節や古傷の痛み、こわばりの増強
鼻づまり・咳・痰など呼吸器症状の悪化(花粉期など)
立ちくらみ・めまい・低血圧様症状
気分の落ち込み、イライラ、集中力低下
これらは単独で出ることもあれば、複数が同時に現れて生活の質を下げることが多いです。
西洋医学的なメカニズム(季節変化が体に与える影響)
体温・体液の恒常性負荷
気温や湿度が短期間で変化すると、身体は血管の収縮・拡張、発汗、皮膚血流の再配分などを繰り返して体温を保とうとします。この“恒常性(ホメオスタシス)”の維持に自律神経がフル稼働するため、短期的には疲労を感じ、長期的には倦怠感や不眠などが生じやすくなります。
概日リズム(サーカディアンリズム)の乱れ
季節に伴う日照時間の変化はメラトニン(睡眠ホルモン)やコルチゾール(覚醒・ストレスホルモン)の分泌リズムに影響します。朝日を浴びる時間が遅れたり夜間の光環境が変わると、睡眠の質や覚醒リズムが崩れやすくなり、日中の疲労や集中力低下を招きます。
気圧変動と血管・内耳への影響
気圧が低下すると頭蓋内圧や副鼻腔内圧、内耳の圧バランスが変動しやすく、片頭痛既往のある方や内耳感受性の高い方は頭痛やめまいを起こしやすくなります。血管の微細な反応が引き金となり、頭重感や不調が現れます。
アレルゲン・感染症の増減と免疫の反応
季節の変わり目は花粉やハウスダスト、ウイルスの活動変化が重なり、局所的な炎症(鼻粘膜・気道)や全身の免疫反応が起こりやすい時期です。慢性炎症の亢進は倦怠感や睡眠障害の要因となり、既往症の悪化につながることがあります。
自律神経との関係(なぜ自律神経が鍵になるのか)
自律神経は外界の情報(温度・光・匂い・運動・心理的ストレス)を受け取り、交感神経と副交感神経を切り替えて体内環境を保っています。季節の変わり目は、この“スイッチング”が乱れやすく、次のような影響を及ぼします。
断続的な交感神経刺激:寒暖差や気圧変動が繰り返されることで交感神経が何度も刺激され、筋緊張・血管収縮・不安感が増します。
副交感神経への移行障害:回復・消化・睡眠を促す副交感神経への切り替えがスムーズに行われず、睡眠の質が低下し回復が不十分になります。
感覚過敏・中枢の反応性上昇:気候やアレルギーによる不快刺激が慢性的に続くと、中枢神経での感受性が高まり、軽度の刺激でも強い不調として自覚しやすくなります。
体内リズムのズレ拡大:日照や活動時間の変化がホルモンリズムをズラし、結果として自律神経の昼夜リズムも乱れる悪循環となります。
このため、季節の変わり目に出る不調はしばしば「自律神経の調整不全」=体のスイッチの切り替えがうまくいかない状態と表現できます。
東洋医学(中医学)的見立て:季節変化と体の「気・血・津液」
東洋医学では、自然の四季と人体は密接に連動しており、季節の変わり目は「気(エネルギー)」「血(栄養)」「津液(体液)」のバランスが乱れやすい時期と捉えます。季節ごとの特徴的な不調と中医学的な見方は次の通りです。
春の変わり目(肝の影響)
肝は気の流れを調整します。春は気が動きやすく、花粉や寒暖差で肝の調整機能が乱れると「肝気鬱結(気の滞り)」や「肝陽上亢(のぼせ・頭痛)」を招き、頭痛・イライラ・筋緊張が現れやすくなります。梅雨〜夏(湿熱・痰湿の影響)
高湿度は体内に「湿」を生み、消化機能(脾)の働きを弱めます。結果、重だるさ・むくみ・食欲低下・下痢など「痰湿・湿邪」による症状が出やすくなります。秋の変わり目(燥邪の影響)
乾燥が強まる季節は肺が影響を受けやすく、喉や鼻の乾燥、皮膚乾燥、乾いた咳や不眠が出やすくなります。体液の不足が顕在化する時期です。冬の変わり目(腎陽の影響)
寒さは体の陽気(温める力)を消耗し、腎の機能低下(腎陽虚)として現れることがあります。冷え・関節痛・疲労感・頻尿などが出やすくなります。
中医学では、まずこれらの「季節特有の病理」を弁証(タイプ分け)してから、臓腑のバランスを整えることで季節適応力を高める方針を取ります。季節ごとの変化を見越した体質づくりが重要です。
まとめ
季節の変わり目に体調を崩す原因は多面的で、気候要因(温度・湿度・気圧・日照)と生体側の適応機構(自律神経・免疫・内分泌)が相互に影響し合って生じます。西洋医学は原因や危険なサインの把握に優れており、東洋医学は季節に合わせた体質調整という視点で補完的に機能します。季節の変わり目は誰にでも起き得る反応ですが、繰り返しや日常生活への支障が強い場合は、専門家に相談して原因の精査と対策を検討することをおすすめします。
関連記事はこちら
info_outline平井鍼灸院
- 住所
- 〒132-0035
東京都江戸川区平井4丁目11−3 サンライズエンドウII 4階 - 電話番号
 03-3683-7670
03-3683-7670
- 営業時間
- 火金 10:00~20:00
水 12:00~20:00
土 9:00~17:00
日 9:00~16:00 - 休業日
- 月曜・木曜・祝日
- アクセス
- JR総武本線平井駅から徒歩1分